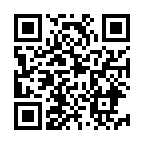
大澤博隆 さま
第63回(2025年)日本SF大会(蒲田開催=かまこん)で講義拝聴&著書拝読させていただいた、之人冗悟(のと・じゃうご=第四回:2017年日経星新一賞グランプリ『OV元年』作者)です。
8/31(日)の『日経星新一賞について語ろう』の部屋でお伝えした通り、前日8/30(土)『環境問題や生命科学をSF的思考で考える』のワークショップで初めて接したsci-fi prototypingの概念と実態について、より詳しく知りたいという衝動に駆られて読んだ『SFプロトタイピング』(編著=大澤博隆/難波優輝:編著&監修=宮本道人:早川書房)は、最初から最後まで一切ダレることなき知的ワクワク感で読み切ることができた「ここ十年来で一番”払ったカネ以上の価値”がある本」でした。
「星新一賞つながり」で大澤さんの名刺を頂戴したのも何かの御縁でしょうし、二千円弱であれだけの「sense of wonder:脳内攪拌感覚」を味わわせてもらったお礼の意味も込めて、「数日前まで<SFプロトタイピング>の用語すら知らなかった空想的(だけどプロじゃない)物書き」が抱いたあの本(ひいては「SF」とその周辺事情、さらには「日経星新一賞」)に対する素朴な感想を申し述べさせてもらいたいと思います・・・ただ、「感動&感謝」一辺倒では(角砂糖3ケぶっ込んで差し出されたコーヒーカップみたいなもので)受ける大澤さんの方でもたまったもんじゃないでしょうから、なるべく(blamingではなくcriticalな意味で)批判的な形で(destructiveではなくconstructive & suggestiveな形での)疑問・懸念を提示するような内容にしようと思います ― 『OV元年』の作者としての之人冗悟から舞い込んだメールには「予定調和裏切り文物」が期待されるのが当然でしょうからね(・・・救いようのないdystopiaまでブッ飛んだりはしませんから、どうか安心してお読みください・・・)
■第一章)why sci-fi?:どうして「SF」なの?■
最初に自分が抱いた疑問は、「SFプロトタイピング」が「現実には存在しない何か」を「あたかも存在するかのごとく扱う」ことだとしたら、それは「思考実験」という使い古された用語で事足りるのではないか、というもの・・・ですが、この疑問は「歴史に”IF:もしも”を持ち込んでみる」というタイプの「思考実験」との対比ですんなり氷解しました ― 「もし本能寺の変で織田信長が暗殺されていなかったら、歴史はどう変わっていただろう」というタイプの思考実験は「既に敷かれた現実のレールの上を走る列車を、別の線路に切り替えて走らせ続けて、どこに行き着くか見てみよう」というものであるのに対し、「SFプロトタイピング」のほうは「レールも何もない状態」から想像のおもむくままに列車を走らせるもの ― その乗り物は「地を這うレールの上を走る列車」である必要すらなくて「地球温暖化の激化でもはや大深度地下交通網以外に移動手段がなくなった未来の地球の地底超特急」だったりするかもしれない ― 「既知の現実を出発点とする知的遠征=forecasting:現在から未来へと思考の影を長く引っ張ること」と「未知なる未来を出発点とする想像的冒険=(forecastからの逆成語で)backcasting:思考の影を生じる光の投影方向を<現在⇒未来>ではなく<未来⇒現在>へと転じてみること」とでは思考・想像の質が全く別物/正反対/コペルニクス的転回なわけですからね。一昔前の生真面目な学校の先生や真っ当な企業経営者の前で語れば「なぁ~にを夢みたいなこと言ってるんだねキミは? もっとちゃんと地に足の付いた考え方をしてくれないと困るよ」と説教されそうな「ブッ飛んだ空想」を、「現実離れした絵空事だから」という理由で一顧だにせず切り捨てるのではなく、「未来の数ある可能性の一つ」として真剣に模索する態度が「SFプロトタイピング」だとしたら、それはそれで「SF」という名を冠したことにも納得が行く気がします。
視点を変えて言えば、そういう「現実離れした突飛な空想」にまで手を伸ばさないことには「今ある現実の延長線上」に持続的発展可能性をもはや見出せないところまで、今の世の人間達(特に、企業)は「成長打ち止めのどん詰まり状態:developmental impasse」にある(ことを自覚せざるを得ないところまで追い詰められている)ということなのでしょうね ― 「sustainable development goals:持続可能な成長目標:SDGs」なる近年のbuzz-word(誰も彼もがブツブツ唱えて世の中全体を<蜂の巣周り>みたいな喧噪状態に包んでる流行語)そのものが「現実には存在しない絵空事」であり「絵空事へと手を伸ばす<ないものねだりのおまじない>」であることを(よほどオメデタイ人以外は)誰もが薄々感じ取っている時代だからこそ、「絵空事から出発する空想論的な未来模索法」へと手を伸ばそうという人々が ― 「地に足の付いた考え方」しかしない&できないタイプの実直な人々の間でさえも ― 増えてきた、ということなのでしょう・・・で、そういう人達へと「販路を伸ばすためのチチンプイプイのおまじない」が『SFプロトタイピング』の本の帯に踊る「ビジネスは想像力。SFを通じて未来を試作=プロトタイプし、逆算&ストーリーの力で、製品/事業開発・組織変革の突破口を開く(・・・マイクロソフト、日産、清水建設ほかで続々採用の画期的手法!)」(文責=早川書房・・・たぶん、編著者である大澤・宮本・難波にとっては<あ~・・・まぁ~・・・本を売るためにはしゃぁねぇけど、そういうウタわれかたされちゃうと、実は後々かなり困るんだよねぇ・・・>的なhype:後々きっとハジけちゃう風船っぽい宣伝文句)である、と・・・そういう想像まではきちんと導いてくれる本でした・・・オビに引かれて「未来への突破口(の、現実的な最適解)」を引ったくるべくあの本を手にした「地に足の付いたまま、飛べないタイプの企業のおエラいさんたち」の読後感がいかなるものになるか ― 「チチンプイプイ」に振り回された挙げ句「何一つ現実的な未来への突破口も与えてくれないおまじない本」と感じて(ヘタすりゃ途中で)放り出しちゃうのか、はたまた「脳味噌引っかき回されてちょっぴりハイ」になる感覚(sci-fi sense of wonder)を(遅ればせながら)味わって「うん、ウチでもこの<SFプロトタイピング>ってやつ、採用してみよう!」という気分になってくれたのか ― そっちの方への興味関心は(ハヤカワさんや編著者のみなさんほどには)ない之人冗悟なんですが、「<本書く側>と<本売る側>との思惑乖離率がかな~り高い本だなぁ」という感覚に思わずニヤリとしちゃったその後で、「この<編著者>と<ハヤカワ書房:販売促進担当部>との思惑の隔たりが、そっくりそのまま<SFプロトタイピング提唱者>と<潜在的顧客>との間に横たわる溝の深さを示す(企まざる)metaphor:隠喩になってるわけだなぁ・・・う~ん、さすがはSF大手のハヤカワから出てる本だけのことはある」という不届きな感想まで突き抜けてしまったことを白状しておきます ― そういうレベルであの本の帯を笑えた人なら、あの本の素晴らしさを本当にわかった読者である、ということになるのでしょう・・・こういう斜め目線で見たあの本は「読後に改めて眺めれば、実は冒頭部に<意外なオチ(≒編著者にとっては心外なオビ)>が付いていた、という希有なタイプのショートショート」と呼べるのかもしれませんね(・・・読後の興奮でちょっぴり悪ノリしすぎちゃいました、編著者のみなさんの不興を買いましたらゴメンなさい・・・まぁ、本はちゃんとカネ出して買ったので、それに免じて許してください)。
次に、「現実には存在しない何かを、あたかも実在するかのごとく扱う」という思考形態には、「reify」という英単語が存在する(名詞型なら「reification」となる)ので、それを使えば(べつに「sci-fi prototyping」なんて新語を持ち出すまでもなく)事足りるのでは、という想念も浮かんだ・・・ものの、これは「そもそもreify / reificationという語は、<現実逃避>としての<妄想>に言及する、という否定的色彩が濃密」という言語学的慣用を踏まえれば、「そんな悪い手垢の付いた古い語は、未来の可能性を<絵空事>としてではなく現実にあり得る<可能性の模索>として考察する思考実験を表わす肯定的な用語としては、使えない」ということであっさり却下・・・この「reified:現実ではないものが、あたかも現実のごとく扱われている」という表現に代わるものとして、サイバーパンク系のアメリカ人SF作家 Bruce Sterling が「diegetic」なる珍奇な語を「<架空の物語>の中で<現実>として扱われている」という意味で用いている、というインプット(p.258)に接して、「なるほど、<MATRIXは実在する>という前提の上に立って物語世界に没入しないといけないわけね・・・ということは、『Blade Runner』は十回以上観たけど『Neuromancer』は一読して頭痛くなって放り投げちゃった<70年代の古いSF読者>みたいな層は、いよいよ本当に時代遅れになるわけだ」という形で納得しつつ、もう一つ語源学的にも納得したくてオンライン英語語源辞典で「diegetic」なる語の成り立ちを調べたかったのだけれど、結局「dietetic:食餌の」しか与えられずに消化不良に終わってしまいました・・・今のこの便利なネット時代、ガンバって食い下がればいずれきちんとした「diegetic」の語源・来歴に辿り着けることでしょうが、まぁいずれにせよ「知ってる自分はエラい/知らない連中はトロい」系の排他性の臭味を(無自覚のうちに)振りかざすタイプの人々が大喜びする類いのesoteric jargon(部外秘専門用語)であることは一目瞭然の語であって、一般人向けに「sci-fi prototyping」の解説&普及を図るつもりであれば、「diegetic」なんぞは潔く捨て去って「fictionally real:虚構世界の中では真実である」あたりの2語構成で地道に表現するのが(サイバーパンク文学者ならともかく、SFプロトタイピング伝道者としては)正しい態度であるように思われます ― 布教対象層が「SFマニア」だけ、というのなら話は全く逆ですが、たぶんそうではないはずなので。
そんなこんなで、現時点で存在する何か(技術とか制度とか生物とか)の延長線上でその<先々の姿>を思い描くのではなく、今はまだ存在しない何かを<物語世界の中では既にもう存在する>という前提で扱うことで、今現在の現実とは接点のない(地続きではない)「<あり得る未来>の様々なありようを想像(を通して創造)しよう」という考え方を「SFプロトタイピング」という用語で表わす・・・というのはどうやら「日本独自の習わし」のようで、アメリカでは「design fiction:虚構としての意匠」・「speculative fiction:未来について考える枠組みとしての虚構」・「diegetic prototyping:物語の中の実在物として未知なる何かに具体的な形を与えること」・「future thinking:未来思考」等々、その呼び名はまちまち(p.227)・・・ということになると、次なる疑問は「日本ではなぜ<未来>とか<物語内>とか<虚構>とかの形容詞の代わりに<SF>というラベルが付くのか?」ということになるわけですが・・・ここで「今はまだ存在しない何か」を「あたかも現に存在するかのごとく」扱うという心的態度が、アメリカでは「虚構として」・「物語として」・「未来学として」ごくごく自然な形で(=べつに「SF:空想科学物語」なんぞという大袈裟な冠をかぶらずとも)成立するのに対し、日本では「SF的な態度で」と断わり書きを入れねばならぬほど「地に足の付いていない考え方」に対する拒絶反応が(アメリカとの相対比較で言えば)根強いのだろう、という考えに至ります ― 「これはあくまでSF物語として話を進めます、いいですね?」と断わらないことには「空想を通して未来の創造ができない日本人」と、「<虚構ではあるが物語世界の中ではリアル>なものとして仮想現実の中での<何か>を思い描いたり<誰かの立場>を<自分事>としてロールプレイしたりする芸当が自然にできるアメリカ人」との対比を、「SF」という「冠の重さ」が示しているような気がしてくる(というか、現実の日本人の空想力&想像的創造力の限界点を再確認させられる)わけです。
さらに穿った物の見方をするならば、「SFプロトタイピング」なる用語を創造することで、「原稿料だけで食って行くには苦しいSF作家」のための「新たなる創造分野(・・・ぶっちゃけて言えば、稼ぎ口)」を作ってしまえ、という商業的思惑がこの「<SF>プロトタイピング」なる用語の背景にあるのかもしれない、という空想も ― 星新一のエッセイの中で語られていた『士・農・工・商・SF作家』という(今となっては「政治的にぜんぜん正しくない」けど「経済的現実としては実はいまだに正しいかもしれない」)SF作家の社会経済学的序列の低さが脳裏にこびりついて離れない1960年代生まれの人間としては ― ごく自然に沸いてくるわけです・・・仮にこの”邪推”が”事実”だという前提で話を進めた場合、そこから自ずと導出される「SF業界の未来図」は、「(1)個人の脳内から沸いて出た<絵空事>を描き続ける<在来型SF作家>」と「(2)個人創作もするが、外注(主として、企業)の求めるところに従って<SFプロトタイピング>という形の<オーダーメイドの絵空事>を納品する<ニュータイプ理系ライター>」とに二分されることになるでしょう・・・「個人的創作物のみ」でメシが食えるSF作家(=その名前だけで本が売れるような大御所)は今のSF業界では絶望的なまでに少ないはずなので、大方のSF作家(その多くは”自称”のレベル)は「sci-fi prototypist:SFプロトタイプ、請け負います」という肩書きで「カネになる企業・学校等からの外注仕事」で稼ぐ道を必然的に志向するようになるでしょう・・・その先に待つものは・・・おっと、「dystopiaまでは飛びません」という約束でしたから、ここはただ「そういえば、芥川龍之介に『蜘蛛の糸』とかいう作品があったっけ」とかつぶやくだけで、この路線での遠出は打ち切っておきましょう・・・
次なる疑問は、「既存の職業的(あるいは学問的)枠組み」との対比構造について ― 想像的創造の出発点/到達予定地点が「既存世界(の中で連綿と続く”過去”から”現在”に至る連続した=linearな流れの中の”近未来”)」であるか「物語世界(の中で実在するものと前提されたものであるがゆえに、既存の現実世界との直列性=linearityを前提とはしないが、少なくとも現時点で人類が手にしている科学知識のフィルターで濾過した場合に”不純物”としてその可能性を排除されることなく残存し得る”架空的に現実的な未来:fictionally/diegetically REAL future”)」であるかの相違はあるにせよ(&その”realityに束縛されるlinearity”を断ち切るところから出発する心的態度にこそ革命的な意味がある、とは言えるものの)、「未来予測」という括りで言えば、この世界には既に「futurology:未来学」という学問が存在し、斯道の専門家(”自称”含む)として「futurologist:未来学者」という既存の職業がある・・・わけですが、「SFプロトタイピング」という思考実験の枠組みと、既存の「未来学的予測:future projected by futurology/futurologists」とは、対比構造を成すものなのでしょうか? 「-ology」という名を冠するための必須条件として「確固たる理論的土台を有する予測」であることを求められる(であろう)「futurology:未来学」の条件的制約として、「科学的に成立可能」ではあるが「現実的に存在しない」架空世界の「reified / imaginary / fictional / diegetic REALITY:仮想的現実」を出発点とする未来予測を立てることは「学問的自己否定:academic suicide」であるように(門外漢の目には)見えるので、「SFプロトタイピング」なる手法が「未来学(者)」の世界から生まれたものであるとは想像し難いのですが・・・それとも、「史実に縛られる歴史学」の世界から「自由に書ける歴史小説」の世界へと転身する作家がわんさか存在するように、「キミのその”未来予測”とやらには”現実的裏付け”が欠けている」の一言で自らの”納品”をあっさりボツにされる場面の多さにいいかげんウンザリした未来学者の誰かさんが、「そういう<既存の枠組み>からの脱却によって自分たちの<未来の可能性>を切り拓くためにこそ未来学者のオレ/ワタシにお伺いを立ててきたんじゃなかったの?・・・カンベンしてよ、もぅ・・・」ということで、そういう「頭がカタすぎて”未来”なんて到底思い描きようがない”現状の奴隷”のクライアントたち」を「未来の話がきちんと通じる話し相手」にするための「素人に想像の飛躍を促す思考実験の(最もとっつき易い)土台」として「”現状”の鎖につながれることなき”想像の翼”を(ジャンル的特性として特権的に)付与されている、SF(空想科学)」を「便利なツール」として引っ張って来ることにしたのでしょうか?・・・だとすれば、「SF(空想科学)ベース」を宣言した時点でその人は(過去から現在への連綿たる現実の延長線上にのみ未来を想定することを許される)「futurologist:未来学者」としての職業的肩書きを喪失することになると思うのだけれど・・・まぁ、「歴史学者<転>歴史小説家」が「歴史学者<兼>歴史小説家」としての便利な立ち回り方を学会サイドから拒否されて「歴史学との絶縁」を強いられたとしても別段その「学問上の肩書き喪失」を悔やんだりしないように(むしろ、「ワタシ、元々”歴史学”の世界の人間だったんですけど、今じゃあ学会を追い出されて”歴史小説家”としてメシ食わせてもらってます」という自己紹介の仕方で自らの知的優位性を印象付ける「ロストキャリアツール」として積極活用するように)、「ワタシ、元々”未来学”なるものをやっていたんですけど、あんまり誰も耳を貸してくれないんで、もっとずっとキャッチーなフレーズ&ツールとして”SF的手法による未来予測”というものを最近では用いてクライアントの理解を深めると同時に、クライアントがその”予測される未来”という”絵空事の世界”の住人であるかのごとく振る舞ってもらうことで、専門家の誰かさんがポン!と提出してきた”未来はきっとこうなる”の図を”抽象絵画を前にした鑑賞者”という立場で眺めるような態度ではなくて、”VR(virtual reality)ゴーグル付けてゲーム世界に没入する一般消費者”みたいな”immersive experience:没入体験”として、”発注元と納品者”という一方通行性のやりとりではない”interactive game:相互に作用を及ぼし合うゲーム”として共に作り上げて行きたい、ということで<SFプロトタイピング>という想像的創造の枠組みを使わせてもらってます」(・・・おかげで「未来学」の世界からは追い出されちゃったんですが、まぁ、元々「未来学者」なんて肩書きではメシ食えないし、思い描いた”未来”が物凄~いスピードで”現実”に追い越されちゃう流れが加速している今の世の中では”未来学”の未来は暗いんで、”未来学者”の肩書き喪失にも特段の悔いはないです、ハイ)・・・みたいな生い立ちを有する「SFプロトタイピング」なのでしょうか?・・・だとしたら、「未来学者の仕事を革命的にやり易くするための道具(facilitation tool)」として自分の仕事に<SF>という便利な道具を導入したつもりが、「未来学」という(元々かなり狭い)市場に<SF作家>(”自称”含む)という厄介な商売敵の大量侵入を許す風穴を開けてしまったことになる・・・ということで、この先「既存ベースの未来学」vs「空想ベースのSFプロトタイピング」の(職業的)対立の図式が展開することになる・・・その場合、単純な人数比から言っても行動様態の尖鋭性から言ってもこれはもう「SF作家側の圧勝」は目に見えている勝負なので、そう遠からぬ未来に於いて「futurology is an occupation of the past:未来学は過去の職業」ということになる・・・のかな?・・・そういえば、星新一に『コビト』とかいう作品があったっけ・・・というか、「便利なツールで仕事をラクにする」つもりが、「その便利ツールによって仕事を奪われる」の図は「AI失業」の使い古されたメタファーだよなぁ・・・あ、でも、このメタファー、あまりにも普遍的すぎて、その語り口に乗せられない「絶対安泰な職業」なんて、想像するほうが難しいんだよなぁ・・・あれ? 何の話してたんだっけ?・・・なんかよくわかんなくなってきちゃったんで、この路線もここらで廃線だな・・・
■第二章)cui bono?:・・・で、誰がどういう利益を得るの?■
件の『SFプロトタイピング』の本が(当方にとって)大変刺激的だったのは、「既存の現実の鎖につながれることなき自由な空想の飛躍」を「個人の脳内世界」で展開するのではなく「複数人数のインタラクティブプレイ」として実現するというその構図、その想像的創造の共作を実際に体験した人達の「!ワクワク感!」が紙面を通じて読者である自分にダイレクトに伝わってきたからです・・・が、そのめくるめく知的興奮の共同体験に想像を巡らす時、同時にまた次の疑問も(過去の自らの体験上)自然と生じてきます ― <diegetic/fictionally real future:物語世界の中で実在するものとして扱われる未来>を想像的に創造可能なイマジネーションを持った人物や、その想像世界の科学的現実性に疑義が生じた場合にこれを現実的に存在可能なものへと理知的に修正可能な専門知識を持った人物が、現実世界にいったい何人存在するのか? そうした人々を一堂に集めての知的共同制作としてのSFプロトタイピングが現実に成立する可能性は、どの程度のものなのか?
『SFプロトタイピング』の本の中で自らのワクワク感を(良い意味で”子供っぽく”)語る人達はみなそれぞれ「自らが自家薬籠中のものとする科学分野の専門知識」で理論武装したintellectual soldiers(知の兵士)ですから、自分の頭上を「見たことも聞いたこともない未知なる弾丸」が飛び交った場合、それを「恐怖の新兵器」としてひたすら畏怖して塹壕の中で縮こまったりはせず、その「魔法の弾丸」を何とか手に入れて分析してその弱点を発見するなりそこに技術的発展を加えて「自分側の新兵器」として戦場へ投入するなりといった道を(嬉々として)選ぶことでしょう・・・が、現実世界にはそのような「知的ヘンタイ人間(俗称、ヲタク)」なんて圧倒的少数しか存在しない・・・そんな「選ばれた少数の<知的ヘンタイ>の群れの中で、<絵空事>を<想像的現実>として共にアツく語り合う」という図式は、「sci-fi convention:SFファンの集い」そのものです ― そうした「知的相互作用」の中から「(あわよくば)<現実世界に実装可能な新たな何か>を生み出す」ことを目的(少なくとも、クライアントに対する説明の中では、主目的)として掲げている点に於いては、「ただ単にSFが好きだから、みんなして集まってアツく語り合う」という単純明快な<SFファンダム>とは別世界と言えますが、その「アツい空理空論のぶつけ合い」に没入可能なほどまでに「自らの知識&理論武装に自信のある<知の兵士>」以外の目からこれを眺めれば、それは「近寄り難いヲタクの輪」そのものです・・・実際、この之人冗悟自身、「第四回日経星新一賞グランプリ受賞者」という”SFっぽい冠”をかぶったゲストとして無料御招待いただいたからこそ今回の『第63回日本SF大会 蒲田大会(かまこん)』には(コワいもの見たさで)参加させてもらったわけで、そうした特殊な状況展開でもない限りは「自らの知性の刃を研ぎ澄ました自負のある知的兵士たち」の剣劇の場になんて、のこのこ出かけて行く気にはならなかったでしょう・・・自分は「自らの知性の刃の切れ味に自信がないごくフツウの人間です」などと謙遜するほど露骨に偽善的な社交性を有する人間ではないので、今回のSF大会に(6講座ほど)参加した結果の感想としては「自分の既知の知的枠組みのちょい上を飛び交う銃弾の雨あられ」の音は(それをニマニマ顔で楽しんでしまっている自分を発見して、こりゃマズイかも、と感じるほどに)心地良いものだったし、自分の周囲でその銃撃というか意味不明ギリギリミサイル乱発事象に遭遇した聴衆の反応として「やった!しっかり迎撃したぞ!撃ち落とすまでは行かずとも、少なくとも脳天爆殺されるほど自分はヤワじゃなかったぞ!」の自己主張を「あぁ~、はぃはぃ、例のアレね!」・「うんうん、わかる!」・「ぁはは、やっぱそうなるよね?」・「うわぁ、そこでそうくるか!?」といった「ゴキゲンな猫が喉の奥で奏でるゴロゴロ声」めいた(決して控え目とは言えない)会場内輪唱を耳にした時には、「ぁはは、やっぱそうなるよね、自ら好きこのんで<SF大会>に出向いてくる”自称”知のソルジャーたちの行動様態としては」という感覚に、思わず頬が緩むのを禁じ得ませんでした ― それは「ヘンタイ集団を遠巻きに眺めるしかない一般人」が浮かべる”冷笑”ではなく、自らも「ヘンタイの輪のこっち側の人」であることを認めざるを得ない(けど<SFファン>を自称できるほど斯界の事情に通じてもいなければ通暁する意志もない)変わり者としての”自嘲的失笑”、即席造語で形容すれば”類笑”としての「笑い」でした・・・壇上から聴衆へではなく会場内から壇上の話者に向けて「自分自身のヲタクぶりを大声で自慢するための発言連発」によってさしも辛抱強い<同類たち>をも鼻白ませてしまう「空砲機関銃乱射魔」も(少なからず)混入する「SFファンの輪」の”あるある図式”もまた当方の事前予測の範囲内の事象として(こちらはもうはっきりと”冷笑”を誘うばかりの”例証”として)眺めさせてもらう経験が(必要十分量をかなり上回るサンプル数で)得られたことも、今回の「かまこん」参加の収穫の一つでした・・・そうした経験を踏まえた上で想像を巡らせば、「SFプロトタイピング」の現場を「SFファンの自己顕示欲の修羅場(sci-fi self-display pandemonium)」へと貶めることなく展開するのは、実は、かなりの難題だろうという気がします ― むしろ「SFに関して一家言を持つ自負のある参加者」の自己顕示欲の非建設的暴発に対しては(”出禁”までは行かずとも)「ノイズ除去」のための特殊フィルターの用意が必要になるのではないかという気さえします ― このあたりは、「アイドルの追っかけやってるヤツを、そのアイドルのマネージャーとして採用する芸能プロダクションは、愚かである」というのと同じ構図でしょうね・・・そう考えると、「SFプロトタイピング参加者」の適格要件としては、「<知的武装>はしているが、はちきれんばかりの<SF知識>が無意味に暴発しまくる<sci-fi trigger-happy:SF乱射魔>ではない(or乱射乱撃を自制するだけの知的制御弁を有する)空想力豊かな人物」ということになるのでしょうね・・・実際、『SFプロトタイピング』の書籍の中に登場する”知的ワクワクの体験者たち”の多くは「SFファン」でもなければ「SF知識豊富な人物」でもなく、「ガンダムやエヴァンゲリオンの世界が日常的な<cultural background:文化的背景>として無自覚のうちに自らの<想像的未来許容度>を高めてくれていたことを、大人になってから再認識した知識人」のようですから ― そういう「例外的な知的精鋭集団」の輪の中での想像的創造の共同作業としての「SFプロトタイピング」なら、それはそれはもう無上の快楽でしょう・・・が、そうした舞台設定(or部隊編成)がいかに難しいかは、想像に難くないところです ― それだけに、その希有なる知的興奮の個人的体験を素直に「おもしろかった!」と報告する人達の声が羨ましいくらい心地良かったわけですが、そうした「例外的(であろう)事例」をもって「SFプロトタイピング礼賛」に走るのは、怜悧な第三者(とりわけ、クライアント側の企業)としては、あり得ない態度ということになるでしょう ― ということで、ここから先は「SFプロトタイピング、やってみたところで、実際成功するの? それで誰がどんな形でトクするの?」という批判的考察を試みることにしましょう。
「日経星新一賞組」の八島游舷さん(2018年グランプリ&優秀賞、2025年優秀賞)は、SFプロトタイピングによるグループディスカッションの実践を(「SF文物執筆」という個人的創造活動と併行して)行なっているようですが、彼の『筑波大でSFプロトタイピング講義したら』というワークショップ(2025/08/31)にお邪魔した時に伺ったお話では、この想像的創造の共作活動の参加人数としては「4人」が一つの目安になるようです ― 議論の風通しを良くするための人数としては妥当な気がしますが、問題はやはり「人数」よりは「人選」でしょうね・・・やたら大声で数多く発言はするけれどその発言が「自己顕示」以上の実質的内容を伴わない人物ではディスカッションの活性化につながらないどころか阻害要因になる・・・他者が何らかの可能性を提示したのを受けて「なるほど!」と納得してみせるけど実際には相手の心証を良くするための社交辞令の相槌としてそうしているだけの「reflective YES-man:反射的首肯人種」では参加させる意味がない・・・「次の議論を読み、それに対するあなたの意見を、賛成/反対のいずれかの態度を明確にする形で、論理的に述べなさい」というお題を出された時に「相手の論点の穴を見付け、そこを広げる形で自らの反対意見の拠点とする」という最も安直な芸当へと反射的に流れる(日本の受験生の圧倒的多数を占める)「他人の出した叩き台を叩くだけ」の「whack-a-mole player:もぐら叩き人種」の場合、その叩き方が「科学的に正しい反論による議論修正作用」の形で機能すればディスカッションにとって有益ではあるが、そもそもの「叩き台」を他の誰かが出してくれぬことには想像的創造過程に携わることができない「parasitic participant:寄生虫的参加者」でしかない・・・その「ディスカッションを進めるための土台・出発点・叩き台」となる「SF的物語」を描く役回りが「SF作家」という役割分担になるのかもしれませんが、そもそもその物語を「SF的」に成立させるための状況設定ぐらいは明確に提示してもらわぬことには、いかに空想力豊かなSF作家といえども何も描けない・・・というか、「空想的現実として物語を描く」その必然性を各参加者に認識してもらった上で「思い思いの物語」を「出発点・土台」として自ら描いてもらわないことには、「SF作家以外、全員が<イエスマン>か<もぐら叩き役>」という構図では、有益なディスカッション展開は望めないのではないか・・・とまぁ、だいたいそのあたりが「SFプロトタイピング、いかがですか?」という誘い掛けを受けたクライアント(企業・学校等々)から反射的に飛び出すであろう「お断わりの論拠」として想像できるわけですが、それに対する「sci-fi prototyping evangelist:SFプロトタイピングの福音伝道者」の<反撃手段>としてどういうものがあり得るか ― 件の『SFプロトタイピング』の書籍中で提示された事例には、次のようなものがありました:
<1>クライアント(主として、企業)の「自衛本能」に訴え掛ける:
●折角積み上げてきた企画内容が、いざ世間に公表したら総スカン、企画は立ち消えになり、それまでの努力は水の泡・・・というような骨折り損のくたびれもうけを避けるため、「企画の立ち上げ⇒練り上げ⇒公表」というリニアに現実的な一本道を辿る前にまず「その企画が実現された場合の世界とそこに暮らす人々の生活・意識は、どうなりそうか?」を「<絵空事>ではない<自分事>」として真剣に思い描いてみることで、「<企画倒れ>による資金・時間・労力の浪費を回避する手段」として「SFプロトタイピング」を推奨する(p.133~134)
●「こんなことをしていたらあなたたちの会社はそのうち訴えられますよ」・「時流に乗れていないですよ」・「これから世界的にいろんな倫理やルールが変わってくるなかで、内部からはこうした厳しい話は上がってこないのだから、私たち(注:この場合、<SFプロトタイピング推奨者>ではなく<社外コンサルタント>)の話を聞いたほうがいいですよ」といった形で「SFプロトタイピング」を推奨する(p.166~167)
・・・現実的に考えて、「企業向けアピール」として最も効果が上がる訴求点はこれでしょう ― 「あなたたちの会社を殺すのは誰だと思いますか?」(p.187)なんてのは最強の”殺し文句”になるでしょうね・・・もっとも、この種の説得手法は「あなた、この<聖なる壺>を買わないと、地獄に落ちますよ」という新興宗教の脅し文句と紙一重なだけに、振りかざし方を誤れば自分で自分の脳天かち割ることになるけれど・・・
<2>コンサルタントがクライアント(主として、企業)に対して提供し得る数あるサービスの一つとして「SFプロトタイピング」を組み入れ、状況に応じて適宜その適用を提案する:
●特に、クライアントにとって未知の分野での企画を立ち上げようとする際の「予期せぬ未来に足をすくわれてスッ転ぶ」ことを避けるための「転ばぬ先の杖」としてSFプロトタイピングというオプションを提示する(p.149)
・・・「既存の枠組みからの地続きの発展形」として生み出される「新製品開発」とは異なる出発点/着地点を持つ(べきである)「SFプロトタイピング」の提示の作法としては、「地続き展開の中で当然生み出されるはずの<実利的成果>」を求められるその他のコンサルティングオプションと並べて置かれたオプションの一つという位置付けになった場合、「会社にとって役立つ(=カネに結び付く)成果」を当然のごとく求められてしまいがちなだけに、「SFプロトタイピングとはそういうものではありません」という説明をよっぽど丹念に行なっておかない限り、クライアント側との思惑のズレからロクでもない結果に流れて行く危険性もありそうですね・・・そもそも、「丹念な説明」ではなく「体感的理解」を通してしか相手側に納得してもらえなさそうなのが「SFプロトタイピング」という気がするし・・・まぁ、「いま○○業界で話題になっている△△っていう新製品、あれを生み出す元になったのが<SFプロトタイピング>なんですよ!」みたいな実践例がポンポン生み出されるようになれば勧誘もラクになるだろうけど、そうした成功例に釣られて「SFプロトタイピング、ウチにも一つちょうだいな!」と言ってくるようなクライアントってやつは「現実的成果込みでね!」という態度で来る可能性が高いから、なまじ「青々と茂る隣の芝生」とかをいっぱい見せ付けちゃうと、「土づくりだの水はけ整備だのなんて面倒くさいことはいいから、お隣さんみたいな<見事に青い芝>だけちょうだい!」みたいな注文の洪水で溺死させられる予感大だけど・・・
・・・そういう「SFプロトタイピングに現実的効用の即効的見返りを期待する連中だらけ」の悪夢的展開を回避するための方法としては・・・
<3>「企業クライアントからの受注」以前の段階で「SFプロトタイピングの実践」が当たり前に行なわれる社会風土を作る(p.149)
・・・八島游舷さんの『筑波大でSFプロトタイピング講義したら』はその可能性を開く一例でしょう。宮本道人さんが『環境問題や生命科学をSF的思考で考える』の中で言及していた『science cafe:サイエンス・カフェ』のような「特定の専門知識を前提としない、一般市民参加によるSFプロトタイピング・ワークショップ」の目指すところも一緒ですね。いずれにしてもこれは一種の「教育改革」ですから、地方自治体レベルでの「草の根文化推進活動」ということになるのかもしれません・・・実際あの中華人民共和国では「科学・人類想像力研究センター」を通して「国ぐるみでのSFマインド醸成」に邁進している(p.230)みたいな話になっているらしいので。
・・・しかしながら、「SF的思考法の育成と、そこから生まれる想像的創造物の社会への実装」を国策として遂行する、というのは(いかなSF的思考をもってしても)この日本では考え難い気がします ― 「現実的見返りが見込め(そうに)ない企画にはカネなんて出せない」というのが「日本の企業&政府のマインドセット」であることは(何のてらいもなく「知識人」を自称可能な日本人なら)誰もが周知の事実であり修正困難な現実であるし、「現実的見返り」を期待された時点で「自由な想像力の飛翔による意外性のある未来図の創出」というSFプロトタイピングの効用に掣肘を加えることになるわけですから ― 中国のように「絶対権力が上から下々の人民の全てを統御しようとする国家体制」の下で「自由なSF的発想(による有益な成果の社会還元)」を国策遂行した場合、最終的にどのような展開が待っているか、という点に関しては(政治的に、ではなくSF的に)かなり興味深いところですが、同種の事を日本政府の下でやろうとした場合の結末は「上への忖度によって方向付けられた<お望みの結末>」以外の何もないのが最初から見えているので(どうせ最初から国はカネなんて出さないだろうから考えるだけムダかもしれないけど)「上からのお達しによる下々の民のマインドセット転換事業としての<SFプロトタイピングの社会普及>」という構図には、あまり現実的未来性が感じられません。
ここで、もっと根源的な(そしてかなり人聞きが悪い)話まで踏み込みましょう ― 「SFプロトタイピングを公的レベルで実現」という未来図を思い描いた場合、自分が何よりも懸念するのは、各人が<社会人として当然知っておくべきSF知識>というやつのレベルがどんどん上がり、「なぁにキミ/アナタ、こんなのも知らないの?」という形で「知ってる自分は、知らないアイツより、エラい!」と思い込みたがる(知性の水準が低い凡人が必ず陥る)「排他的<知識比べ>」が「有害無益な尖鋭化」を続けまくった挙げ句の果てに、「で、結局、そんなの知ってたからって実際上どんなトクがあるの? 知ってる人間が知らない人間よりどれくらいエラいわけ?」という形で「<知らない側>というよりは<知りたいとすら思わない側>の圧倒的多数の<フツウの人々>」からの拒絶反応の対象として<SF>が目の敵にされ、<SF>と聞いた瞬間に一般市民の心の扉が閉ざされてしまう、という暗黒の未来図です・・・これは決して「あり得ない空想」ではありません ― 現実に、日本の文芸世界の中で、一部知的エリート(を気取る連中)の排他的知識比べが究極まで高まった結果、かつて有していた<文芸的生命>を失うに至ったものが実在するのです ― それは「和歌(短歌)」です・・・ウソだと思うなら、今のこの令和の世で「五七五」の上の句のみの「十七文字の断片詩」に留まることなく「七七」の下の句を継ぎ足すことで「三十一文字のミニストーリー」を描く創造的営みに挑んでいる日本人の姿を思い浮かべてごらんなさい・・・あまり思い浮かびませんか?・・・そうでしょうね、江戸時代このかた、「31文字の短歌」は「17文字の俳句」にほぼ駆逐されてしまっているのですから ― そのきっかけを作ってしまったのが鎌倉時代初めに世に出た『新古今和歌集』であり、「新古今調」と呼ばれる意図的に難解な詠歌ぶりを我が物顔で振りかざした平安末歌人たちだったのです ― この故事、よほど心して「反面教師」とせぬ限り、「SF」にも起こりかねない由々しき事態であることを、ここに指摘しておきたいと思います・・・
・・・平安末期(から鎌倉最初期)に成立した『新古今和歌集』(1205年)に収載された和歌の数々を、和歌文芸を漢詩文の上に押し上げた記念すべき第一勅撰集『古今和歌集』(905年)のそれと比べた上で、「趣向・技芸の水準を極限まで高めた結果、<知らない人、お断わり>の自閉的閉塞性の中で衰えるべくして衰えた、日本の短歌」というこの之人冗悟の言い分を体感的に認識できる日本人が、今の世の中に何人存在するかはわかりませんが、「<ニューウェーブSF>の波に乗り遅れていまだに<空飛ぶ車>のイメージで<SF>を捉えてる人達って、ダメだよね?」という言辞と態度が「うんうん、まったくその通り!」という形で相互認証されてしまう世界が「SFファンダム」だとしたら、その行き着く先に「”新古今集”型自閉的衰亡の未来」を思い描くのに、さしたる想像力は必要ない・・・と(SFは読むけどSFファンではない)この之人冗悟は考えます ― 『新古今集』などという得体の知れぬ過去の文物なんて持ち出されても途方に暮れてしまう人に対してもっと具体的にピンと来る(あるいは、ガーン!とくる)イメージを与えるならば、「日本SF大会参加者の年齢層」だけで十分でしょう ― 今回の「かまこん」の案内冊子の冒頭にある「実行委員長挨拶」の中で櫻井晋さんが「近年、年次日本SF大会は参加者やスタッフの高齢化が深刻な課題となっていると感じています」と率直に述べていますが、この現象はなにも「SFを読む若者の数が減っている」ということではなく、「御同類の輪の中で、自分が有する<SF知識>のレベルを、再確認したり自慢したり足りない点があれば補足するための観測気球をブチ上げたりする」という<SFファンダム>の営みに加わってみたところで「<長年の蓄積>の分だけ幅を利かす<年長者の圧力>をヒシヒシと感じさせられるだけ」という形で発動される「自尊心防衛本能」に促されて「若いSFファンは、古参のSFファンの輪を避け、自分と同等かそれ以下の知識水準である(可能性が高いと見込まれる)同年齢の御同類との接触を好む」という至極自然な行動原理の必然的帰結なのだろうと思います・・・ですから、「日本SF大会に参加する若者の数が増えない」からといって「今の若者はSFを読まない」という危機意識へと短絡的に結び付ける必要は全くないと思います ― 「日本SF大会の未来」はともかく、「SFの未来」は常に明るいのです(描かれる世界がdystopiaだらけになったとしても、常に新たな形態の悪夢世界が描かれ続けるであろうと100%の確信をもって言い切れる点に於いて、SFという文学ジャンルは未来永劫不滅なのです・・・まぁ、それを書く人類が滅亡しちゃえばそれまでの話だけど) ― それでもやはり、「SFは、現実の科学や社会の変化に合わせて、絶えず新たな姿への自己変容を続ける特異な文学ジャンルである」という動かし難い事実がある以上、「進化するSFに合わせて自らの知識をも絶えずアップデートし続けぬ限り、いっぱしの<SF読み>を自称することはできない」という事実もまた不変であり、そこから「自らのSF知識がきちんとアップデートされているか否かの観測気球を打ち上げるための<ファン交流会>への参加は、SF読みに必須の嗜み」という現実も生じるわけであり、そこから「半ば<確認>、半ば<自慢>のための、自分自身のSF知識開陳」というSFファンダム特有のあの空気感が生まれるわけで、その空気の中で「自分は窒息せずにきちんと呼吸できた!」という発見のもたらす自己肯定感をこの上なく愛する「SF知のソルジャーたち」は「SF知識自慢機関銃トーク」を(空砲連発の形で)積極的に楽しんだりもできるわけです・・・この之人冗悟などは、そういう「ひけらかし」の形で開陳される知識には(嫌悪を抱く、とまでは言わぬまでも)さしたる効用も魅力も感じぬクチなので、今回の「かまこん」に参加して(大学時代とかに散々体験済みの)「自分が<知ってる>ことを他人に<知ってほしい>人達の(半世紀経過しても一向に変わらない)行動様態」を久々に体表感覚で味わう体験を「back in the 1980’s at 2025 sci-fi convention:2025年SF大会での<1980年代再訪>」という懐古体験として(ニマニマ笑って)愉しむことはできましたが、「ねぇキミ、こんなの知ってる?・・・え、知らないの?・・・いやぁ、それはちょっと問題だなぁ・・・え? なにキミ、『三体』(2015年ヒューゴー賞受賞の中国SF)も読んでないって!? ウソでしょ!!! キミっていったい何者?! え? <2017年日経星新一賞グランプリ受賞『OV元年』作者 之人冗悟>だって?・・・なんだよそれ?・・・ヘンなヤツ(プイっ!)」みたいなesotericism(排他性)の空気には(平然と耐えられるけど)体質的に馴染めないし、「知識試し/知識比べ/知識誇り」(注: 「知恵比べ」では決してない)を通しての自己優越性確認行動の舞台としての「日本SF大会」は「若いSF読者向けではない」という必然の構図を(『新古今和歌集』という大先輩を通して)思い浮かべる時、「ジャンルとしてのSFは不滅でも、SFファンダムという生態系の持続可能性は、ある特定世代限りであって、連綿と続くリニアなものには成り難い(成り得ない、とまで言えるか否かは、今後の日本SF大会の展開を観察することで結論めいたものが見えてくるかもしれない)」という怜悧な観測を立てています・・・「かまこん」の大会運営に奔走してくれた「(暗黒星雲賞に輝く)受付」のみなさんの情熱のアツさを思うと、何とも心苦しいdystopia的未来予測になってしまいますが、この「SFそのものには可変的成長性があるが、SF読者の輪の持続可能性はそう高くはない」という考察は、そっくりそのまま「SFプロトタイピング」に関しても言えるような気がします ― 「SFプロトタイピングには<non-linear backcasting:既存の現実との連続性の鎖から解き放たれて自由な、未来から逆算した現実予測>の無限の可能性がある・・・が、その営みへの<参加者>の輪は、思いの外、小さい」 ― そうなりがちな構造的条件としては、「SFプロトタイピングの<提供者側>が、<参加者>に対して要求する<最低限のSF知識>の水準」というものがあるわけで、「キミぃ~、<SFプロトタイピング参加者>としてノコノコ出てきておいて、こんなことも知らないわけ?! 頼むから『三体』ぐらいは読んどいてね!!!」みたいな排他的空気感の醸成が<日本SF大会>並みに当然許容されるなどと甘いことを考えているようでは、「SFプロトタイピング」の辿る道は「”新古今”的排他性自滅展開」以外、あり得ないでしょう ― 「SFなんて全然読んでなくてもいいし、SF関連用語の知識もゼロで構わないから、とにかくただ<既存の枠組み>に縛られて想像力の自由な飛翔に自ら鎖を付けてしまうような心的態度だけは脱却してね」という態度へと「SFプロトタイピング提供者側」が(自分は<SFファン>ではなく<SFプロトタイピング伝道者>なのだという意識改革を通じて)到達しておくことに加えて、「SF知識ゼロでもSFプロトタイピングに参加できる構造的枠組み」を(何らかの「飛躍的空想」の具体的な姿を顧客に提示する上で「既存のSF作品への言及」に依拠するという「SFファンとしては許されるが、サービス提供者としては決して許されない安易な態度」を脱却した上で)確立することができない限り(=「最低限、これぐらいはやっといてくれないと困るよ」という”宿題”を出しまくる”手抜き教師”であり続ける限り)、この「SFプロトタイピング」という潜在的に有益な思考実験は、一般人相手には成立しないでしょう・・・
・・・まぁ、「現場に出て身体を張って仕事してるわけじゃない<非ブルーカラー(≒知的エリート)会社員>たち」だけを相手に「コンサルティングのサービスオプションの一つ」としての「SFプロトタイピング」を提供する、というだけの話であれば、「あれこれいろんな本を読んでの<知識武装>の”宿題”」も、そっくりそのまま「自らの仕事&キャリアアップの一環」として参加者たち(=ホワイトカラーの中でも一番”まっしろけ”な会社員たち)にすんなり受け入れてもらえることでしょうが、それによってトクをするのは「知的労働者としての自己価値の底上げ」を達成した&その過程でワクワクするような知的興奮を味わえてものすご~く楽しい思いをした「SFプロトタイピング参加者(のエリート層)」だけ ― 彼らの属する企業体としては、特定の「エリート従業員」の「知的底力増強」のための「自己啓発セミナー」に会社のカネを出しただけ(で、その実利的見返りは「そういう現実と地続きのリニアな収穫にはあまり期待しないでください。SFプロトタイピングとはそういうものではありません」とか最初にクギ刺されちゃってる) ― という構図の上で捉えられてしまった場合の「SFプロトタイピング」は、あまりクライアント受け(=企業側の好感度)が高いものにはなりそうにない気がします・・・ましてや、その裾野を「大学一般教養レベル」にまで広げようと試みた場合には「MUST-READ sci-fi repertoire:必読SF一覧」の膨大なリストを示した途端(日本の大学生なら)逃げちゃうでしょうね(で、教場は<SFマニアの魔窟>と化し、もはや講義の体を成さなくなる、と)・・・アメリカの大学生なら(たぶん、中国の大学生も)絶対逃げない(というか、逃げた時点で単位が取れないので、たとえSFファンでなくとも真剣な態度で読みまくる)でしょうから、彼らがそのbackcasting能力を尖鋭化させることで「国家未来戦略の担い手」としてバリバリ活躍するための強力な知的武器としての「SFプロトタイピング」が(中国・米国の国力の持続的向上を支える原動力として)俄然注目されるようになる・・・そうなって初めて「SFプロトタイピング導入による未来予測能力の錬磨」が「2100年度”新”教育大綱」の中で(世界の潮流に周回遅れどころか2周・3周遅れで)謳われる、と・・・あ、いけない、「dystopia的描写はなしで」という約束でしたね・・・とにかく、SFプロトタイピングの「草の根展開=誰でも参加できる思考実験としての普及活動」のためには「esotericism:排他的空気感」の意志的排除が(MUST-read sci-fi materialsというhomeworkの排除まで含めて)必要不可欠、という「恒常的知的武装の労を厭うものではないが、その武装のための<SF読み>なんて強いられたくはないフツウの知識人」の素朴にワガママな感覚を再度強調しておくことで、この話の展開には(まだまだ続きはあり得るけれど)ここらで意志的に終止符を打っておくことにしましょう。
■第三章)想像的創造の<果実>を追い求めないのが「SFプロトタイピング」・・・なら、「投稿者の思い描いた<未来予想図>」が例年四桁単位で寄せられる「日経星新一賞」の位置付けは?■
第四回(2017年)の星新一賞に何気なく投稿して「グランプリ&賞金百万円」を頂戴してしまったその後で初めて「数ある文学賞の中での、日経星新一賞の位置付け」に興味を抱いた実に本末転倒なこの之人冗悟にとって、「星新一賞」を巡る最も根源的な疑問点は、次のようなものでした ― この「理系的発想から始まる文学賞」に寄せられた作品の数々は、いわば「そこそこ以上の空想力を自負する千人以上の投稿者が必死に思い描いた未来予想図」なわけだけど、それらの作品は「今後の企業活動のヒント」として協賛企業各社のreference(参考資料)として提供されたりするのだろうか?・・・だとしたら、「百万円単位のグランプリ賞金」なんて安いものなのかもな・・・いや、SF文学賞に寄せられる「未来予想図」の中に(たとえ数千の応募があったとて)企業活動の未来の方向性を示唆するものなんて、そうそう入っちゃいないだろうから、こういう邪推に基づく算盤勘定は(腹芸のショートショートで百万円もらっちゃった身分としても)不謹慎かな?・・・
文学賞に投稿された作品の「著作権」は投稿者にあるにしても、その作品の「閲覧権」を「賞の審査員」のみに限定せねばならないという法は(たぶん)存在しないはずなので、毎年四桁にも上る「SFプロトタイピング・マテリアル」を(企業内企画としてコンサルタントに外注する場合に比べれば)タダ同然の協賛金の供出だけで手にすることができる「猟場」として見た場合、この「日経星新一賞」は企業側にとって「かなりオイシイ文学賞」ということになる・・・のかもしれませんね・・・実際、そういう「明日の企業活動のアイディア収集の場」として投稿作品が提供されている&参照されているのか否かはわかりませんし、たとえそうした形での「協賛企業への利益供与」があったとしても、自分はそれを「投稿者に対する背信行為」だとは思いません ― 「著作権」を不当に奪取されたというのならともかく、読んでもらうために書いた作品の「閲覧権」を「賞の選考委員のみに限定」するつもりの作者なんて一人も存在しないはずなので、「読ませるつもりもなかった読者である協賛企業に自分の作品を読まれた」ことに文句付ける投稿者もいないでしょうから・・・まぁ、いずれどこかの企業が何らかの新製品を世に出した時に、「あれって、自分が<日経星新一賞>に投稿した作品中に登場したアイディアの無断盗用なんじゃないか?・・・いや、きっとそうだ、そうに違いない!」という妄想に駆られて「不当搾取に断固抗議する!」と叫んだり「アッタマきたからあの会社の事務所に灯油まいて火つけてやる!」みたいな凶行に及んだりする人物が一人もいないとは限らないので、「こんなことをしていたらそのうち灯油まいて火着けられますよ」みたいなSFプロトタイピング的未来予測を発動した上で、「投稿作品は、審査員のみが読むこととし、部外者がこれを閲覧することはありません。ただし、入選作品については一般公開されます」というような取り決めに至るのが(時世柄)妥当な推量であろう(というか、その旨を伝える文言が「募集要項」の中にあるべきであろう・・・あれ、サイト上にはそういうこと書いてあったっけか?・・・ま、いいや、自分はもう図々しく「二匹目のドジョウ」狙いに行ったりはしないんだし)といったあたりで、この”邪推”コースのレールは打ち切っておきましょう。
それよりもむしろ気になるのは、「日経星新一賞は、今後、どこへ向かうのか?」という未来予測のほうです ― 自分がグランプリを取った2017年の時点ではまだ過去3回を数えるのみだった「日経星新一賞」は、この之人冗悟の個人的感覚では「ショートショートの殿堂」といった感じでした。自分の書いた『OV元年』なんて「星新一っぽいショートショート」の最たるものだし、前年2016年グランプリを取った佐藤実さんの『Launch free:ローンチ・フリー』もやはり「テクノロジーの進歩の波に押し流されて時代遅れになってしまったかつての最先端エリートの、個人的情念の物語」という形での「星新一作品『空への門』へのオマージュ」でした。初年度と二回目のグランプリ作品に関しては「理系的であることを生真面目に主張する作品」だったのに対し、三回目・四回目が「理系の天ぷら粉に身を包んだ文系寄り作品」だっただけに、「今後の星新一賞は<理系っぽさ>よりも<ショートショートとしてのおもしろさ>を求められる流れになるのかな?」と思っていたら、翌第五回(2018年)以降のグランプリ作品には「プロのSF作家を目指して文章鍛錬を積んだ投稿者たちの<理系フィクション>の優秀作」が居並ぶ流れが連綿と続いて今に至る・・・となれば、今の星新一賞は「理系プロ作家への登竜門」ということになりそうですが、果たしてこれは「星新一賞が目指す方向性」と合致しているのかどうか、という疑問は残ります ― 「プロのSF作家への登竜門」という位置付けの文学賞としては、『ハヤカワSFコンテスト』や『創元SF短編賞』があるわけで、後発文学賞である『日経星新一賞』が「単なるプロSF作家への登竜門」を目指す理由は見えてこない ― 『小松左京賞』と『日本SF新人賞』が相次いで2009年に廃止されたことへの危機感から創設されたという成立背景はあるにせよ、「日本のSF文学の未来を担う新人作家の発掘現場」としての役割を「星新一賞」(2014年~現在)が担うものという図式には全くピンとこない・・・ともなれば、これは「協賛企業の新製品作りのアイディア発掘現場」としての役割を期待されている賞なのか? ― 今回『SFプロトタイピング』の本を読んだところ、この目新しい思考実験の方法論が唱えられ始めた時期(2012年前後)と日経星新一賞の創設時期(第一回作品募集の開始は2013年)がほぼ重なるようなので、「星新一賞は<SFプロトタイピング>の壮大な実験場である」という言い方が、もしかしたら成り立つのかもしれません・・・だとすれば、「星新一賞で入選したい」という野心を抱いた投稿者は「SFプロトタイピングの良質なマテリアル」を書いて送れば入選確率が高まるか、といえばそんなことはないでしょう ― 仮に「協賛企業によるSFプロトタイピングのマテリアル入手先」として星新一賞を捉えた場合、入選作だろうが落選作だろうが、それを参照する協賛企業にとっては同じこと ― 投稿者が目指すべきは「面白い作品を書いて選考委員の目にとまること」であって「実現可能性の高い<近未来ガジェット>の青写真を送って協賛企業を喜ばせること」ではないのだから。
結局、「星新一賞がこの先どこへ向かうのか」は「どんな作品がグランプリを取るか(=どんな作品を選考委員が面白いと感じるか)」によって決まるわけですが、この賞もすでに13回を数え、過去のグランプリ受賞作品11編を集めたアンソロジー『星に届ける物語』(新潮社)も刊行されているからには、入選(できれば、グランプリ獲得)を目指す「真剣な投稿者」の多くはこれら過去の受賞作品を参照しての「傾向と対策」を練った上で自分が書くべき作品の方向性を決めるでしょうから、投稿作品の全般的傾向は「過去のグランプリ受賞作品」と同一の方向へと自然と流れることになるでしょう・・・入選作を選ぶ立場の選考委員たちもやはり「過去のグランプリ&入選作」を一通り読んだ上で選考作業に入るはずなので、その「選考基準」も自ずと「過去のグランプリ作品の傾向」へと歩み寄ることになるでしょう・・・そうなると「プロSF作家の創作上の方法論」に従って書かれた「プロっぽい洗練された作品」が入選する流れが定着することになり、かつての『ローンチ・フリー』(2016年)や『OV元年』(2017年)のような「素人が情念や勢いで書いた作品」の入選作は減るでしょう・・・そもそも「プロのSF作家を目指して<書き方講座>を受講した人たち」ばかりがズラリと並ぶ「筆者略歴」を目にした時、「じゃぁ、自分もその<書き方講座>を受講してみよう」と考える生真面目な投稿者が爆増する一方で、「じゃぁ、素人の自分が書いた面白い作品で、<プロ志望投稿者の牙城>に一石を投じてみよう」と考えるようなアマノジャクで威勢のいい素人投稿者は激減するでしょう・・・そうなると、「(プロの水準には満たないけれど)プロ作家を目指す投稿者の書いた<いかにもSFっぽいマジメな力作>だらけ」になった星新一賞には、「SFプロトタイピングの良質なマテリアルの入手先」としての「協賛企業にとっての魅力」が薄れることになるのではないか ― 「意外性のある未来予想図」は「プロSF作家の作品創作上の方法論」から「リニアに創出」され得るものではないのだから・・・そうなってしまった場合の星新一賞が、果たして「協賛企業」や「熱心なSF読みではない一般読者」にとって魅力的な存在たり得るかどうか、「プロ志望ではない一般投稿者」にとって近寄り難い排他的威圧感を漂わせる場になってしまわないかどうか ― この懸念は、ここまでに述べてきた「SF大会は、古参の参加者にとって居心地の良い場所となるのと引き替えに、一般大衆はおろか、若いSF読者にとってさえ、寄り付き難い存在となってしまっていないか?」・「SFプロトタイピングは、<SF知識の宿題>を参加者に強いることによって、万人にとって有益な思考実験ツールとしての潜在可能性に自らフタをする自閉構造に陥ってしまったりしないか?」という問題と、同一地平線上で連なるリニアな心配事と言えるでしょう。
もちろん、この之人冗悟は「SFファンダムが持つ<自己のSF知識>の披露・交換・観測気球打ち上げの場としての、独特な雰囲気」を否定するものではありませんし、「プロSF作家を目指す投稿者の技倆確認・自己存在アピールの場としての、日経星新一賞」という構図を否定するものでもありませんから、「同じ人物、それも明らかにプロ志向投稿者が、何回も入選したりグランプリ取ったりすると、一般投稿者にとっての敷居が高くなる」という事実は事実として指摘しつつも「だから、一度グランプリを取った者は、星新一賞の今後の発展のために、以後は投稿を自粛すべきである」などと言うつもりはありません・・・が、「<作品>の選考は<作者名>を伏せた状態で<誰が書いたか>ではなく<どれぐらい面白いか>のみを基準に行なわれる」という星新一賞の「覆面選考」の公明性については、もっとハッキリ大声で(ベテラン投稿者向けのみならず)世間全般に向けて明示的にアピールすべきだ(でないと、「特定のスター候補を売り出すための口実でしかない<出来レースとしての芸能界公開オーディション>」と同じような白い目で「日本のSF界の明日を担うスター候補を売り出すための<出来レースとしての星新一賞>」という事実無根の中傷フィクションをデッチ上げてネット上にバラまく不届き者の出現を防ぎきれないだろう)という点についてだけは、声高に叫んでおきたいと思います・・・ので、大澤さんから日経星新一賞サイドへ伝えていただければ幸いです。
■第四章)to re-name but a few:呼び方を変えたほうが良さそうな語を、ふたつみっつほど■
「SFプロトタイピング」という呼び名は(今回この本を読ませてもらった限りでは)どうやら日本限定のものらしいと思われますから、これを敢えて「世界標準」を意識して「sci-fi prototyping」にすべきだとは考えません(・・・諸外国の人々相手に英語で言及する場合だけ「エスエフ・プロトタイピング」ではなく「サイファイ・プロトタイピング」と反射的に読み替えれば済む話です)・・・が、書籍中で何度も出て来た「SFプロトタイパー」という呼び名だけはさすがに違和感があります ― 英語世界では「typeする人」は「(×)typer:タイパー」ではなく「(○)typist:タイピスト」ですから・・・おそらくは「youtubeへの投稿で広告収入を稼ぐ人」を表わす「youtuber:ユーチューバー」からの無意識の横滑りから生じた「SFプロトタイパー」だと思いますが、この呼び方は「SFプロトタイピング」という方法論の知名度・普及度が上がる前に「SFプロトタイピスト」へと改めておくことを強く推奨します・・・で、「SFプロトタイピング」の名前(方法論ではない)を遅ればせながら知った一般人が、知ったかぶりして「”自称”SFプロトタイパー」とか名乗った時点で「あはは、わかってないなぁ ― ホンモノのプロは<プロトタイパー>なんて<ユーチューバー>めいた横文字は使わずに<プロトタイピスト>と言うんだよ」という形のリトマス試験紙として作用する土台を作っておく、と・・・まぁ、これはあくまで「語学屋の之人冗悟なら、そっちの方がいい(というか、面白い)と考える」というだけの提言であって、「英語として間違っているから、修正を求める」というような話ではありませんので、「べつに<プロトタイパー>でいいじゃん」と思われたならそのまま流してしまって構いませんが。
書籍の中では、「SFプロトタイピング」の利点として「既存の枠組みと地続きでない空想的非連続性がもたらす発想の自由度」が幾度となく力説されていましたが、その自由な発想から生まれる未来予測の到達点としては必ずしも「明るい将来展望」のみならず「暗い結末」に至ることもあって、そうした「実現してほしくない暗黒の未来」を予想することでその可能性実現の芽を未然に摘み取る「転ばぬ先の杖(あるいは、炭鉱のカナリア)」としての役割をもまた積極的に認めるべきだという主張のほうは(幾度か触れられてはいましたが)もう少し力点を置いたほうがいいと思いました ― なにせ日本人(特に、集団化した日本人)というものは「自分(たち)にとって不都合な何か」に対しては反射的に目を閉じてしまう「穢れ忌避体質」を(上代このかたず~っと)引きずっている極めて特異な「精神的潔癖症人種」であって、「SF的思考法による未来予測」という触れ込みで「SFプロトタイピング」なる新たな思考実験法を売り込む際にも、「この不確実性の時代に<未来を見通す>ための強力な知的ツール」という「勝ち組に回るための武器」としての側面ばかりが世間に流布することになってしまうので(しかも実際のSFプロトタイピングの成果としてそうそう都合良く<勝ち組ウェポン>が手に入る展開などあり得ないので)、ここはむしろ意識的に「負け組に回らぬための将来のリスク回避手段」としての側面をこそ力説しておくのが「日本人を相手にする場合の正しい振る舞い」だと思います・・・ということになると、「SFプロトタイピスト」の中にも「明るい未来図を描く(傾向の強い)者」と「暗い未来図を描く(傾向の強い)者」という二元論的切り分け方をするのが世間というものですが、その際の両者の呼び名として日本人がすぐさま口にするであろう横文字は「ホワイト・プロトタイパー(=顧客が喜ぶ<明るい未来図>を出してくる者)」と「ブラック・プロトタイパー(=顧客が渋い顔をするのを承知で<炭鉱のカナリア>として苦しげな声を上げる者)」ということになるでしょう・・・が、これらの安直極まる呼び名が「SFプロトタイピングの本質も知らずにただ何となく<明るいほう>/<暗いほう>の二元論で物事を片付けたがる<浅い>人達」を見分けるリトマス試験紙として使われる一方で、「プロのSFプロトタイピスト」の世界での呼称は「dystopian:暗黒世界構築型」と「euphorian:多幸感演出型」という風に分けておくべきかと思います・・・後者を「utopian:理想郷描写型」と呼ぶのはいかにも幼稚なので、そういう呼び方をする人々をもまた「わかってない連中」として切り分ける便利なレッテル・ツールとして活用させてもらうのが好適だろう、と(『OV元年』とか書いちゃう典型的dystopianのシニカルな語学屋の)之人冗悟としては考えるわけです。
上の2つに関しては「語学屋の戯れ言」の域を出ませんが、最後の1つはかなり「言語学的に真剣な疑問点」 ― 書籍中では「スペキュラティブ」と表記されていた「speculative」という英単語の読み方についてです。末尾が「-tive」で終わる英語の形容詞の中には「-ェイティブ(例:creative:クリェイティブ)」か「-ァティブ(例:initiative:イニシャティブ)」かのいずれか一方の発音しか許容されないものも多いのですが、懸案の「speculative」に関しては「スペキュレィテイブ/スペキュラティブ」双方の読み方があり得るようです・・・が、この語の動詞形は「speculate:スペキュレィト」であり名詞形は「speculation:スペキュレィション」であるだけに、その形容詞形の発音もまた「speculative:スペキュレィティブ」へと流れるのが自然に思われます・・・が、ここにまたもう一つ考慮すべき事情が絡んできます ― 「投機的な(=これは儲かる、と踏んだ投資対象へとお金をぶっ込む形の)」という経済学的に重要な「speculative」という形容詞が存在し、そちらの発音は(たぶん)「スペキュレィテイブ」なのです・・・となると、この「金儲けのために頭を働かせる」という生臭い語義は「スペキュレィテイブ」と読み、「現実ではない想念上の」という理知的な語義のほうには「スペキュラティブ」という別発音を宛がって、性格がかなり異なる2つの語義に音感的次元での差別化を施す、という作法が行なわれていたとしても不思議はないように思われます ― 日本語の世界でも、「iron」という英単語に関して「衣類乾燥装置としての<アイロン>」という先発語義に対し「ゴルフ用具としての<アイアン>」という後発語義を別発音で区別していますし、「icon」の読み方も「キリスト教的偶像」の意味では「イコン」と読み、「コンピュータ画面上の絵柄」の意味では「アイコン」と呼び分けていますからね ― そういうわけで「speculative」の発音が「金儲けの文脈では<スペキュレイティブ>/理知的推論の文脈では<スペキュラティブ>」という意図的読み分けの対象となっているのかどうか、「SFプロトタイピング方面の専門家であるEnglish speaker:英語話者」との接触機会が多いであろう大澤さんには「実際の発音を通しての答え合わせ」が可能だろうと思いますが、残念ながらそういう機縁がない(人と会うこと自体、数年に一度しかない仙人みたいな)語学屋之人冗悟としては、いささかモヤモヤとした謎が残るところ・・・まぁ、べつに「気にしだすと夜も寝られない」みたいな話じゃぁないんで、「大澤さん、是非正解を教えてください!」みたいな悲鳴を上げるつもりはありませんが、教えていただければかなり嬉しいです。
■第五(最終)章)SFプロトタイピストに求められる5つの<mo->■
部下の結婚式でスピーチする羽目になった上司ふうにまとめると、「SFプロトタイピング」を展開する側(参加する側ではない)に求められる専門技能には、次の5つの<mo->があるようです:
<mo-1>motivator:ディスカッション参加機運醸成係
・・・これは個別的な「SFプロトタイピングセッション」を成立させるためというよりは、「SFプロトタイピングというツールを使って未来予測を立ててみよう」という気分へと「参加(希望)者たち」を駆り立てる「誰か(というよりはむしろ、何か)」です。「A社やB社ではSFプロトタイピング技能に優れた人材が新製品開発でめざましい成果を上げているらしい」という情報を耳にしたC社のエラい人が「ここはひとつ、我が社でもそのSFプロトタイピングとやらを用いての新製品開発を行なってみよう」という気分になったり、同じ情報を耳にした「A社・B社への入社を希望する大学生」が「SFプロトタイピング講座に通って、就職面接の際の自己アピールポイントにしよう」という行動を起こしたりする場合の、「A社・B社はSFプロトタイピングでかなりイイ感じになってるらしい」という情報がそれにあたります。
・・・『SFプロトタイピング』の本の帯にあるハヤカワさんの売り文句「マイクロソフト、日産、清水建設ほかで続々採用の画期的手法!」もその系統だけど、ちょい弱すぎるかも・・・特に「追浜工場おっぱらっちゃったばかりのニッサン」とか入ってるあたりが・・・あ、いかん、またdystopianの地金が出た・・・
<mo-2>mobilizer:ディスカッション参加者動員係
・・・これもやはり「SFプロトタイピングセッション」の成立以前に発揮される技能ですが、実際問題としてはSFプロトタイピングを成功させる上で最も重要なキーになるものと思われます ― ディスカッション参加者として最適な人材の「人選力」、というよりそれ以前にまずそうした人材のselection(選別)を行なうためのdatabase(データベース・・・この場合、単なる<能力評価表>を越えた<人脈力>)がどれほど充実しているかが問われることになります・・・SFプロトタイピングを外注するクライアント(企業、学校等)からの「参加者の人選」は当該クライアント側で行なわれるでしょうからSFプロトタイピスト側の関与の余地はありませんが、セッションを進める過程で必要になる「物語作成人員(=modeler)」としてどの程度有能な「SF作家」を調達できるか ― これはそのSFプロトタイピストの「人脈力」というか「人間的魅力による人材吸引力」によって決まるので、最もリアルで最もシビアな「プロとしての試金石」と言えるでしょう・・・「SF(ふう)物語をまとめるのが上手」なだけの「writer:書き手」では、「SFプロトタイピスト」にはなれず、「SFプロトタイピストが取ってきた外注案件の下請け人材」止まり、というのが(「SFプロトタイピング」の黎明期はともかく、普及して以降の)現実的構図になるものと思われます。
・・・ここから先は「SFプロトタイピングセッション」が実際に動き出してからの役割分担・・・
<mo-3>moderator:ディスカッション進行係
・・・この技能もまた「SF(ふう)物語をまとめるのが上手」であれば務まるというものではなく、当該セッションで求められる「(未来図構築に必要な)技術的情報」に精通しつつ、「SFプロトタイピング」というプロセスの全体像を俯瞰的に把握した上で、現在進行中のセッションパートがセッション全体の中で意味をなす不可欠なピースとしてしっかりハマるよう(ダラダラだれてしまったり脈絡無視の暴走的展開で脱線したり虫眼鏡で太陽光を一点集中して火事起こしちゃうような粘着質的滞留で二進も三進も行かなくなったりしないよう)きちんと目配りして流れを滞らせない「交差点のおまわりさん」の役回り。
・・・「セッション進行の円滑な調整役」という技術的役回りに加えて、セッション参加者の誰かの出してきた話にケチつけてヘコませる「molester:イジメっ子」だの、自分自身の知識や卓見を振りかざすことで他の参加者を萎縮させる「mortifier:サゲサゲ屋」だのが出現した場合(出現しないようにする、という芸当は不可能なので)、他の参加者の萎えそうな気分を支えてあげる「mollifier:なだめ役」も演じなければならないわけですから、「知恵者」であると同時に「人格者」でないと務まらない、かなりハードルが高い役回りと言えるでしょう(・・・之人冗悟にはたぶんムリ)
<mo-4>modifier(or modulator):ディスカッション内容微調整係
・・・「SFプロトタイピング」で思い描かれた「物語内現実」を「絵空事」で終わらせないためには、「今はあくまで架空の存在ではあるが、この種の条件を満たせば現実のものとなり得る」という形で「仮想的存在に科学的実在性を持たせる検証作業」が必要不可欠 ― 誰かが描いた「ブッ飛んだ空想世界」に対し、「それのこの部分には科学的整合性がない・・・ので、このように変えたほうがいい」といった形で修正意見を添えてくれる(地味だけど)大事なバランス役で、「SF作家」よりは「科学畑の専門家」のほうが(たぶん)適任。
<mo-5>modeler:仮想的現実モデル作成係
・・・「物語世界の中で仮想的に未来の世界を思い描く」のが「SFプロトタイピング」の一特性である以上、その「物語作者」としての役回りは参加者全員が受け持つことになる・・・とはいえ、セッション開始時にこの先のディスカッションで志向すべき未来図の「ラフスケッチ」を描き、セッション完結時には参加者全員の想像的創造の産物として生まれた未来世界に「フィニッシングタッチ」を加えて「参加者以外の読者の前に差し出してもきちんと読んでもらえる物語」として完成させる役割は、やはり「架空世界を現実として描く文章のプロ」たる「SF作家」ということになるでしょう・・・べつにそれは「SF作品として面白い物語」である必要はないし、それを完成させたSF作家が「自分の書いた新作」としてそれを世に出すことができるわけでも(たぶん)ないので、「自己表現の手段として、自らの脳内世界を<SFワールド>として文章化して本にして出す」というSF作家本来の「創造主としての欲求」を満たす仕事ではない(でしょう)けれども、大方は「SF書いてるだけじゃメシ食えな~い」という社会経済的状況に身を置いている(であろう)SF作家にとっては、この「他の人たちがワイワイがやがや言ってるうちに何となく出来上がった<あり得る未来>or<あってほしくはない未来>の姿を(半ば代筆者として)文章化する仕事」は、「食い扶持」としても「お金持ってるクライアント(企業、あわよくば、出版社)との人脈作り」という観点からも、「自分の脳内世界をSF文学として結実させる仕事」では(残念ながら)得られない実利的効用を持つものとなる(でしょう・・・之人冗悟はあんまりやる気ないけど)
・・・この他、「SFプロトタイピング」を「SFプロトタイピスト」に対して「発注」してきたクライアント(主に、企業・学校)の側としては、さらに次の2つの<mo->を付け加えたいと望むかもしれません・・・が、ハッキリ言ってこれは「お邪魔ムシ」ですね(・・・邪魔だからと言って無視するわけにもいかんだろうけど・・・):
<monitor:監視役>
・・・得体の知れぬ空想ゴッコにうつつを抜かすばかりで「会社のカネ」や「授業時間」をムダに空費するばかりの展開になっていないかどうかをチェックする御目付役。
<monetizer:利益化役>
・・・「SFプロトタイピング」を単なる「架空現実空想ゴッコ」に終わらせたのではカネを出したクライアント(企業・学校)としては持ち出し一方で何の旨味もないので、セッション完了時に生み出されている(はずの)「自由な発想で思い描いた未来の世界」から(企業イメージ向上なり何なりの形でこれを売り出すとか、「日経星新一賞ジュニア部門」に投稿させてあわよくば入選してもらって学校の名を高めるみたいな形で)「実利的見返り」を得る道を模索する役。
。
。
。
。。。以上の箇条書き的記述は、『SFプロトタイピング』(早川書房)の内容を整理したものではなく、同書を読んだだけで実際の「SFプロトタイピング」に参加した経験はゼロの之人冗悟の想像の産物 ― 至らぬ点があれば、「勢いだけで『OV元年』とか書いて間違って日経星新一賞グランプリ取っちゃっただけのトウシロウの想像的構想力なんて、所詮こんなもの」と笑い飛ばしてください(笑笑)・・・もし上記の「<5つのmo->に寄せて」のテーマで書いたまとめ記事がそれなりに正鵠を射たものになっていたならば、『SFプロトタイピング』の本の中身がそれだけ濃密だったということで、誇りに思ってください(真顔)・・・
・・・いずれにせよ、久々の良書との巡り会いに、改めて感謝します。
・・・今回の「かまこん」では、編著者の御三方のうち、難波さんとはお目に掛かれませんでしたが、宮本さんには『環境問題や生命科学をSF的思考で考える』(8/30)のビデオ経由のリモート参加の形で発言を聞く機会があり、大澤さんとは同講座でお話を聞かせてもらったのに加えて『日経「星新一賞」について語ろう』(8/31)の部屋では少しだけ対話させていただく機会もありました・・たったそれだけの接近遭遇からの印象だけで語らせてもらえば、大澤さん・宮本さん御二方の「<mo-4>modifier(or modulator):ディスカッション内容微調整係」としての技能には信頼が置ける感じでした ― やはりこの面では「SF作家」よりも「理系研究者」の方が優れている(参加者に与える印象面だけからでも、そういうことになる)と思います ― 誰かの空想の暴走・妄想を程良い所まで膨らませつつ、頃合いを見て合理的収束を図る役回りは、研究者にしか務まりません(・・・SF作家やSFファンは、その暴走ぶりの自慢合戦に知らず知らずのうちに走る悪癖からなかなか自力では抜け出せませんので・・・)。
・・・「<mo-3>moderator:ディスカッション進行係」としての役どころに関しては、「参加者全員への目配り」という点では大澤さんに、「積極的発言による議論の活性化と方向付け」に関しては宮本さんに、それぞれ軍配を上げたい感じです・・・これは「SFプロトタイピング」に限ったことではありませんが、とかく日本人集団の「ディスカッション」は「誰か一人の独演会」に終わりがちなだけに、「発言したがらない参加者」の口を開かせる「誘導役」と、「発言しすぎる参加者」のムダ口を(より高度で意味のある発言を通して)閉じさせる「引導渡し役」の役割が重要になってきますが、前者を大澤さん、後者を宮本さんが務めたなら、「空砲飛び交うSFファン4名によるSFプロトタイピング」というdystopian discussion(できれば避けたいグジャグジャ討論会)でさえもそれなりに乗り切れてしまうのではないか、という気がします・・・が、まぁそういう人選だけは避けるような「<mo-2>mobilizer:ディスカッション参加者動員(&選別)係」としての役回りの方が大事ですね ― この点に関しては「人的交流のネットワークの広さ」がモノを言うはずであり、御二方ともその拡張を合目的的に推進している「ただ好きなこと研究してるだけじゃなく、好きな研究をするために必要な条件を整えるための活動も怠らない、ちゃんとわかってる研究者」であることが明瞭に見える活動を行なっているのですから、自ずと「SFプロトタイピング」の「<mo-1>motivator:ディスカッション参加機運醸成係」の役回りとしても適任、ということになるでしょう ― 同名の本を書いているから言うわけじゃありません: 生身の発言・行動様態の一端に接しただけでもう「口先ばかりの宣伝屋とは違う、本筋のevangelistsたり得る人々」であると確信させてくれたからこそ言っているのです。
・・・これは「絵空事を現実めかして書く<職業的ウソつき>の(プロじゃないけど)小説家としての勘」で言うのですが、実際の「SFプロトタイピングセッション」に於いては、「<mo-5>modeler:仮想的現実モデル作成係」の役割の重要性はさほど高くないように思います ― みんなしてワイワイがやがやまとめた「漠たる空想の未来」の姿を、「プロのSF作家」が「読者をグイグイ引っ張る一級品の短編小説」にまとめ上げた場合、「おぉ~!さすがはプロ、あれだけモヤモヤしたものを、これほどワクワクする話にまとめ上げてしまうとは!」とか感心はされるかもしれませんが、べつにその作品を「日経星新一賞に投稿」するわけでもない以上、問題になるのはやはり「物語の<読み物>としての質」ではなく「まとめ上げた物語世界の<論理整合性>」だと思います ― 「筋は通らぬけど面白い近未来SF」ではダメで、「面白くはないけど筋は通ってる未来の世界の話」が出来上がらないことには意味がないわけですから、「modelerよりもmodifier/modulatorが大事」ということになるはずです ― この点だけは、「modelerとして参加してもらうSF作家」にも参加者全員にも、しっかり認識してもらう必要があるでしょうね・・・でも、プライドの高いSF作家相手にはなかなか納得してもらうのが難しいかもしれません ― 「読み物として優れていなくてもいい物語を書け、というのなら、わかったよ、思いっきり手を抜いてヘボいやつ書いちゃうから、いいんだよね、それで!?」とかヘソ曲げられちゃったりして・・・そうなるとやはり「SFプロトタイピング」を成立させる最重要要素は「<mo-3>moderator:ディスカッション進行係」としての能力(特に「mollifier:なだめ役」としてのそれ)だったりするのかもしれませんね。
・・・あれこれ考え合わせると、良質なSFプロトタイピングセッションを成立させるのは「日経星新一賞」に入選するよりも難しいような気がしてきました・・・でも、うまくハマった時の知的興奮や達成感は、グランプリ(間違って)取っちゃった時よりも大きそう・・・だけど、SFプロトタイピングを実現するには、ずいぶんと「人・カネ・時間」がかかるようですからねぇ・・・星新一賞への投稿なら想像力一つでできちゃうけど、SFプロトタイピングセッションを開くとなると「グランプリ賞金2~3回ぶん」ぐらい投じないとダメそうだし・・・そんなわけで、「自分には手の届かぬ空の彼方で輝く星々の知的きらめき」の一端なりとも感じ取らせてくれた『SFプロトタイピング ― SFからイノベーションを生み出す新戦略』の本には、まぶしい讃辞を惜しまぬ之人冗悟なのでした。
2025年9月3日(水)
之人冗悟(Jaugo Noto)
語学屋...のほうも一段落付いたので、ここから先の肩書きは「妄想屋」になるかも...
admin@notojaugo.comまで
***「ワタシはスパムではありません」の身元証明として、
re:『SFプロトタイピング』・『日本SF大会』・『日経「星新一賞」』について
のタイトルを必ず付けてお寄せください。
