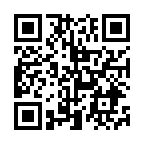
ここ数年(いやもうここ十数年来か)、日本人はみなこぞってヘンな日本語を口にするようになった ― 曰く、「ここ最近」・・・古来(=1950年の設立以来)「日本語の番人」たることを自負していたはずのNHKアナウンサーまでもが「ここ最近、天候不順が続いています」みたいなおかしな事を平然と言っている。何がおかしいのかわからぬ日本人は、次の英訳を見てそのヘンテコぶりを確認してほしい(・・・ぁはは、無理言ってやがらぁ、この英語屋は・・・) ― 曰く、「The weather has been rather wild for these recently.」 ― 「ここ(for these)」という<(前置詞+)形容詞>で語り始めるなら直後には「数日(few days)」・「数週間(several weeks)」・「二~三十年(couple of decades)」といった<名詞(複数形)>が続かねばならぬのに、後に続くのが<副詞>の「recently(最近)」というのでは、これはもう「言語学的裏切り行為」というものである。
言葉に疎い一般日本人ならいざ知らず、よりによってNHKのアナウンサーや番組までもが「ここ最近(正しくは<最近>)」だの「古来より(正しくは<古来>もしくは<古(いにしへ)より>・・・<(以)来>は英語の<since ~:~より>なのだから、<古来:since olden times>の後に更にまた<より>を付けるのは<since since olden times:昔日よりより>と言ってるのと同じtautology:類語反復)」といった「ヘンテコ和語」で言語学的裏切りを平然と演じ続けている令和の世の日本語の惨状には、「語学屋」としてまったく耐え難いものがある。
「ここ最近」なんて言わずに「ここのところ」か「最近は」と言えばいいのに・・・「古来より」なんて言わずに「古来」・「昔から」と言えばいいのに・・・なんでそう言わないのか、答えは2つ ― 「<古来より>って言い方、<ここ最近>よく聞くから」という「neologism:新語(偏愛)体質」と、「みんなそう言ってるから」という「conformity:右顧左眄(うこさべん=右へならえ)体質」とが、日本人の言語学的(のみに留まらぬ全般的)体質だからである ― 「関係」で済ますべきところを「関係性」と反射的に口走ってしまう「ここ最近」の日本人の笑っちゃうような言語習慣もまた、この列に連なる(無数の)右顧左眄新語傾倒事例の一つである。
「よくよく考えてみればヘンな事」であっても、「周りがみんなそうしてる」なら、深く考えもせずに自分もそれに靡(なび)くのが当たり前 ― 特にそれが「ここ最近」の事ともなれば「周りに負けじ」と自分もそうするのが当たり前 ― むしろ「みんなが歩んでるヘンテコな道」から自分一人だけ「逸(そ)れる」ほうがよっぽど「ヘン!」であり「おくれてる~!」ということになる ― それが圧倒的多数の日本人の体質であることは、ここで敢えて指摘するまでもあるまいし、指摘されないとそれが判らぬような人間観察力の鈍い人では「ショートショート(に限らぬ文学)の傑作」なんて書けないことも、言うまでもないだろう・・・が、どうも、そのあたりがよく判ってないんじゃないかと思われる状況が、「ショートショートの殿堂」(だったはずの)『日経「星新一賞」』に関しても(ここ6~7年来)見られるので、以下、敢えてそれを指摘しておこうと思う・・・「たった一度まぐれでグランプリ取っちゃっただけの語学屋ふぜいが、何をエラそうな事言ってやがる!」と思うのが「フツウの日本人」の感覚だろうが、よくよく考えてみてほしい ― 『日経「星新一賞」グランプリ』は、「フツウの日本人」や「フツウの文学」や「フツウの発想」で手が届く代物ではない(はずであろう?) ― グランプリ獲得を目指すなら、「フツウ」の道から逸れること ― 『OV元年』みたいなヘンテコ作品であっさりグランプリ取っちゃった「変わり者」だからこそ、堂々とそういう「フツウじゃない事」を言えるわけである。
この第四回グランプリ作者の「もう自分は<ホシ賞>には投稿しないので、野次馬ファンの立場で、言いたいこと&望むこと、はばかることなくズケズケ言っちゃうよ」というスタンスで放つ以下の提言を受けて、何を思うか、どう活かすか、それはアナタが「どういう人間か」次第 ― 「フツウの日本人」なんて最初から対象外の話なので、「ホシ賞でグランプリ取るようなフツウじゃない作品を書きたい人」だけ、読んでください(・・・あ、あと「ホシ賞の選考委員」に指名されちゃった因果な人々にも、読んでもらえたらいいかもしれない・・・)
『日経「星新一賞」』を特徴付けるものとしては、「理系的発想から始まる文学賞」というフレーズと「人工知能(AI)創作物も可」という募集条件の二つがその最たるものだろう。
「<理系的発想から始まる>とはどういうことか?」に関しては、『日経「星新一賞」』の公式WEBサイトに次のような「創作ヒント」が掲げられている:
<ステップ2>50 年後や100 年後など、未来を想像してください。その研究や技術は、どのように進歩しているでしょうか。こちらは、不老不死が可能になった、自我を持つロボットが発明された、分子レベルであらゆるものが複製できる技術が確立されたなど、できるだけ具体的に想像するようにしてください。
<ステップ3>その未来の世界では、どんな物語が生まれるでしょうか。たとえば、恋愛はどのように変わるか、家族のあり方はどうなるのか、といったパーソナルな変化を描くのもありです。逆に、社会のあり方の変化や、法律がどのように変わるのかなど、マクロな視点で描くのもありです。それから、それを発明した人はどんな行動をとるのか、というアプローチもあるでしょう。もちろん、これだけではありません。想像力を働かせて、自由に書いてみましょう。
・・・念のため書き添えておくが、この「創作ヒント」の下には次の文言が続いている:
・・・ということであるが、日本人というのは(間違いなく)世界一クソマジメな人種であり、(よほどの「外れ者」でない限り)右顧左眄(うこさべん=右みて左みて、自分もそれに合わせる)が第二の本能と化すような生き方を(幼児期から社会人引退まで)ずっと強いられ続けて生きているような人々なので、上掲の<ステップ 1⇒2⇒3>を踏み外すような作品を書いてホシ賞に投稿してくる人(=之人冗悟みたいな外れ者)は、極めて少ないだろう ― 即ち、「自分が研究している分野やもの、本や雑誌やウェブサイトを見て興味をいだいた理系の研究や技術」を創作の<出発点>とする投稿者がほとんどであって、それ以外の<出発点>を持つ作品は「フツウじゃない」ことになる・・・ということは、アナタがもし星新一賞でグランプリを狙うなら、「フツウじゃない作品」を書いて送るほうが、いいんじゃありませんか?
筆者は過去のホシ賞入選作の全てに目を通しているわけではないが、第一回~十一回までのグランプリ受賞作に対象を絞って言えば、「理系的な<出発点>」から書き始められた物語が居並ぶ作品群の中で、「<道具立て>こそ理系的だが作品の精髄(soul)は文系的」と形容できる作品は三作しかない ― 自作の第四回(2017年)グランプリ作品『OV元年』と、前年度第三回(2016年)の佐藤実氏の『ローンチ・フリー』、そして第八回(2021年)の村上岳氏による『繭子』である ― これら三作以外のグランプリ受賞作はどれもみな「生真面目に理系的」というか「いかにもSF的」なのである・・・上に挙げた三作に関してさえ(『OV元年』以外の二つは)「バリバリ理系的」と見る人が多いかもしれない・・・そういうグランプリ作品がズラリと並んでいる以上、(例年四桁にも上る)応募作品のほとんど全てがそうした「理系SF」を目指して書かれている、と考えるのが(クソマジメで右顧左眄的な日本人が投稿者の大多数を占める以上)妥当な見立てとなるだろう・・・そういう作品が悪いとかつまらないとか言っているわけではない ― 「理系的発想から始まり、理系的記述に終始して、SF的に終わる」といった作品群の中にあって、そういう群れから外れた「black sheep:黒羊」が三頭もグランプリを取っていた、という事実に(もしアナタがホシ賞でグランプリ目指すなら)注目すべきなのではないか、と言っているのである。
・・・以下、当該作品を未だ読んでいない人へのネタバレにならぬ範囲で、これら三作の「黒い羊たち」を評してみよう:
●佐藤実氏の『第三回グランプリ)ローンチ・フリー』は、「科学技術の急速な進歩のせいで時代遅れになってしまった<ちょっと前まで時代の最先端を走っていたテクノエリート>の情念から生まれた冒険物語」である。作者の佐藤実氏は実際<宇宙エレベーター>という「近未来のSF的テクノロジー」の研究をしているらしく、作中ではその技術的細目が(全体字数の約半分を用いて)語られてはいるが、『Launch Free』は決して<宇宙エレベーター>が主役の物語ではない ― 作中世界では<宇宙エレベーター>は既にもう”枯れた”技術であり、物語の舞台となる<宇宙エレベーター>は「廃棄処分のガラクタ」扱いであって、そこを舞台に自らの情念の物語を展開する「時代遅れのテクノエリート」と”時代に取り残されたものどうし”という形でのmetaphor(メタファー:隠喩)を成している点も(「文学的」にみて)秀逸である ― 自分が選考委員だとしたら、一読しただけで「絶対これがグランプリ!」と確信しちゃうような傑作であるが、作者の佐藤実氏の談によればこれは「星新一の『空への門』の主人公のその後の人生が気になって気になって仕方がなかったから生まれた作品」であるとの由 ― その創作動機の背後にあるものは「宇宙エレベーターに関する専門的知識」という「理系的発想」よりむしろ、「作者自身の長年の心のつかえ」なのである・・・この点で、あの作品は「主人公/作者双方にとっての<情念>の物語」なわけであり、その「非理系的なsoul(魂)」が読む者の心に共鳴することであの作品を傑作たらしめているのである。
●村上岳氏の『第八回グランプリ)繭子』は、「量子力学に於ける<観察(者)問題>」についての「理系的解説」が(これまた全体字数の大半を費やして)展開されるものの、作品のキモはそこにはない・・・あまり詳しく踏み込むと未読の人達の興趣を削いでしまうので、可能な限りボカした寸評を加えるならば、「<人と人との関係>という人類最大の難題について、<数理モデル>で割り切ろう、という思春期特有の(or未成熟科学に特有の)単純化の試みをあれこれ繰り返した末に、ある少女が辿り着いた<人間的(≒非科学的)解(・・・正解か否かは不明ながら、理系的アプローチ以外の新たな可能性を示唆する、一つの萌芽)>」の物語である『繭子』に於いては、「量子力学の観察(者)問題」は単なる「ダシ」として使われているに過ぎぬ小道具であって「主役」ではない。作者の村上岳氏の(WEBサイト上に掲載された受賞の弁)「まったくSFではないです」という自己評は(謙遜じゃなく)偽らざる本心であろう ― これは「量子力学の観察(者)問題について書かれた理系文学」ではなく、「主人公(そしておそらく、作者自身)の悩み多き思春期の暗中模索の(未完結の)過程を描いた文系作品」なのである。たぶん、選考過程の初期段階では「とりあえず、残しておこう」という程度の扱いだったものが、二読・三読と重ねるにつれてジワジワ心に沁みてきて、最終的にはグランプリとしての評価を得た物語なのではないかと推測する ― こういう作品が(グランプリ/入選作含めて)ホシ賞にはもっと増えてほしいもの、と個人的には強く願うようなタイプの佳い作品である。
●之人冗悟の『第四回グランプリ)OV元年』の表面上の主役である「omnivisor:オムニバイザー」というガジェットは、「その利便性により人間の潜在的可能性を減退させてしまう危険をはらんだ最先端テクノロジー」の概括的アイコンとして(「効用」のみ記載、「構造」は不明、の形で)使われているのみ、真の主役は「テクノロジー依拠による人類の退行現象(・・・というか、坂道を転げ落ちる人類の定点観測手段としての<文体>)」である。この作品がグランプリに選ばれたのは「とにかくひたすらおもしろい!」から、だと信じたい之人冗悟ではあるが、もし万一そのグランプリ選考理由に「2012年あたりからビジネス界隈でも徐々に広がりを見せている『SFプロトタイピング』という近未来予測手法の具体例として好適」という「ミョーに現実的な理系性」が含まれていたとすれば、それは「ショートショートの殿堂としての<星新一賞>」のファンとして、かなり興醒めな話になるだろう・・・実際のところどうだったのかは知らないしホシ賞関係者に問うつもりもない之人冗悟ではあるが、そういう「口実としての理系性」に過度の敬意を表するような態度は ― 投稿者としても、読者としても、そして何より選考委員としても ― 厳に慎むべき態度であろう・・・でないと、「ホシ賞」は確実につまらない文学賞に成り下がるばかり ― 「理系の衣」に身を包んだ「文系的魂(literary soul)」が読者の心に響く作品が(数年に一度程度でもいいから)グランプリ取ってくれないと、この賞の先は暗いと思う。
・・・とか何とか言いながら、実はこの之人冗悟、『日経「星新一賞」』の未来には全然悲観していないばかりか、従前以上の強い興味・関心を寄せている ― 近々(ひょっとしたら来年とか再来年とかに)いずれ登場&常連化するであろう「AI作者による入選作」とグランプリを競うことになった場合、「人間の書いた物語」の勝利のカギとなるのは「理系的」ではなく「文系的」な何かであるに決まっているわけだから、「SF物語の作法に専門的鍛練を積んだ理系プロ作家志望者」や「SF的な物語とはどういうものかの学習データを十分蓄積した人工知能に最適なパラメータ設定を施したAI研究者」との(やる前から負けが見えている)空しい競争を最初から放棄するところから始まる賢い創作態度で「理系の衣に包まれた文系的魂を持つ作品」を寄せてくれる投稿者の数が(現状の数十倍ぐらい)増えてくれることを(2025年の時点で)願う一方で、この願いはそう遠からずして叶えられることになるだろうという(ゾクゾクとゾーッとの共存するambivalent:相反する感覚の)確信を抱いてもいる ― 「AI(人工知能)が書いた作品、SF文学賞を受賞!」というセンセーショナルな見出しが各種メディア上に躍る日が来れば、そこから先は誰もが自ずと「AI(≒プロのSF作家・・・志望者たち)が考えるSF的物語」の”逆張り(≒文系傾斜)”へと靡くわけだから・・・
今春(2025年3月)、新潮社から『星に届ける物語』という文庫本が出版されている。なんか『お星さまになっちゃったあの人に届けたい思いを綴った鎮魂歌集(♪千の星風になって~♪)』っぽいタイトルなので、書店で見かけてもSFファンには見過ごされちゃいそうな本だが、中身は『日経「星新一賞」』の第一回から十一回までのグランプリ作品を集めたアンソロジーである・・・タイトルが『ホシに届ける物語』なら『エヌ氏の遊園地』っぽい響きで「あ、星新一の新作だ!」と一発でわかってもらえそうな感じだが、実際には「星新一賞の旧作品群」なのだから、まぁ『ホシ』じゃなくて『星』なのはこれはこれでいいのだろう・・・星が出てくるわりには表紙の背景が青空なのは「昼間の星はなかなか見えません(≒ホシ賞もまだまだ<スター待ち>の状況です)」のメタファー(隠喩)かもしれない・・・とか余計な事言っちゃうのは(たくさん売れれば印税もらえる立場としては)不義理というものだから、話を元に戻そう ― 「星新一賞に投稿」するような人達なら、『星に届ける物語』なんてわざわざ買わなくとも「過去のグランプリ作品群の傾向と対策」はもう(WEBサイト上で公表されている各年度の入選作をじっくり読んで)十分練っているかもしれない(&その結果として「いかにも理系っぽいやつ」書かないとダメ、みたいな自滅的決意を固めちゃってるかもしれない)が、過去のグランプリ作品群の特性について俯瞰的に眺めてみようという戦略的購買動機をもってあの文庫本を手にしたグランプリ志望投稿者(がもしこの文章を読んでいた)ならば、ここまでの之人冗悟の言い分を踏まえた上で、11本のグランプリ受賞作を以下に掲げる順番で読んでみれば、きっと何かしら得るところがあると思う:
『(No.10=2023年)楕円軌道の精霊たち』by 関元聡(p.221)
『(No.5=2018年)Final Anchors』by 八島游舷(p.93)
『(No.1=2014年)「恐怖の谷」から「恍惚の峰」へ~その政策的応用』by 藤崎慎吾(p.26)
『(No.6=2019年)SING×レインボー』by 梅津高重(p.123)
『(No.7=2020年)森で』by 白川小六(p.149)
『(No.11=2024年)冬の果実』by 柚木理佐(p.247)
『(No.2=2015年)次の満月の夜には』by 相川啓太(p.27)
『(No.4=2017年)OV元年』by 之人冗悟(p.71)
『(No.3=2016年)ローンチ・フリー』by 佐藤実(p.49)
『(No.8=2021年)繭子』by 村上岳(p.175)
・・・最後にもう一つ、『第63回日本SF大会@蒲田』(通称=かまこん)の『日経「星新一賞」を語ろう』(2025/08/31)の部屋に於ける某選考委員の「希望を込めた疑問」を(多少アレンジを加えた形で)紹介して、この文章の締めとしましょう ― 『一万字のショートショートに、<思い切り感情移入できる主人公>を求めるのは、やっぱり難しいのかなぁ?』・・・それが無理じゃないことは『ローンチ・フリー』や『繭子』が証明していると思いますが、残念ながら、実証例がまだまだ足りません ― 『日経「星新一賞」』は「思わず感情移入しちゃうような主人公の情念の物語」を渇望しているのです!
。。。以上、第四回(2017年)グランプリ『OV元年』作者(プロ作家ではない語学屋)之人冗悟(Jaugo Noto)の、ウルサい独り言でした。。。
2025年9月15日(月)
・・・第十三回『日経「星新一賞」』応募締切まであと 22 days 05:05:05・・・
