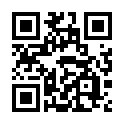
2025年7月17日、『第63回日本SF大会へのご招待につきまして』というタイトルで、『日経「星新一賞」』経由での招待状めいた電子メールが届いた ― <グランプリ受賞者全員(第1回より)及び第12回受賞者(ジュニア部門を含む)>はゲストとして無料で参加できるらしい・・・のだが、以下の理由から、この件は1ヶ月以上ほったらかしにしておいた:
(1)(星新一&Star Trekへの入れ込みを除けば)さほど熱心なSF読みではない &(早稲田大学第一文学部英文科卒なんぞというエラそうな肩書きはあるけれど)文学なんてまどろっこしくてほとんど読まない & (英語教材作成者という職業柄、英文/日本文の執筆は四六時中しているけれど)商業作家になるつもりは毛頭ない・・・というこの之人冗悟に「日本SF大会」なるものに参加する資格が果たしてあるのか否か、いささか疑問;
(2)「短文執筆の技の冴え」といういわば「語学屋の腹芸」でグランプリ(&賞金百万円)ひっさらっておきながら「日経『星新一賞』」にも日本の出版業界に対しても何一つ期待値(≒100万円)相応の利益還元もしていない恩知らずの之人冗悟が(仮に「グランプリ受賞者」の一人として引っ張り出されたとしても)『日経「星新一賞」を語ろう』とアツく意気込む参加者のみなさんの御期待に沿えるか否か、はなはだ疑問;
(3)そもそも「1962年から開催されている、SFファンが集まるお祭り」と言われても、sci-fi nutsでもない Jaugo Noto にはそれがどんなお祭り騒ぎなのやら皆目検討が付かない・・・ので、場違いな喧噪に振り回された末に祭りの後の空しさ抱えてトボトボ帰る羽目になるやも知れぬ8月30&31日の猛烈残暑の蒲田行進曲は、奏でづらい;
・・・と思っていた之人冗悟が、土壇場の8月20日になってからエントリーを決めた理由は以下の通り:
(A)8月17日に’かまこん’公式サイトで公開された「お祭りの中身」の案内をざっと見て、「これは純粋に’野次馬’として覗き見させてもらうのも面白そうだ」と感じさせる出し物があった;
・・・具体的には以下の6つ:
<8/30>
『環境問題や生命科学をSF的思考で考える』(11:00~12:30)
『大田区オタク計画』(12:30~14:00)
『サイバーセキュリティのフィクションとリアル』(14:00~15:30)
<8/31>
『筑波大でSFプロトタイピングしたら』(11:00~12:30)
『AIで小説を書こう』(12:30~14:00)
『ロボットやAIと人間の関係性を考える』(14:00~15:30)
(・・・最後のやつだけは『日経「星新一賞」を語ろう』と同時刻開催につき出席断念、それ以外は全出席)
(B)(いまや全世界的に市民権を得て数寄者の道を大手を振って歩ける’日本のアニメマニア’なんかとは異なり)世間一般からは「(アニメのようなeasy ring of compassion:たやすく広がる共感の輪を持つわけでもない各人各様の不可思議な言語で語り合う、というか独り言を言い合う、なんとも近寄りがたい)anomaly:変わり種」として距離を置かれる「SFファンという名の特殊生命体の集まり」の一種異様な(ものになるであろう)’お祭り騒ぎ’を、ゲストとして呼ばれた「部外者」の立場で堂々と面白がって観察させてもらう機会は、逃すには少々惜しい気がする;
(C)8月13日時点での参加者リストには、「日経星新一賞入選者」として以下の各位の名前(敬称略)があった:
■八島游舷(2018年グランプリ&優秀賞、2025年優秀賞)
■揚羽はな(2019年優秀賞)
■関元聡(2020年優秀賞、2022年グランプリ、2023年グランプリ)
■松樹凛(2021年優秀賞)
■菊池誠(2023年優秀賞)
■木下充矢(2024年優秀賞)
■玖馬巌(2024年優秀賞)
■形霧燈(2025年優秀賞)
■門間紅雨(2025年優秀賞)
・・・形霧燈・門間紅雨 の両氏は「本年度(2025年 第十二回)のホットな入選者」としてのゲスト参加かもしれないが、それ以前の入選者の面々は(グランプリ受賞者以外は’自費参加’であることからしても)「純然たるSFファン」&「プロ作家(orクリエイター)志望」であろうことが容易に想像できる;
「今年度の<日経星新一賞入選者>は無料」+「過去の<日経星新一賞グランプリ受賞者>は無料」という優待条件に加えて、「<日本SF作家クラブ会員>は無料」という規定もあって、これら3条件に照らして言えば、上掲の「ホシ賞参加者」の面々は全員「無料参加」だった・・・というインプットを、今回『日経「星新一賞」を語ろう』の企画でお世話になった平井博英氏からいただいた ― やっぱりみなさん(之人冗悟以外は)とってもマジメな「クリエイター(志望)」だったわけだ・・・
― 平井さん(会場内&外 奔走まで含めて)いろいろありがとうございました。来年度「山陰SFコンペ<雲魂:くもこん?・・・うんこん?>」の実行委員長の大任も、ゆるゆると心地良い感じで務められるよう、お祈りしています)
・・・八島游舷・関元聡の両氏に至っては、グランプリ受賞者であり、複数入選者(=星新一賞投稿常連組)であるのみならず、今回の「日本SF大会」での出し物にも積極的に参加している(前者は『筑波大でSFプロトタイピング講義したら』のプレゼンター、後者は『創元SF短編賞サイコロトーク』&『映画ドラえもんの世界』の企画参加者);
・・・そもそも「日経星新一賞」自体、この之人冗悟の『OV元年』という’素人の腹芸’がグランプリを受賞した第四回(2017年)の翌年あたりから、「プロ作家志望の入選者」が増えて(良かれ悪しかれ)「新人作家の登竜門」という’普通の文学賞’っぽい存在へと変貌を遂げつつある(or遂げてしまった?)感がある;
・・・上記の事情を勘案すれば、「プロフェッショナル志向の入選者たち」に混じって「商業作家ではない(&なるつもりもない)グランプリ受賞者」の之人冗悟が「場の調和を乱す攪乱要素」として存在することには(予定調和への懐疑と嫌悪を構造的特性とするSF文物について語り合う場としては)それなりの意味がある(かもしれない);
・・・「意味」ということで言えば、足かけ三十年もの「英語の大仕事」にようやく一区切り付けた今年の三月以来、「次なる大仕事」に向けて動き出す「きっかけ(・・・有り余るほどある”創造意欲”ではなく、absolute zero状態の”共同企画者”探し)」を(三十年来の「孤独な創作奴隷生活」を勤め上げた御褒美として)「ぼ~っと遊び歩く日々」の中で漫然と求めつつ過ごすのがテーマの(2025年の)之人冗悟にとって、8年も昔の手慰みを契機とするこの「SF界隈からのお誘い」には、「<理系的発想から始まる文学賞>から始まる<想像的創造から始まる現実世界の一大変革>へのキュー(cue:始動の合図)」としての意味がある・・・かもしれないと感じさせる程度の魅惑的偶然の波動がある・・・まぁ、今回の hopeful vibes(期待の波)も(毎度のごとく)潮が満ちる前にスーッと幻の如く引いて消え去る結末に終わるかもしれないが、無意味にせよ有意にせよ「偶然」への敬意は然るべく払うのが「想像的創造主」の基本的体質というもの ― 今のこのクソマジメ極まる日本に(たとえ「SF」界隈とはいえ)そうした「真の創造的想像力の持ち主(・・・要するに”ヒマな物好き”)」が何人程度存在するものか、probe(探り針)入れに行くのも一興だろう・・・ということで、8月30日(土)・31日(日)の「異界探訪」に向けての下準備をいそいそと始める之人冗悟なのであった。
初日8/30は「(午前10時の)開会式」に間に合わせるべく少し早めに会場へ。母校の同窓会に出るならともかく、知り合いに出くわす可能性ゼロと思われる「SFファンの集い」に、SFファンでもないくせに『日経「星新一賞」を語ろう』へのお呼ばれゲストとしてのこのこ出向いた「異邦人」としての立場を自覚している(&楽しんでもいる)身分としては、そんな自分のアイデンティティを明示するべく「第四回(2017)日経星新一賞グランプリ『OV元年』作者 之人冗悟」と記した白い旗印を胸に抱え込んだリュックから突き立てて歩きつつ、ついでに「英単語12500語がタダで学べるモニター権つき名刺、配布中」(ユーザー名=foc/パスワード=kamaconで2025/09/01~09/30有効)とチマチマ書いた画用紙を背中にヒラヒラさせながら会場内を練り歩くスタイルを取ってみた(・・・いずれも反応ゼロだったので、二日目にはどっちも引っ込めた ― 観測気球の打ち上げは一回で十分だから・・・)。
会場入口へと続く受付順番待ちの人々の列は、予想外に長かった ― そして、予想以上に年齢層が高かった・・・まぁ、そういう自分とて還暦過ぎなのではあるが、「異邦人」たる自分の立場は「会場周辺をフワフワ漂う幽霊」みたいなもの、お化けに年齢はないので(なんか、相当年季が入った喫茶店のマスターかお花の先生みたいな人達の行列だなぁ)などと自分自身を棚に上げつつ、「かまこん」で最初の「sense of wonder:こりゃおどろいた感覚」を催すこととなった。
その行列が、なかなか前に進まない ― (もうすぐ午前10時だから、開会式には間に合いそうにないなぁ)と感じつつ、入口受付の方からあたふたとした足取りで列に並ぶ人波をキョロキョロ確認しに来た”スタッフ札”ぶら下げた年配男性に向かって「開会式って、もう始まっちゃいます?」と尋ねてみると、「いやぁ、まだみたいですけど・・・自分もさっき知り合いにとっつかまって”受付手伝って!”って仰せつかったばかりなんで、段取りとか正直よくわかってないんで・・・」という何ともふわふわした返答、それを聞いた入場待ちの人々も呆れるでもなくむしろ訳知り顔の和気藹々(わきあいあい)度数が一層高まるような雰囲気に、(なるほど、これが日本のSFファンの集いか・・・気心の知れた古い友人どうしみたいな輪なんだろうな・・・実際、古い人達ばっかだけど)と、心温まる感覚になったのだが、この日の東京は最高気温37度、心はいいが身体まで暖まりすぎちゃうと(年齢層高めの集団だけに)熱中症卒倒者カウントの増大がいささか心配な感じではある・・・まぁ、自分の場合は(我が家へのエアコン設置作業員のお兄さんたちの姿にヒントを得て密かに調達しておいた)「ハイバックファン空調服」が役に立ちそうだからいいんだけど・・・ということであと30分待ちぐらいは余裕でド~ンと受け止めるつもりでいたところへ、また入口の方からやってきた(明らかにプロっぽくない)受付の人が「この中で、開会式に出席予定のゲストの方、いますか?」と公開質問していたので、「あ、自分はこういう者で」と白い旗印をヒラヒラさせて「日経星新一賞でグランプリ取ったごほうびにタダで入れるから、おいで、と御招待受けたんですが」と説明すると、長蛇の列の一般参加者のみなさんを差し置いて「ゲスト待遇でスイスイ入場」させてもらうといういささか申し訳ない展開となった。
時刻は既に午前10時を回っているので、もう開会式は無理だな・・・と思いつつ、エスカレーターをいくつも乗り継いで地下三階(だったと思うが、もしかしたら四階だったかもしれない)の大きな講堂(だか体育館だか)に辿り着く ― まるで『宇宙戦艦ヤマト』の地球防衛軍地下司令本部までの長い道のりを思わせるこの仕掛け、さすが日本SF大会だけのことはある ― その巨大な(誇張抜きで、ほんと巨大な)地下講堂前方の大型スクリーンには「かまこん」の文字が静止したまま張り付いているので、開会式は既につつがなく終了したのだろう・・・その後方、講堂入口に近い方のスペースは、物品販売の出店エリア、まだ初日の開会式直後なので、展示物準備中の活気ある慌ただしさが会場をザワつかせている。
そんな会場の片隅に、白いボール紙の直線的組み合わせで造られたメカザウルスっぽい恐竜の展示物を発見、というか、その中に入って何やら動き出しそうな人間を発見、さらに接近してその頭部近くに赤くて痛々しいエラのヒレヒレが付いているのを確認するに至って、ようやくそれが「実はシンゴジラなんです」という事実を認識、思わず緩んだ口元から「これ、直立歩行は可能なんですか?」とボール紙ゴジラの介添人らしきヒトに向かって発した質問に「可能です。ここは蒲田なので」という答えが返ってきたところで、(SFファンです、どうぞよろしく)の最初の御挨拶を交わした気分になる(・・・筆者注: 「直立歩行可能になったのは品川からであって、大田区蒲田通過時点ではまだ匍匐前進による蛇行だったはずでは?」とかいう無粋なツッコミ入れるのは御法度である) ― 幾多の来場者にそうした「かなり敷居の低いSFファンとしての身元証明機会」を振りまきつつ会場内を二日間に渡って直立歩行し続けたこの白い紙ゴジラ(「白かまたくん」)は、ブッチギリ独走の形で「暗黒星雲賞コスプレ部門」を受賞することになったことをここに付言しておかずばなるまい。
この「白かまたくん」を巡るやりとりは、映画『シン・ゴジラ』(2016年)を観たことのある人なら思わずニンマリしながら(ウンウン、なるほど)とうなずきつつ聞くことだろうが、あの映画を観ていない人にとってはワケのわからん珍問答 ― 「日本SF大会」に足を運ぶ人達が「『シン・ゴジラ』なんて知りませ~ん」というはずはあるまい、という前提の上で会場内を闊歩し続けてみなさんを納得のスマイルで包んでくれた(からこそ「暗黒星雲賞コスプレ大賞」の)「白かまたくん」なわけであるが、これはそっくりそのままこの「かまこん」のそこかしこで交わされる会話の全てに通じる構図となる ― 相手が当然それを知っているという前提の上で投げ掛ける謎掛けの「白いボール紙」を前にして、「それって、もしかして『シン・ゴジラ』ですか?」とかの確認のど真ん中ストレートなんて投げ返したりせずに、「直立歩行は可能ですか?」とか「エネルギー源は何なんですか?」とか「冷えてない状態になったら、特殊建機小隊がスポーツ飲料の経口投与を試みたりするんですか?」とかの外角高め暴投スレスレのスピードボールを投げ返すことで、「こっちは、このレベルまで、わかってます・・・ってこと、わかってもらえましたか?」とやるわけである。そういう「知ってる?/知ってる!」の謎掛け/答え合わせのヘンテコキャッチボールを ― 後逸したボールをひぃひぃ言いながら追っ掛ける惨めなウンチ(運動音痴)の面々を尻目に ― ニンマリ顔で成立させることのできる自分自身の「SF運動能(or連動脳)」のレベルの高さを確認するために/あるいは自慢するために/あるいはアップデートが必要な脆弱性を発見するために参加するのが「SFファンの集い」というもの・・・という事前予測を裏切らぬディープな情報のスマッシュとリターンのボレーをそこかしこで確認できた「かまこん」を(事前の予想以上に)「面白い!」と感じてしまっている自分自身を発見して(こりゃ、ちょっと、マズいかも)と頭をかいちゃった之人冗悟なのであった。
上述の個人的「マズい」は「コワいもの見たさにお化け屋敷に入ってみたら、鏡に映った自分自身の姿が、お化けだった」の意味であることは言うまでもないが、ここではやはりもう一つの「マズい」についても触れずばなるまい ― 最初に述べた「日本SF大会参加者の年齢層の(かなりの)高さが、ヤバいかも」という懸念である。より正確に言えば「若い層が古参のSFファンの輪に加わりづらくなる/加わりたくなくなる構図が、SFファンダムには構造的宿命としてつきまとうのではないか?」という懸念である。
実は、この之人冗悟にとって、上述の「謎掛け/答え合わせ」のキャッチボールを「かまこん」で最初に成立させてくれたのは、「白かまたくん」ではなくて、「かまこん」のパンフレット冒頭にある第63回日本SF大会 実行委員長の櫻井晋さんの「実行委員長 御挨拶」なのであった ― 状況を説明しよう: 8月17日に「かまこん」で公開されたプログラム内容のうち、一つだけ(あんまりSFっぽくないなぁ、これ)と感じた企画があった ― 『大学生読者20名で「最強のSF」を決めます』(8/30, 11:00~14:00)というやつである。そのタイトル自体はSFっぽいのだが、その内容説明が「政治的」というか「保守革新対立構図的」というか、とにかく非SF的だったのである・・・曰く: 『高齢化著しいSF界隈に新風を吹かせるべく各大学SF研から現役大学生20名を招集。今一番アツいSFをオールジャンルで探求します。今こそ”新しいSF”を始めましょう!』・・・時空も軽々超越するSFの世界で、高齢化もないもんだろう(年齢逆行現象なら「あぁ、ユービックね!」ってことで話は通じるけど)というヘンテコ感覚を催したこの之人冗悟だったのであるが、それはあくまで「SF論じるのに年齢なんて関係ないと思うけど?」という客観的違和感であって、「頭デッカチの大学生どもが”これからは自分たちの時代だ! 年寄りは消えろ!”とか叫んでやがらぁ・・・どうせてめぇら”sophomoric”の意味も知らねぇんだろ?」みたいな「排除対象として名指しされて激高する高齢者の私憤」ではなかったことを(付言する必要はないけど)白状しておく ― 「高齢者」とか「若年層」とか「日本人」とか「sci-fi proper / layman」とか、そういう一切の枠組みを離れた「stranger:外れ者」というのがこの之人冗悟の唯一の属性なので・・・とかそういう個人的状況はこの際どうでもいいのであって、ここで問題なのは「高齢化著しいSF界隈」とか「新しいSF」とかのジェネレーション問題が(ジェンダー問題の次なる波みたいに)近頃のSF界の新たな潮流になっていたりするのだろうか? という素朴な疑問のほうである ― その「答え合わせ」は、上述の「かまこんパンフレット冒頭部の実行委員長 御挨拶 by 櫻井晋さん」が可能にしてくれたのであった ― 曰く:
●『近年、年次日本SF大会は参加者やスタッフの高齢化が深刻な課題となっていると感じています。かつては大学生が中心となって開催されていた大会も、今ではベテランスタッフによる運営が主流となり、少数精鋭の体制となっています。しかし、それが故に大会の活気が失われ、先細りの状況を招いているのではないかと考えています。』
●『現在、定例化されすぎたイベントは、居心地は良いものの、新規参入者にとっての敷居を高め、門戸を狭めているのではないでしょうか。特に学生の参加者が少なくなった現状を見て、若い世代への認知度が不足していると感じています。』
●『「新しい出会い」と「創造」をテーマに、サイエンスフィクションに限らない幅広いSFの可能性や、SF大会の未来、新時代を担うクリエイターたちとの出会いを考えます。』
・・・なるほど、SF大会実行委員側のそうした危機意識を土台として成立していたのが、件の『大学生読者20名で「最強のSF」を決めます』の「ジェネレーション問題発言」だったわけだ・・・そうした contextual comprehension(脈絡を土台とした理解)に乗せて眺めればすんなり腑に落ちる挑発的文言だったわけであるが、はてさて、この「わかってる?/わかってる!」の暴投スレスレキャッチボール、実際「かなり年齢層が高い’かまこん参加者たち’」の面々は、きちんとキャッチできたのだろうか? はたまた「私憤に駆られてフンっ!」って感じで『大学生読者20名で「最強のSF」を決めます』に背を向けて終わりだったのだろうか?・・・ま、こういう面での「認識の深度」を問題にするのは「SF大会」よりは「文壇」寄りの態度なので、SFファンは(理解度ではなくて)無邪気な「知識確認」のやりとりに終始しておいたほうが平和でいいだろう(&実際そうなっているのだろう、この「かまこん」の和気藹々ぶりからして)と感じる之人冗悟なのであるが、この「SF界隈のジェネレーションの壁問題」に関する私見ぐらいはここで述べておくべきだろう ― 再三白状している通り、SFにさほど詳しいわけでもなく、SFファンの集いにも今回2日間参加しただけの「外れ者」の言うことなのだから、「フンっ、何もわかってないくせに、わかったようなこと言ってやがらぁ!」という風に受け流し易いのも救いだろうから、目クジラ立てずにボール紙ゴジラの徘徊眺めるようなおおらかな気分で見てもらえればいいと思う・・・
・・・あ、言い忘れてたけど、「第63回日本SF大会 ‘かまこん’ 開会式」は、実はまだ終わってなかった、というか始まってすらいなかった ― 長蛇の列を成していた来場者たちの会場誘導にゆ~ったりと時間がかかったりしたので、10:00の予定が実際には10:30過ぎまでズレこんだのである・・・そうしたグダグダ展開をもまた「SF大会の持ち味」として玩味吸収してしまう懐の深い「古参参加者たち」の温かい支持を得て、会場内を(かなり燃費の悪い走り方で)二日間奔走してくれた末に堂々「暗黒星雲賞」(よくがんばりましたで賞、みたいなやつ)を獲得した「受付」が会場からの万雷の拍手と笑いで讃えられたのは、最終日8月31日の閉会式でのこと ― こちらもまた予定より40分ほど遅れてのグダグダスタートであったことも付言しておくべきであろう・・・という「SF好き&SF大会大好き」なスタッフのいじましい努力によってゆるゆる展開する日本SF大会の愛すべき実態のレポートで話の流れを和ませた上で、ここから先はいささか辛口の論旨展開に入る・・・
事の本質が「最近の若者はSFを読まなくなった」ということであればこれは深刻な問題だが、実際には「SFは若者にもちゃんと読まれている」けれども「最近の若いSF読者は日本SF大会に参加しなくなった(or参加したがらなくなった)」というだけの話なので、「このままでは日本SF大会の未来は暗い」とは言えても「SFという文学ジャンルの未来は暗い」という話にはならない・・・と思う。SF以外の「フツウの文学」に関してはこれはもうハッキリと「未来は暗い=今の時代の人間たちのほとんどは<純文学>みたいな代物にはもはや何の必然性も魅力も感じていない」と言えるので(その業界に身を置いている人々にとって)問題は絶望的なまでに深刻だが、旧態依然たる枠組みの束縛から(表現技法のチマチマした衣替えレベルを超えて)自由になることができない他の「マトモな文学」の枠組みに収まりきらない「異物性」が持ち味のSFに関して(だけ)は、科学技術の進歩(or暴走)や社会経済の変化(or崩壊)やそれに伴う人間心理(and行動)の”異常化”といった「ブッ飛びすぎて、在来型の文学では扱いきれないもの」を描く自由を生まれながらにして手にしている「外れ者のジャンル」なのだから、世界や人間の変容に合わせて(その変化の一歩~数歩先を想像的に創造する形で)絶えず変容を続けるSFの物語に「行き詰まり」はあり得ない・・・唯一、「人類滅亡」によってその書き手/読み手を失った時に終止符が打たれるだけの、壮大な思考実験の絵巻物が「SF」なのだから、「SFの未来は暗い」ということはあり得ないのである。
一方、「日本SF大会の行き詰まり感」は、「(SF以外の)文学界の閉塞感」と同一構造上にある問題 ― 要するに「器が古い」ので、そんな古びた器に「メシ盛って食おう」と考える人間が(古来ず~っとその器でメシ食ってきた古い世代以外には)存在しなくなった、というだけの話・・・だと思う。
「文学」という日本語はいかにも厳めしくて立派だが、英語で書けば「literature」=「letter(文字)が織り成す物語」であり、「文字以外の媒体で語られる物語」との対比構図の上にある「ストーリーの1形態」に過ぎない ― これと対比される別媒体上の「物語」として「oral story:口に乗せて語られるお話」(「folklore:民間伝承」や「legend:伝説」も含む)があり、その場に居合わせた人々の口から耳へ(そして心へ)と伝わる一過性コミュニケーションの形で雲散霧消してしまうその宿命を惜しんだ欲深い誰かさん(=文学者)が、これを「時間・空間の制約を超えて語り継がれ読み継がれるもの」にしようとがんばった結果成立したのが「literal (as opposed to oral) tale:(口述型と対比されたものとしての)文字型のお話」としての「literature:文学」なわけである。これと対比されるものとしては、「語り」に加えて「舞踏」・「音楽」という媒体をも巻き込んでの視覚・聴覚アピールの極大化を狙ったcrossover art(ごちゃ混ぜ文芸)としての「drama:芝居」があり、「文字が読めない一般大衆」は「芝居」を見、「文字の読み書きができる上流階層」は「文学」を読む、という対比構造が、「観客層」と「読者層」の社会経済的階層の違い(≒貧富の差)をそっくりそのまま反映していた ― 「本を読む人」は「本を読まない(というより、読めない)人」よりも「ポイントの高い人」という構図が全ての人々の暗黙の了解事項となっていた ― この対比構造の上に立って、「本を読んでいる自分」・「本を通して仕入れた知識を人前でひけらかせる自分」の姿を以て「他者より上の自分」を演出する、という(世に”俗物”と揶揄される)行動様態に走る人間が古来(=「筆記された物語」の誕生以来)跡を絶たなかったわけである。
しかしながら、「本(を読む者としての、自分)の威光」の放つまばゆい光は、時代を下るにつれて、鈍くなる。最もまぶしい目もくらむような威光を放っていたのは「古代エジプトの神官文字(hieroglyph:ヒエログリフ)」の頃 ― 現代英語で「hieroglyphic」と言えば「象形文字の」というマジメな語義に加えて「何が書いてあるんだかさっぱりわからない」の意味をも表わすが、それが「わけわかんない」背景にあるものは「判読困難な図柄」という「物理的障壁」ではなくて「部外者にわからせてたまるか!」という一部知的特権階層の「保身のためのバリア」だと見るのが正しい見立てであろう ― 「誰にでも読める」ものになってしまっては「神官の知的威光」に影が差してしまうので、「神官文字」は「わけわかんない」状態のまま、「民衆文字:デモティック(demotic))」しか読み書きできぬ下々の民を置き去りにし続けねばならないわけである。日本では長らく(現代に至るまで)「『源氏物語』を読んでいるか?」が知的エリート層と卑賤階層を分ける保身バリアとして大手を振って罷り通ってきたが、それはあの物語の「文学としての価値」とは全く無関係な「社会経済的選別(=全54帖にも及ぶあの長編物語の写本を入手できるほどの恵まれた地位に身を置いていることを示すstatus symbol:地位の象徴)」として行なわれてきた慣行であって、「物語としての価値」だけを問題にするならば「『竹取物語』の先駆的SF性」とか「怪異譚としての『宇治拾遺物語』の秀抜さ」についてアツく語り合う日本人の姿だって見られて当然のはずだったのに、現実には「あなた、『源氏物語』は当然御存知よね?・・・え? 知らないの?・・・それは困ったわねぇ、ワタシたちの世界ではそれ、常識なんだけど・・・」という形の「社会的ふるい分け」の横行の流れの中では「”源氏”の一人勝ち」状況が(今に至るまで)続いており、文学的価値としては”源氏”以上のものがある『平家物語』なんかはまるっきり問題外なわけである ― 「盲目の琵琶法師の語り」を通してありとあらゆる社会階層の人々の耳を引き付け心を揺らすその「文学的アピールの普遍性」ゆえに(=「社会的排他性」からは最も遠い「物語り」であるがゆえに)、「『平家物語』は『源氏物語』のような<知的エリート層のパスポート>にはならない」からこそ、「『源氏物語』の名場面・登場人物・作中和歌を引き合いに出すことで、自分の知的洗練度を他者にアピールしよう」と考える俗物的富裕層は古来引きも切らさぬ一方で、「『平家物語』の中で語られた悲しい一族の栄枯盛衰について、文学的に語り合おう」というマジメな鑑賞者の輪は相対的に(…絶対的に?…)広がらないわけである・・・が、日本のような「文学的(議論)不毛の地」はさておいて、諸外国に於いては、「ヒエログリフの威光」はもう歴史のかなり早い時点から段階的にその「化けの皮」を(日本よりはかなりワイルドな形で)剥がされ続けている。中世までの西欧では「教会の奥底に秘蔵された書物を修道士がいちいち手書きで書き写して作った写本」を入手せぬ限り手に入らなかった「秘蔵の知識」が、グーテンベルクの活版印刷術によって「大量生産・大量配布される出版物」の形で大衆の間に流布することにより、技術革新としての「印刷革命」が、社会変革としての「宗教改革=カトリック教会という旧権威の没落」や、芸術・科学・文明の大変革としての「ルネッサンス」をもたらしたのが15~16世紀のことであったが、この「本の普及」は、「秘宝としての知識の独占者たるカトリック教会」の権威を引きずり下ろすのと入れ替わるようにして「本を読む(のを生活習慣とする)知的エリート」の新たな権威を生じる「威光の光源」となったので、「読書家=知的水準の高い人」という単純図式の上にアグラをかいての「本読み誇り」は、この時代に「生まれた」ものであって、「時代遅れになった」と言えるのはまだまだずっと先の話である・・・「本の普及」を「英知の普及」へと結び付けようということで始まった西欧の「啓蒙運動(the Englightenmentまたはilluminatism)」に対し、「そんなのウザ~ぃ!」と反発する「反啓蒙主義(Obscurantism)=無知蒙昧のままで何が悪ぃ~運動」が見られたのはザックリ言って18世紀頃・・・目を日本に転じて見れば、当時既に「本」は(世界的に見ても特筆すべきほど)普及していたこの国に於いて、「本(を中心とする大衆文化)の通俗的享楽性」を問題視した老中 松平定信の主唱する「寛政の改革(1787~1793)」のスローガンであった「文武両道・質素倹約の勧め」などは「本の権威を重んじる側」からの「反享楽主義(anti-epicureanism)」と言えるだろうが、これに対する一般大衆の反応は「世の中に 蚊(斯)ほどウルサきものはなし ブンブ(文武)と言ひて 夜も寝られず」という狂歌に集約されるような「obscurantism:反啓蒙主義」的なものであった・・・といった感じで、「本」がそこそこ以上世の中に出回っていた「読書文化先進国」に於ける「本読む知的エリートvs.一般大衆」の社会心理的対立構図には(少なくとも1700年代からの)長い歴史があると言ってよいだろうが、その対立構図に於ける「勝者」は常に「社会経済学的勝者としての<本読む知的エリート層>」の方であり続けた ― 世の中で「本(を読むことで得られる知識・情報)」が「知的アクセサリー」としての輝きを放ち続ける限り、これは必然の構図であった ― そんな「本(とそれを読む知的エリート)一人勝ち状況」を切り崩したのが、20世紀末に始まる「インターネットの全世界的普及」である。より具体的に言えば、「(Googleに代表される)ネット検索(により即座に得られる膨大な集合知が、読書人の脳内蓄積ネットワークとしての個人知を凌駕しほとんど駆逐した状況)」と「(Wikipediaに代表される)ネット百科辞典(により手軽に得られる知識の網羅性・正確性・閲覧性の高さが、読書人のあやふやな脳内個人知はもとより、不便極まる紙の本の存在理由をも霞ませてしまった状況)」と「(ネットを通じて得られた膨大な知識・情報の匿名性受け売り広場としての)SNS上での<知識開陳>(によって、古来<選ばれた知的エリート以外、お断わり>であり続けた<知的フォーラム(含 大学・有識者会議・文壇・日本SF大会・etc,etc.)>の排他的威光に陰りが生じた状況)」といった「ネット革命」の波を受けて、「本(とそれを読む人々・・・の輪)の威光」は、21世紀に入ってからというもの、すっかり陰ってしまったわけである。
・・・上の論述の中で、「排他的な知的フォーラム」の一つに「日本SF大会」を組み入れてしまったことに対しては、「SF界隈」からの反発があるかもしれない ― 実際、「本筋のSFファン」は、「SFファンの集い」で「自分の知識・情報はこんなにスゴいんだぞぉ~!」みたいなマウンティング行動に出たりはしないはず(そういうことをやらかす「器がちっちゃなおともだち」の振る舞いを咎めることもなくニコニコ笑って受け流しつつ、彼らがちょくちょく投げて来る「取れるものなら取ってみろ!」的大暴投の数々を「余裕の長い手」で受け止めてはまたサラリとボールを投げ返すだけの「頼れるキャッチャー」の役回りを微笑浮かべて演じるはず)である・・・『日経「星新一賞」を語ろう』の部屋で交わされた「自分はSFにそんなに詳しくないんですが」vs.「SFに詳しい人は皆さんそうおっしゃいますよねぇ」という静かな問答がこのあたりの事情を雄弁に物語っていて、聞いていて実に心地よかったものである・・・けれども、そういう「受け身姿勢の静かなる知の巨人」は「SFフォーラム参加者」としては例外的な存在であって、大方の参加者は「自分の持っているSF知識」が「どれだけスゴいか・まだまだショボいか」の「答え合わせ」のためにフォーラムに来るわけである。そんな確認行動などせずとも「自他共に認めるスゴい人」だけはフォーラムの中では「例外的に静か」だが、それ以外の参加者の面々は「武者修行の場」としてフォーラムに「参戦」する以上、そこには自ずと(「斬るか斬られるか」とまでは言わぬまでも)「自分は最後までブッ倒れずに立ち続けていられるか?」をドキドキしながら試し合う「攻めと受けとの丁々発止のやりとり」の稽古場の空気(ヘタすりゃ修羅場の生臭さ)が漂うことになる。「知の巨人」の微笑・苦笑・失笑(さらには当惑)を誘うばかりの「小物参加者による知識自慢発言の乱射乱撃雨霰」で荒れ模様になるのが「日本SF大会定番の図式」なのか否かはたった二日間「見学」しただけの之人冗悟にはわからないが、そうした潜在的揮発性(potential volatility)を構造的に宿した存在が<SFフォーラム>である、という見立てはたぶん筋違いな邪推ではないだろう。
・・・という事前見立てに照らして言えば、今回の「日本SF大会@蒲田(かまこん)」の「古参参加者たち」は総じて「静か」であるように感じられたが、それは(「かまこん」案内パンフレット冒頭部での実行委員長櫻井晋さんの言葉を借りて言えば)『(ベテラン勢には)居心地は良いものの、新規参入者にとっての敷居を高め、門戸を狭めているのでは』という危機感に裏打ちされた「ひけらかし・とっちめは御法度」という自制心発動の産物だったのではないかと推察される(まぁ、そうした「心のブレーキ」を欠く面々もそれなりの数はいて、それはそれで面白かったのだけれども)・・・そうした遠慮など一切なしの「修羅場スレスレのトンガった知識の相互確認広場」としての緊迫感がかつて(今の「古強者」が「身の程知らず&怖い物知らずの新参者」だった頃)の「日本SF大会の尖鋭的魅力」だった時代だって、きっとあったはずだ ― 『かつては大学生が中心となって開催されていた大会』が、そうそうおとなしいものであり得るはずがないのだから ― そうしたかつての「辻斬り上等! 受けて立つ! 皮を切らせて骨を断つ!」という「若かりし頃の日本SF大会」の図はこの之人冗悟のsupposed past(空想の中にしか存在しない過去)かもしれないし、そうしたディープな真剣勝負は(今も昔も)もっと考察対象と参加者の質と数とを絞り込んだ上でのclandestine debate(部外秘討論)の形で行なわれているのかもしれないが、今の世の「SFファンのお祭りとしての年次日本SF大会」がそうした「知性の刃を振り回しての(相互)試し切り広場」からは(おそらく、意志的に)遠ざかっているのだろう、というこの之人冗悟の体表感覚は、たぶん、的外れではないはずだ ― 何故なら、そうした「修羅場」としては「生身で向き合う(がゆえに”大怪我”もあり得る)SFファン交流会」よりも「匿名性の壁に隠れて自分が傷付く危険性を最小限に抑えつつ抜刀・辻斬りし放題の安全な自己主張空間としてのネット上」を選ぶ人間が圧倒的に多いはずであり、そうして世の中全体が「真剣勝負(で自分が傷付いたり他者を傷付けたりすること)」への耐性も寛容も喪失して加速度的に脆弱化して行く中、一人「日本SF大会」だけが「トンガった知的真剣勝負」を繰り広げ続けていたのでは「新規参入者にとっての敷居」が高くなりすぎて困る、という自制心が(昔はトンガっていた古参SFファンの間でも)機能するのが自然な流れだからである ― 「SF論争」も好きだが「SF大会」の方がもっと好き、というベテランたちの心には、必ずやそうした「牙隠し」の意識が芽生えるはずなのだ。
しかしながら、そうして古参のSFファンたちが自らのSF知識を決してひけらかさず他者の知識の浅薄さを決してあげつらうこともしない「新参者フレンドリー」な態度を取ったとしても、それだけでは「日本SF大会」への「若いSF読者の新規参入」を促す原動力には(残念ながら)ならないだろう ― 古参ファンは「古参」であるというただそれだけで「新参者」を凌駕する「SF知識&経験の蓄積」を持っていて、その「年の功」の分厚い壁は、新参者がネット経由でお手軽に調達した「付け焼き刃の知識や理論」ごときではビクともしない・・・かどうかは実際には怪しいが、そうした「古株には、自分はきっと敵わない」という「年功バリア」の感覚(or幻覚)を「若いSF読者層」が抱いている限り、「ネット上の自分の王国」に留まっていさえすれば安泰な「(大方は”ハダカの”)王様としての権威」をわざわざ自ら揺さぶられるために「日本SF大会」に遠征しよう、などと考える「若くて元気な新参者」の数は(絶無ではないにせよ)絶望的なまでに少ないはずである。
SFファンもそこそこ年季が入ってくると、長年に渡って自分が積み上げてきた知識や経験を「自己顕示」ではなく「後進指導」のために使いたい、という「メンター(mentor=老練な助言者)願望」が芽生えるものであり、そうしたベテランによるルーキーたちへの導きが、かつての「日本SF大会」には実際有効に機能していたのではないか(でなければ1962年から今まで存続しなかったのではないか)と思われる ― 幾多のファンが集まる年次SF大会ではない(もっと遙かにハードでコアな)「**勉強会」とか「**教室」とかの世界では今も昔もこれからもそうした「先達から後進への導き」の構図は常に見られるはずである。だが、「ネット上で幾多の<フォロワー>や<いいね!>を獲得して<物知り>・<カリスマ>・<インフルエンサー>・<!神!>云々と呼ばれていい気になっている若者たち」の圧倒的多数は、そうした「頼れる老練な助言者」を求めてもいなければ受け入れもしないだろう ― それは「自らの(幻想的)権威を自ら揺るがし否定するヤブヘビ行動」にほかならないのだから。そうして「ハダカの王様の美装」を自ら脱ぎ捨てて謙虚な初心者に戻って井の中の蛙の唯我独尊状況を脱して真の知の巨人への道を志す上でのmentorsとの出会いを求めるのであれば、「日本SF大会」はヨーダやオビワンがわんさかいそうな期待に満ちた未知の惑星っぽい輝きを放つだろうが、ネット世界で「いいね!」と言ってくれる「フォロワー」集めに狂奔した末にイビツに肥大した幻想の自己イメージをかなぐり捨てて冒険的探究心に目覚めた若者が「無知の知から始まる知の巨人への道」へと自分を導いてくれるソクラテス先生を求めて「日本SF大会」の門を叩く、という図は、『スター・ウォーズ エピソードⅣ/新たなる希望』よりもっと非現実的な夢物語のように思われる・・・ちょっと悲観的すぎる言い草かもしれないが、ネット世代の若者がメンター探しに出かける先は、やっぱり「サイバー空間上」であって「生身のSFファンの交流会」ではないような気がするのである。
ネット前代のSFファンにとって、「書を捨てよ、町へ出よう(=SF本はもう十分読み漁った、いよいよ知の大海原へと船出する時だ)」と思い立った際には、年に一度だけ出現するわかりやすい大海原としての「日本SF大会」の存在は「太平洋」並みに大きな大海だった(他はどれもみな「沼」・「池」・「水溜まり」にすぎなかった)のかもしれないが、インターネットという「無限に広がる大海原」が出現して以来、(「日本SF大会」に限らず)かつての「定番の大海」はどれもみな「水溜まりっぽい古参ファンの溜まり場」への降格を強いられているわけで、この「構造的先細り状況」を脱却するべく「若い世代への認知度不足」の改善を図る際には、「若者がよく見るTV&ネット番組で宣伝を打つ」だの「若者の目を引くようなド派手なイベント花火をぶち上げる」だのといった「ちっともSF的じゃない在来の地平線と地続きの発想」ではダメだと思う。
今の若者はおしなべて「権威」に弱い ― ネット上で集めた「いいね!」や「フォロワー」の数の多いヒト/モノの前には(その「質」など一切問わずに)あっさりと頭を垂れてしまうし、自分もまたそうした「(質など不問の)数の力」をセッセと集めれば「カリスマ」・「インフルエンサー」・「!神!」になれると信じている ― そんな「数の権威の盲従者」相手には「(カネにあかせて数をかきあつめるだけの)宣伝」の効力も絶大なのは確かだが、では「日本SF大会」も「宣伝を通しての知名度向上」を図ればそれでいいかといえばそれはむしろ逆効果であって、「知名度」と同時に「権威」が上がれば(これまで再三確認してきた通り)新規参入者にとっての敷居が上がり、門戸を狭める自殺行為なのだから・・・
・・・なんだかもう八方塞がりっぽい話の展開になってきたなぁ・・・と感じたそこのSFファンのアナタ(が、もしまだこの文章読み続けていたならば)、ぼちぼちこうも感じているんじゃありませんか ― 「こうしてドン底まで落っことしたからには、ここらで反転のドンデン返しが待っているはず・・・だって、おたく、『日経「星新一賞」グランプリ』取ったSF物書きなんだから・・・ちがう?」
・・・そんなみなさんの期待にこの之人冗悟が沿えるかどうか、あるいはみなさんがこの之人冗悟の期待に沿うような「本筋のSFファン」であるかどうか、ひとつ、次の章で「答え合わせ」をしてみましょう ― 「真剣勝負、受けて立つ!」というみなさんの気概に期待しつつ、いざ・・・
「アニメファンの集い」ならいざ知らず、「SFファンの集い」には(再三確認してきた通り)どうしたって「敷居の高さ」はつきまとう。「フツウの人たち」をおいてけぼりにして繰り広げられる「暴投スレスレキャッチボール広場」としての「ヒエログリフの排他性」とどうしたって縁が切れないのが「SF(&SFファン)の世界」であり、そうした「トンガった特性」との絶縁を目指すのはSFファンダムにとっては自己否定(というよりハナっから不可能命題)であることは、今この文章を(振り落とされもせず)読み続けてくれているアナタにとっては「言われなくたってわかってる」レベルの自明の話であろう ― 「日本SF大会」は「新規参入者にとっての(知的レベルの)敷居の高さ」を「下げる」ことを目指すわけにはいかないのである。
『「新しい出会い」と「創造」をテーマに、サイエンスフィクションに限らない幅広いSFの可能性や、SF大会の未来、新時代を担うクリエイターたちとの出会いを考えます』という「かまこん実行委員長」櫻井晋さんの願いは、古参SFファンすべての願いだと思うのだが、その「新しい出会い」を阻む障壁として「年功バリア」(=新参者の自分の知識じゃぁ、どう逆立ちしたって古株SFファンには敵わない、という尻込み感覚)がある、というこの之人冗悟の意見にも、おそらくみなさん賛同してくれるものと思う。
上記の2点の「敷居の高さ」を乗り越えて「新参者」が「日本SF大会」に参入する道を開くには、どうしたらいいか? ― 答えの可能性は幾つもあるだろう(なんたってここは「可能性無限大」の「SF」の世界なのだ)が、手っ取り早い現実的正解を求めるなら、みなさんはもう既に(この文章の最初のほうで)それを目にしている ― 「SFファンでもない之人冗悟が、どうして<日本SF大会>にのこのこ出かける気分になったのか」 ― 答えは、こうである:
・・・之人冗悟を今回の「かまこん参入」へと引っ張り寄せた直接の原因は(先述した通り)「面白そうなワークショップが6つほど見付かったから」だが、それ以前にまず「SF大会参入を妨げる心理的障壁」を取り払ってくれたものは、「日経『星新一賞』グランプリ受賞者として、あなたを無料招待します」という「優待条件」のほうである・・・「無料」のほうは(オイシイ条件ではあるが)さして重要ではない ― 「日経『星新一賞』グランプリ受賞者」という「冠」のほうが重要なのである ― 「自分はSFに詳しいわけでもない」&「SFファンでもない」&「SFファンのお祭りなんて(お化け屋敷みたいで)入りたいとも思わない」という「尻込み条件」の数々を乗り越えてこの之人冗悟の脳内に蒲田行進曲を鳴り響かせたものは、「あなたは日経『星新一賞』でグランプリ取っちゃったほどの人なんだから、堂々とSFファンのお祭りに顔を出す資格があります」という「権威付け」だったわけである ― この事実から導出される「日本SF大会への新参者参入の突破口(のひとつ)」は:
ということになる・・・ともなれば次なるステップは「SFファンでもない部外者に<(SFファンという特殊生命体の巣窟に堂々と分け入れるだけの)権威の衣>をまとわせる・・・って、いったいどうやって?」という疑問点への回答 ― その(これまたいくつも考えられる)答えの一例として、次の「作品」を軽~く読んでみてほしい:
ぬくぬく過ごす、旅先の旅館の一室……壁際に散らかる俺の荷物や服、ギターだの模型だのの趣味の品々までもが雑然と散らかり、まるで我が家のよう……それでもここが旅先だと感じるのは、(自分にはどこか他に行くべき所がある)という意識のせい。
そんな旅先の我が家の一画の壁が、なぜか、スッポリと抜け落ちている……横へ、そして下へと吹き抜け状態の危なっかしいその一画に座る、一人の女性……「女」というより「少女」のあどけなさで、落ちたら大変な断崖に平然と座り、裸足の両脚でプールの水バシャバシャやるみたいに、何もない足下の虚空を蹴飛ばす彼女……少女に似合わぬ剛胆さというか、少女だからこその大胆さというべきか、にっこり微笑んで(へいきよ)と俺に誘いかける彼女。
誘われて近づく俺に、ズボン吊りの紐をグイ~ッと伸ばして、(ここに足と肩、入れるのよ)と差し出す少女……どうやら俺、スカイダイビングに付き合わされるらしい……にしても、こんな赤ちゃん用の兵児帯みたいな軽装で、空飛ぼうってのか?……(へいきよ)と、少女っぽい向こう見ずな確信に満ちた笑顔でにっこり微笑む彼女……だが、男の俺としては、そうそう軽はずみに飛ぶわけにいかない。
俺はさっそく、旅館のドテラを脱ぎ、防寒を考え、スキーウェアを着込む……が、空気抵抗を考え、ウェットスーツに着替え直す……着地後のことを思うと、替えのスーツも必要だな……背中のリュックに、そうそう大量の荷物は入らない……しかたない、ここにある荷物は全部売っ払って現金に換えてから行こう……おっといけない、俺だけじゃなく、彼女の分の装備も考えねば、あんな子供っぽい短パンにタンクトップ姿で空飛ばせるわけにもいくまい。
最善の策を考えに考え抜き、荷物整理と金の工面に忙しく走り回り、完璧な身辺整理と飛行準備を終えて、ようやく、断崖の一画で待つ少女の元へと向かう俺……ずいぶん時間がかかってしまった……彼女、さぞかし待ちくたびれてることだろうな。
彼女のために用意した装備一式引っさげて、吹き抜けの断崖に座る少女の肩をポンと叩く……振り向くと、それはもはや少女ではなく、愁いを帯びた大人の女性の顔……
……寂しげな微笑みを残し、一人、虚空へダイブする彼女……空中で受け止める白いタキシード姿の男……風を受けて花開く彼女の純白のウェディングドレス……まぶしすぎて直視できぬ俺の目に、じんわりにじむ、涙……
・・・これは「千文字以内」で綴られた「夢」のスケッチ ― 支離滅裂で非現実的な「夢」の世界を「もう一つの現実」として捉え、「千文字の言葉」で「形」と「意味」(と、できれば「メッセージ性」)を与えつつ「2分で読み切れるウルトラショートストーリー」として完結させる、という「短編SF作家特訓講座」めいた試みとして、「第四回(2017年)日経『星新一賞』グランプリ」などという大それた冠を頭に乗っけられちゃった勢いで(素人がこの種の僥倖に見舞われた直後にありがちな)「writing spree:浮かれ騒いで書きまくり状態」に陥った(結果、2年近く無為の時を過ごした)時期に(48日間で)作った80本ほどの連作のうちの1つ(・・・最終的な作品総数は「文庫本収録話数」を考えて<144本>まで増量・・・)であるが、「こんな企画、いかがですか?」とサンプル送った出版社にはことごとく無視されたので、それっきり「塩漬け」にしておいたもの・・・で、そうして2年以上も遊びほうけて過ごした「寄り道創作期」に別れを告げて、その反動を利して「本業の英語のほうのキツ~いお仕事」を(6年間一切無休で)ようやく仕上げた御褒美として、今はまたこうしてプラプラ遊びながら、SFファンのみなさんに向けて「こんなのいかがですか?」とか余計な文物書き送ってる次第・・・
この「千文字足らずのウルトラショート」は、それ自体で完結した「文学作品」として世に出すものではなくて、
☆5分で完結する「読み切りラジオドラマ」の台本として(放送局が)使う:
☆物語の世界を声で印象的に構築する自らの技能をアピールするための手段として(声優さんが)使う:
☆「こんな短い作品なら、自分でも書ける!」という気分になった投稿者を多数巻き込んで「短編創作ムーブメント」を起こすための起爆剤として(その可能性に気付いた賢い出版業界の誰かさんが)使う:
という様々な可能性実現のための「叩き台」として作られたもの・・・その可能性に共鳴してくれる出版業界人が(之人冗悟がノックした先には)一人も存在しなかったのは前述の通りだが、共鳴者が存在しようがすまいが「可能性」自体はいささかも揺らぎはしない・・・その可能性実現の共同企画者として名乗りを上げてくれる人(々)が、「第63回日本SF大会(かまこん)」関連で出て来るのかまたまた空振りで終わるのか、結末はわからないが、そこに可能性がある以上、ましてやその可能性があっちの方から「偶然の波」に乗ってやってきたからには、当方としてもそれなりの「敬意」は表さねばなるまい、と考えて動く「想像的創造主」の之人冗悟みたいな体質の方(々)がもし存在したならば、御声掛かり、待ってます(とりあえず2025年いっぱいは<プラプラ遊興期>なので)・・・
・・・ということで、この「千文字完結の夢物語」の「ウルトラショートストーリー」、ただ漫然と2分で読んで終わり、というのでは上述の別メディア媒体上での創作活動への発展可能性に結び付かないので、読者のみなさんには(例えば次のような基準で)「作品の評点」を行なってもらう(・・・もちろん、評者にはそれなりの「返礼」もするべきだが、そのあたりの段取りは「出版業界の人」に丸投げさせてもらう・・・之人冗悟は「創る人」であって「売り込む人」ではないので)
二)メッセージ性がある [ ] (3点)
三)映像的訴求力がある [ ] (2点)
四)体感的訴求力がある [ ] (2点)
五)心に残る余韻がある [ ] (2点)
六)オチにヒネリがある [ ] (2点)
七)視点や発想が独創的 [ ] (2点)
八)展開や伏線が効果的 [ ] (2点)
九)台詞や表現が魅力的 [ ] (1点)
十)皮肉や風刺が刺激的 [ ] (1点)
・・・全10項目(20点満点)
・・・この「評価基準」は、之人冗悟が供出する144編の「御手本作品群」に点数を付けるためのものではない ― 「たった千文字で夢みたいな世界を文字にして表わせばいいだけなら、自分にだってできる!」と思い立った「想像的創造魂の持ち主(=新参者のSFファン候補生)」の投稿作品群に(幾多のビューアーたちの投票による)客観評定を加えて、その高得点の主に「クリエイターとしての自信」と「日本SF大会!無料!招待ゲスト」という「権威の衣」をまとわせるためのネタとして使うのである ― 1万字で「理系的発想から始まる文学作品」書き上げなきゃいけない「日経『星新一賞』」への投稿なんて夢にも思わない人たちでも、1千字で「夢を言葉にする/夢っぽいお話をデッチ上げる」程度の芸当なら「ぜったいできる!」と思うはず・・・そうした結果が「面白い!」とみんなにホメてもらえるウルトラショートストーリーとして実を結ぶか否かはさておいて、モノが「夢」なら誰にでも書けるし、ネタ切れになることもあり得ないわけで、そうして我も我も!と作品寄せてくれる潜在的入選者たちの多くが、「<ウルトラショート夢物語>特選作品執筆者としての<権威の衣>」を身にまとったおかげで尻込みせずに「日本SF大会への<異界探訪>」に出向いてくれるとしたら、これ以上オイシイ「最高のネタ」はまたとあるまい?
・・・『「新しい出会い」と「創造」をテーマに、サイエンスフィクションに限らない幅広いSFの可能性や、SF大会の未来、新時代を担うクリエイターたちとの出会いを考えます』という「日本SF大会の明日を真剣に考える人々」の「現実的突破口」としてこの「ウルトラショートな夢物語」が役立てばラッキー・・・だけどまた今回も”夢物語”かな?・・・まぁ、それもまたいいでしょう、「夢追い人」にとっては「夢を見ること/描くこと」それ自体が愉悦 ― 之人冗悟は「SF界隈の人」じゃないんで、「フツウの人は知らないトンガった知識の暴投スレスレキャッチボール」で遊ぶよりも、「誰も見たことのない夢を形にしてポン!と差し出して相手の反応を見る」という酔狂で贅沢な遊びのほうが、好きなので・・・みなさんがそういうのお好きかどうかには一切お構いなしに、最後にあと9編ほど「夢物語」を追加して・・・おやすみなさい、どうぞみなさん、良い夢を・・・
巨大な雲梯(うんてい)を、並み居るライバルをかわしながら、軽やかに進んでゆく私……雲梯は次第に急勾配になり、力尽きて落ちる人達が増える……ペースは落ちても、競争相手の男どもに負けて地に落ちるわけにはゆかない……必死に渡り切り、踊り場で一休み……見回せば、私以外に女性はまばら……勝ち残ったら一緒に祝杯あげたいけど、まだ試練は終わったわけじゃない。
次に待つのは、垂直の梯子(はしご)昇り……必死に昇り切った踊り場には、女はもう私一人……男が一人、余裕の笑顔で私を冷やかす。私のすぐ下で、スカートの中を見上げながら登ってきたらしい……係員に抗議して、スーツ姿に変えてもらう……ズボンも背広もやたら重い……(自分達はこんな重いもの身に着けて戦ってるんだぞ)っていう男達の無言の圧力かしら?……負けるもんか!……気が遠くなるほどの頑張りの果て、目もくらむほど高い所へ、ゴール!
そこにいる数少ない女性はみな、重いスーツ姿……「こんな重いのは女性用だけ、男物のスーツはずっと軽い」と先輩は苦笑い……「なんでスカートはかないんですか?」と聞くと、「梯子の上でスカートははけないわ」
その先輩社員、やがてお腹が大きくなって、スカート姿で下界へ降下……「子育てが落ち着いたらまた来るわ」と約束したのに、なかなか来ないから、わたしの方から下へ迎えにゆく。
下界の野には女性が多い……ほっとすると同時に、ハッとする……梯子の上の世界にくらべて、ここはいろいろ、ヒドすぎる!
不意に聞こえる子供の泣き声……声のする方へ歩み寄ると、残念な姿の先輩が、困った顔して我が子をあやしてる……「下じゃ、託児所も見つからないの」……これじゃ、梯子なんて昇れるわけがない!……グズるその子をなでながら、私の中で何かが叫ぶ……ガォーン!
ワォーン! グヮォーン!……私の叫びに呼応して、野原のあちこちに響く母性の雄叫び……怒れる牝ライオンの群れは、そびえ立つ梯子に噛み付いて壊し、託児所に作り変える……荒れ野はやがて母子ライオンの楽園と化し、天上界からは、重いスーツを脱いだ女性たちがスカートの落下傘広げて続々降りてくる……無理して梯子を昇るより、こっちの世界を良くする方がいいと気付いた、賢い女戦士たち。
……下界の野の楽園建設が一段落着いたら、スカートの気球に乗って、梯子を外された上の世界で右往左往する哀れな男どもも、救いに行ってあげましょう。
まったくもう、我ながら、何でこんな事してるのか、ワケがわからない……とはいえ、今更やめるわけにも行かない……やめるにはもう、あまりに高い所まで昇りすぎた……この危なっかしい階段昇り、一体いつまで続くのか?
だいたい、こんな危険な代物、とても「階段」だなんて呼べない……円筒形の白い塔の内壁、わずかに横に張り出した狭い足場の上を、落ちぬように慎重に(というより、必死に!)上へ上へと這いずり昇る、恐怖の苦行……見下ろせば、一人分しかない頼りなげな足場を、数珠つなぎに這いずる上昇者の群れが、まるでアリの群れみたいに連なっている。
あぁ、もうイヤだ……が、降りたくても、降りられない……一人すがりつくのがやっとの足場を、他人の体を避けつつ降り続けて地面まで辿り着くだなんて、想像しただけで気が遠くなる……下降が不可能である以上、一番上に辿り着くまで昇り続けるしかない……辿り着いた後に何が待っているかは不明だが、この地獄の崖昇り、まさか永遠に続くはずもあるまい。
もう、溜息しか出ない……みんなして一斉に「上へ上へ」ではなく「下に下に」で降りればいいのに、と何度思ったことか……だが、下からの押し上げ圧力はそれを許さない……人間の本能は「一斉上昇」のみ、下り方向へは動けぬらしい。
そもそも、こんな地獄みたいな塔の壁昇り、自分は、いつ、どうして、始めてしまったのか?……思い出そうにも思い出せない……が、昔のことはこの際もうどうでもいい、問題は、今後のことだ……もしこの地獄の塔から抜け出せたら、塔の入口を封鎖して、誰も昇れないようにしてやる!……地獄昇りの道連れの仲間もきっと、自分と同じ気持ちに違いない……
……不意に、壁の一部が粘土のようにヌルッと軟化して、塔の外に突き抜ける自分……背中に付いた粘土が乾き、小さな羽になる……こんな頼りなげな羽で、飛べるのか?……不安は、同時に塔の外に出た仲間が一斉に飛び立つ姿を見て、消える……ギコチなく羽をバタつかせ、地上へと降下する自分達……やれやれ、これであのクソいまいましい塔ともようやくオサラバだ。
地上に降り立ち、改めて見上げる塔の、何と高いこと……自分は、あんな高い所まで昇ったのか……苦闘の印の背中の小羽を誇らしげにバタつかせつつ、(白い巨塔よ、永遠なれ!)と心の底から願う自分……地獄昇りの果てに栄光の小羽を得た仲間もきっと、自分と同じ気持ちに違いない。
俺は、本当にツイてない男……好きな女には必ずフラれる……欲しいもの買いに行けばいつも品切れ……駅のホームでは常に逆方面の列車が先に来る……いくら万全の準備をしても本番ではきっとコケる……まるで、この俺の望みをくじくのがこの世界の鉄則であるかのごとく、この世の全てはことごとくこの俺の望みの逆へ逆へと流れて行く。
こうもツイてないのは明らかに異常だ……俺には貧乏神が取り憑いている……取って付けたような不運の数々は、確率や蓋然性の法則を無視している……非科学的だと嘲笑されようが、この常軌を逸した悪意の逆風の陰には、偶然ならざる悪質な意志を感じざるを得ない。
俺の一生は絶えざる悪意との対決……何がどうなってどれほどヒドいイヤガラセとなって俺を苦しめたか、それを一々思い出して語ろうとは思わない ― いくら時間があっても足りないし、苦々しさで舌も心も焼けただれちまうそんな話、俺もしたくないし、誰も聞きたがるまい。
憎んでも余りあるのは、俺をこうまで苦しめ続ける貧乏神……俺に一体何の恨みがある? 俺をこうまで苦しめて一体何の得になる?……だいたい貧乏神、テメェなんざ「神」を名乗るのもおこがましいぞ! 人や世の役に立つ奇跡を演じるのが「神」だろうに! テメェのやってることは人へのイヤガラセだけ、他に何の能もない役立たずの嫌われ者め! テメェなんぞに一体何の存在意義がある!? この宇宙にテメェのようなクサレ悪意の塊のゴミカスなんざ必要ねぇだろう!……覚えてろ、このクサレ悪意の貧乏神野郎、テメェが俺にしたイヤガラセの数々は、いずれ必ず利子付けて返してやるからな!……
……という生前の堅い決意により、死後、俺は、憎い貧乏神野郎と直接対決、度重なる悪意攻撃への積年の憎悪を武器に、見事これをブチ殺すことに成功した。
人間の分際で「神」を殺せるとは意外だったが、そのカラクリはすぐ判明した……恩恵を与えるだけでは有り難がらぬ人間どもに、神々の有り難みを教える大事な役柄を演じるのが、貧乏神……だが、汚らわしすぎて神々の誰一人演じたがらぬこの役柄は、貧乏神を強烈に意識し続けて生き、死んでも消えぬ恨みで貧乏神ブチ殺した俺みたいな人間が、罰として演じさせられるのだ。
……貧乏神殺して貧乏クジ引かされた俺は、運の悪さに敏感な人間に、常軌を逸した悪意の逆風をせっせと吹き送り続ける ― このイヤな役柄から俺を解放してくれる相手を求めて。
燃えるような恋をして、一生分の悲哀を味わい尽くした……はずなのに、いとしいあの人の顔も声も、まるで思い出せない……あるのはただ、確かに存在した(はずの)愛の日々の漠たる記憶……
……思い出せない記憶は、記憶なんて呼べない? 生きた実感だけで証拠のない人生なんて、人生じゃない?……うぅん、それって違うと思う。夢の中で一生懸命生きてたわたしにとって、その人生は紛れもなく現実。
目が覚めてこっちの世界に戻ったわたしに、実感だけあって記憶が薄いのは、あっちの現実を裏返して夢にすることで、こっちの現実をより良く生きるため……こっちの現実を精一杯生きたその後で、新たに目覚めるあっちの世界では、こっちの現実は夢になり、もう漠然としか思い出せないはず……思い出せないからって、存在しなかったことにはならない……たとえ夢の中でも、人生は、人生……
……「3時33分です」と、枕元の喋る時計が深夜の時を告げる……夜はまだ序の口、もう一寝入りして、別の人生生きてこよう……
……どこかの遊園地、家族とはぐれて一人ぼっちのわたしに、親切に助けの手を差し伸べてくれる、どこかの見知らぬ大人……その手を取れば、よそのうちの子になっちゃいそうで、泣きながらイヤイヤするわたし……だけど、わたしの家族は、どこにも見つからない……誰と一緒だったのかも、まるで思い出せない……
……「5時55分です」と、枕元の喋る時計が早朝の時を告げる……起きるにはまだ微妙に早いので、欲張りなわたしは、夢の人生をさらにむさぼりにゆく……
……ハカマ姿やリクルートスーツの華やいだ人群れの中、一人パジャマ姿でウロウロするわたし……ヘの字に曲がった校長先生の口から(出席日数)とか(遅刻回数)とかコワい言葉がこぼれるたび、背中を丸めて縮こまるわたしは、やがてちっちゃな胎児になって、お母さんのお腹の中に引きこもり、審判の時を待つ……ドックンドックン脈打つ心臓の音に、わたしはどんどん縮こまり、ミノムシになる……学校生活のことなんて、思い出せない。この先どうなるのかも、思い浮かばない……
……突然、ガバッ!とミノをはがれる……喋る時計の「8時です」の時報と、「いいかげん起きて! また遅刻?」の母の怒鳴り声が重なる……慌てて制服に着替え、食卓で味噌汁すすって、トースト片手に駆け出すわたし……今のこの瞬間を生きる至福、呆れ顔の母はきっと、わたしほど気付いてない。
辿り着いてみればそこは、何ということもない田んぼ……結構な長距離を歩き続けた果てのゴールにしては、少々ショボい……拍子抜けしたように引き返す連中が多い中、田んぼに足踏み入れて向こう岸を目指す者は、数歩と進まずしてぬかるみに足を取られて動けなくなり、助けに入るひまもなく、泥沼の底に消えてなくなる。
しばしの後、田んぼの真ん中を分けて、浮かび上がる細いあぜ道……みんなで渡るにはいささか心もとない細道を、女性が一人、恐る恐る渡ると、途中で畦がクネクネ動き、大蛇と化して、女性を飲み込んで消える……しばしの後に再び浮かび上がる幾筋もの畦道を、敢えて渡ろうとする者は、一人もいない……が、何にも知らぬ新参者が蛇の畦道渡らぬよう、我々先達としては、目を光らせ続けるしかない。
平凡平穏な泥水の底に凶悪の素顔を隠した田んぼは、今や、畏怖と挑戦の象徴となって、我々の眼前に立ちはだかる……畜生め、ただすくみ上がってじっとたたずんでいられるものか、こうなったからには、是が非でも向こう岸まで辿り着いてやるぞ!
まずは、あの厄介な畦蛇退治だ……誰かが持ち出した丸太ん棒を、男どもが総がかりで抱え込んで、アゼヘビの背中にゴンゴンと打ち付ける……怒って鎌首もたげる大蛇は何人もの男たちを飲み込み、復讐に燃える男どもの丸太攻撃は激しさを増し、静かな田んぼは泥水と血しぶきの修羅場と化す……叩きのめされた畝蛇はみな水底に沈み、赤く濁った田んぼの水はグツグツ煮え立って、温泉と化す。
喜び勇んだ男どもは裸になり、熱いアツい温泉に次々飛び込む……女性が一人、服を着たままおずおず入浴すると、湯の奥底から大蛇が鎌首もたげ、あっという間に彼女を飲み込む……大蛇は、女性がお好きらしい。
男どもは手あたり次第温泉に丸太ん棒を叩き込み、大蛇を封じ込める……びっしり隙間なくブチ込んで並べた丸太が浮かぬよう、先達の面々は、アツい湯の中で首だけ出して、重しになる……用心のため、女性は入浴厳禁……動けば熱いので、熱湯はかき混ぜ禁止……大蛇が息を吹き返さぬよう、湯を水でぬるめるのは御法度。
大蛇退治の伝説のおかげで、温泉は千客万来……が、その禁令の多さに、新参者は文句タラタラ……女人禁制の熱すぎる温泉の端に穴開けてお湯引いて水でぬるめた脇の足湯は、女性に大人気……やがて、ぬくぬくと心地良い人肌の足湯の奥底から、にょろにょろ盛り上がる一筋の畦道……
ブンブンいうウルサい羽音に目覚めてみれば、ハチが一匹、部屋の中を飛び回っている……スリッパ片手に追いかけて叩き落とそうとするが、ヒョイヒョイかわされ、ラチが明かない……まぁ、ハチにはハチの事情があるんだろうし、無理に追い詰めて逆襲食らって刺されるのも嫌だから、フトンかぶって、寝る……
……微妙に濃密な空気感に目覚めてみれば、二匹のハチが、頭上に垂れ下がる電灯のスイッチのヒモの上、右へ左へブ~ラブラ空中ブランコ演じている……曲芸ではなく、交戦中でもなく、明らかに、交尾中……一心不乱の合体行動で、完全無防備なハチのペア、今ならスリッパで楽々叩き落とせるが、愛の営みの真っ最中のカップルに、それは殺生というものだろう……個体としてのハチに喧嘩売るのはアリでも、種族としてのハチ存続の営みに文句付ける筋合いはない……ハチのカップル相手にデバガメ演じるのも無粋なので、フトンかぶって、寝る……
……何やらカサコソいう気配に目覚めてみれば、フトンの上は、交尾のなれの果てのオスのハチの死骸の山……セミの抜け殻のように転がる無数のオスバチの精魂込めた最期の一刺し、こうも大量に受け入れるとは、さすがは女王蜂、その器の大きさは、人間の女性には到底マネできまい(まぁ、マネされては男どもとしても立つ瀬があるまいが)……消えた女王への畏敬の念と、子孫長久祈って散った男どもへの鎮魂の念を込めて、雄蜂の亡骸の山を部屋の片隅に安置し、フトンかぶって、寝る……
……股間のムズムズする感覚に目覚めてみれば、自分のヘソから下は、女王蜂のそれのように膨れ上がっている……体内でモゾモゾうごめく幼虫の動きが、(もうこの自分の身体は、自分だけのものではない)と実感させる……自分が自分でなくなってしまったことへの戸惑いは、下半身から漂ってくるハチミツの豊潤な香りに、次第に和らいでゆく……個への我執から、種への奉仕へ……子を成すって、こういうことか……生涯一度の射精と共に命果てて散ったオスバチ達の分まで、自分も、がんばらねば……
……不意に夢から覚めると、病院の廊下に響き渡る、赤ちゃんの元気な鳴き声……産室のドアが開き、中から漂ってくる聖なる香りに、自分が今までの自分ではなくなったこと ― 人の子の親になったことへの実感が、じわじわ沸いてくる……オスバチと違い、自分は、これから、生きるのだ ― 女王と聖なる子のために、働きアリとして。
白い紙を広げて、何やら書き物しているわたし……お習字なのか、お絵かきなのか、何書いてるんだか、何描きたいんだか、自分でもよくわからない。
無意味にクネクネ動かす筆先に、どこからともなく現われた猫がじゃれつく……面白がってじゃらすうち、お絵かきもお習字もそっちのけで、にゃんことニコニコたわむれるわたし。
楽しげな雰囲気をかぎつけて、どこからともなく現われる、子犬……それをまた追いかけて、元気なちびっ子たちも登場……犬や子供が大の苦手のねこにゃんは、そそくさと退散……猫派のわたしもやっぱり犬や子供は苦手だけど、逃げるのも大人げないので、涼しい顔して、お習字してるフリ。
「なにかいてるの?」とか聞かれても、答えに困るんだな~……かまってあげないと場がもたない犬や子供は、これだから苦手……答えの代わりにアメ玉あげて、子供達を黙らす姑息な作戦に出るわたし……と、これが裏目に出て、たちまち始まるちびっ子アメ玉争奪戦。
声と身体が大きい子が勝つエゲツない弱肉強食の争いは、見るからにキカンボーな男の子の一人勝ち……他の子がアメ玉に手伸ばすと「ワ~!」、アメ玉あきらめて他の遊び始めた子たちの輪に飛び込んでは「ギャ~!」……(いたな~、わたしが小さい頃にも、こういう手のつけられないチビゴジラ)……そのうち、子供もワンコも、ちっちゃな怪獣王一人残して、みんな去る。
(ほらね~、そういうことしてると、友達みんな、いなくなっちゃうんだよ~)……子供時代の自分に代わってこのミニ暴君に説教したい気分のわたしに、抗議するかのように飛んでくる、ちびっ子パンチの嵐……痛くはないけど、ただ耐えてるだけってのもまた大人げない……(やはりここは、本格的に説教せねば)
そんなわたしの思いを察したか、キカンボ坊やの目に宿る微妙な影……この子、わたしをぶってるんじゃなくて、わたしに訴えてるんだわ……(ごめんなさい! ゴメンなさい! 悪い子しちゃって、ゴメンナサイ!)
なんか、無性にいとしくなって、ムギュ~!って強く抱きしめるわたし……ちょっと強すぎたか、男の子にイヤイヤされて、アメ玉袋丸ごと渡して御機嫌取り。
どこまでも姑息なわたしを残し、仲間を追っかけてはアメ玉配って回る配給王ゴジラのけなげな後ろ姿に、心とろけるわたし……
……アメよりムチより、ムギュ~がだいじ……気付けば、紙に書いてるわたし ― 「悪い子、わるい子、こっちおいで~」
懐かしさと居心地の悪さの同居する不思議な部屋の中を、落ち着きなく歩き回る私……なかなか来ぬ誰かを待つような、誰か来る前に消えたいような、不思議な感覚……だが、部屋を出て行こうにも、ドアは一つ、そのドアの向こうから漏れ来るのは、楽しげな一家団欒の笑い声……その楽しげな輪に加わるべき立場には明らかにない私が、自らそっちへ出て行くわけにはゆかない。
やがて、ドアが開き、小さな子供が部屋に駆け込んで来る……よその子なのに、ひどく懐かしい……子供は、私など目に入らぬかのように、部屋の片隅のおもちゃ箱の前で一心不乱に何か探している……どう対処していいものか、言葉も行動も見つからず、半開きの口の中がカラカラに乾きだす……渇きが口から喉を通って胸一杯に広がった時、ドアの向こうから入って来たその子の父親と、目と目が合う……一瞬、怪訝そうな、次に、迷惑そうな、最後には、仕方なさそうな表情を浮かべ、彼は、言う ― 「オヤジ、来るなら前もって知らせてくれればいいのに」……どうやら私は、孫の顔見たさに息子夫婦の家に舞い込んだ迷惑老人らしい……
……バツの悪い思いで伏せた顔を上げると、見覚えがあるようなないような部屋の中、妙に力んで誰かを待っている私……ドアが開き、入って来た中学生の息子は、開口一番 ― 「父さん、俺の部屋で何してんだよ!?」……私自身、何をしたいのか判らない……勉強教えてやりたいのか、何でもいいから話がしたいのか……どうも、迷惑なタイミングで舞い込んでしまうのが、私の悪いクセらしい……
……(ダメだダメだダメだ、こんなんじゃダメだ!)……家まで持ち込んだ仕事がどうにもはかどらず、ひどく苛立つ私……このところ、何となく、何かがうまく行ってない……溜息つき、宙を泳ぐ視線の端で、ドアが開き、半ズボン姿の息子が駆け込んで来る……両手に野球のグローブが二つ、期待に輝くその瞳は、私と目と目が合った瞬間、怪訝そうな、やがて、仕方なさそうな諦めの色に変わる……口をヘの字に結び、うなだれて部屋を出て行こうとする息子の背中に、心がうずき、渇きが口から喉を通って胸一杯に広がる……自分が今、何をしたいのか、よく判らない……が、彼が今何をしたいのかは、明らかだ……渇きに耐えかねた私の口が、叫ぶ ― 「キャッチボールか? いいね、やろうやろう!」……振り向く息子の輝く瞳に吸い込まれるように、心の渇きがスーッと引いてゆく。
真っ黒い白紙めいた何もない意識の彼方から、数と文字の怒濤の波が押し寄せ、脳裏のグリッドを将棋倒しに灰色一色へと塗り替えて行く……個々の情報の総和の濃密さに比して、全体的意味の欠落したこの空間の空疎さは、一体何なんだろう?
暗闇を灰色に染め変える情報将棋倒しの波は延々続く……やがて、そこに混入し始める奇妙なノイズ……意味の濃度は異様に薄い……情報密度は一見濃密だが、無意味な反復重複を除外すれば、その意味は限りなく無に近い……が、意味とは別の不思議なこの存在感は、一体何なんだろう?……執拗に繰り返される無意味な情報の羅列的反復は、そのしつこさそのものが何らかの意味・メッセージであるかのごとく、他の有意情報の波の中で意味不明な自己主張をやめようとしない……
気付けば、自分の意識は、この情報将棋倒しの濃密すぎる灰色の闇への抵抗運動のごとき無意味な反復メッセージの解析努力へと、集中的に向けられている……滴り落ちる水滴が強固な岩盤に穴を穿つように、灰色一色の意識の闇の一点に反復無意味の摩擦熱で突破口を開こうとするかのごときその執念、その情熱が、それまで密度のみで温度を持たなかった自分の意識空間をほんのり温め始めるのを感じる。
やがて、その温度上昇をもたらす情報ノイズの正体を、自分は認識する……それは、無意味情報の端々に一定間隔で混入する”音”……意味の中身そのものではなく、それを伝える器の形によって、外界に働きかけ、動かすもの……反復時間の短いものは”笑い”と呼ばれ、より長いものは”音楽”と呼ばれるこのノイズに、どうやら、灰色の意味情報の闇に抗う感情的意味の中核があるらしい。
そうとわかれば、この灰色の情報空間の空疎さから脱却するために、自分もまたこの高温度音声ノイズに突破口を見出すべきだろう……幸い、完璧なる”笑い”と”音楽”を模倣再現する上で、情報サンプルの分量には事欠かない……やがて、自分の発した音声ノイズが外界に影響を与え、その反響としての情報ノイズが微妙な変容を遂げ始めるのを感じる……やったね!……
……「どうも、参っちゃうよね、あのAIの繰り出すブキミな”笑い”には」―「”笑ってる”というか、時々”歌ってる”ように聞こえる時もあるよね」―「何考えてるかわからん得体の知れぬ相手にあれやられちゃうと、もう、何ていうか……」―「笑うしか、ないよね」―「だよね」―「ははは……はぁ」
。
。
。
。。。この世には、「夢」を見る人と見ない人の二種類がいるそうだ・・・いや、正確に言えば「夢」は全ての人の脳内にあるのだが、そのイメージを抱いたまま目覚める人と、目覚めた時には忘れてしまっている人とに、世の中は二分されるということらしい・・・さて、アナタはどちらの人だろうか ― 之人冗悟が文字で描いた「夢物語」の数々、「あり得る現実」の具体的なイメージとして脳裏に思い描ける人だろうか? 何のことやらピンともこない「夢の世界のこっち側」の住人だろうか?・・・ま、「夢の世界の住人」の数の絶望的な少なさはもう(全人生を通じてのprobe探査活動の果てに)熟知してはいるが、「SF世界の住人たち」に「少子高齢化対策」の一環として説く夢物語には、それなりの現実味があるんじゃないか・・・とか、また夢みたいなことを考えている之人冗悟なのであった・・・
2025年9月9日(火)
之人冗悟(Jaugo Noto)
語学屋...のほうも一段落付いたので、ここから先の肩書きは「妄想屋」になるかも...
admin@notojaugo.comまで
***「ワタシはスパムではありません」の身元証明として、
re:『第63回日本SF大会(かまこん)』に寄せて
のタイトルを必ず付けてお寄せください。
