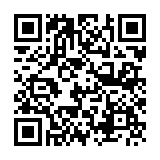
福島への旅も三度目ともなると、今のこの地の抱える問題点があれこれハッキリ見えてくる ― 東日本大震災からの「復興」と言えば(太平洋岸の)「浜通り」の「原発事故の無残な破壊の跡からの復興」ばかりが話題に上る福島県であるが、(内陸の)「中通り」と(西端の)「会津」に関しては「震災の直接的被害としての物理的損壊」は(浜通りほどには)深刻でないものの、「原発事故で汚染された<フクシマ>」という(現実とはかなり異なる)マイナスイメージによる風評被害が根強く尾を引いたまま、その後のコロナショックも加わって、福島県外から訪れる人々の客足はかなり鈍い印象であり、そのダメージ払拭のための施策も(旅人としての自分の目には)まるで見えない感じだった。物的ダメージよりも心的イメージダウンが大問題の「中通り」や「会津」にとって、必要なのは「復興」ではなく「新生」だったはずである・・・が、そうした「新たな芽吹き」の気配は、今回の旅からは(一部の街を除いて)まるで感じられなかった・・・はっきり言って、今のままの「飯坂温泉」・「会津若松」・「猪苗代」といった観光地では、そのあまりの寂れぶりに、県外からの訪問者の多くは再び訪れようという気にはならないだろうし、その一度きりの訪問で自分が抱いた「寂れたフクシマ」のイメージをネットを通じて拡散して世間に根深く定着させることで外来訪問者の減少にまた拍車を掛けるという悪循環が、終わらない ― 終わらせるには、新たな形で生まれ変わり、その新生イメージで「原発事故に沈んだフクシマ」のマイナスイメージを塗り替えるしかない・・・のだが、今の福島は、新たな何かを生み出すための「産みの苦しみ」には挑まずに、終わりの見えない「引き潮の憂鬱」にただ漫然と耐えている・・・ようにしか(旅人である自分の目には)映らない。福島県人はなまじ辛抱強いばかりに、本来なら決然と立ち向かい打ち破るべき「逆境」に対してもただひたすら耐え忍ぶばかり、その淀んだ空気の行き着く先に何が待っているのかは想像するのも辛いから、先々のことはあまり考えず、今はひたすら我慢するだけという「終末病棟のような淀んだ空気感」に満ちている・・・冷淡な言い方だが、それが「福島の今」を肌身で体感するために彼の地を四ヶ月間に三度訪れた「福島びいきの東京者」の客観的な見立てである・・・
・・・が、しかし、淀んでいるのは「街の空気」であって、「街行く人々の心」は「淀み」からはほど遠い「人としての温もり」に満ちている ― この点、「街」は盛っていても「人心」は狂って腐って淀みきっている東京あたりの「neo-Sodom(ネオ・ソドム:現代の神呪都市=神に呪われし悪徳の都)」とは別格の風土が「会津・福島」にはある ― それは「バブル景気とその崩壊を境にして道義も魂も腐り果てたケッタクソわりぃ東京」に対するこの筆者(之人冗悟:のと・じゃうご)の「60年来の江戸っ子としての憤激」の反動的感傷としての「福島へのえこひいき」ではない ― 街に活気はないけれど、民の心は死んではいない ― それを体感させてくれるような会津若松での感動体験を書き残すことが今回の旅行記の主たる目的と言ってもよいくらいである。
最初から全部開いて「本」の体裁で読みたい人は、すぐ下の「Open Book(見開きモード)」のボタンを、「本文」を閉じて「見出し」だけに戻したければ「Index(見出しモード)」のボタンを押してもらえばよい。
.
「旅」の情趣のかけらもない単なる「移動」のこうした行程は(「仮眠」の有り難みがマックスに達する帰路以外では)自分の好むところではない・・・のだが、「車窓の外を流れる春の景色鑑賞会」としての「鈍行列車ノロノロ旅」は前回(4/19,20)既に体験済みなので、今回は敢えて往路に「高速バス」を選んでその「旅の情趣のなさ」を確認してみただけ・・・案の定、ひたすら寝ぼけた「移動」ではあったが、午前6時に家を出て4本の列車を乗り継いで午後2時半に会津若松に到着するよりはよっぽど楽に(&安上がりに)午前8時にバスに乗って正午ちょい過ぎには現地に到着するのだから、まぁ、大方の旅行者は「鉄道旅」なんて選ばないだろう ― それが「目的地」以外の「通過点」として切り捨てられてしまうマイナーな観光スポットにとっての大問題なわけで、そうした「ローカル鉄道沿線のマイナーな閑古鳥観光地」の再生には、「ローカル鉄道での旅そのものの魅力」の創出が必要不可欠となる・・・わけであるが、そっちの方策については別途企画『train-tri-view(車窓三景)』でたっぷり語ってあるので、ここでは触れない。
それにしても、暑いアツい・・・「福島は涼しい」という子供時代のイメージは前々回の「飯坂温泉・福島駅前・郡山駅前」への訪問(3/10,11,12)でかなり変わってしまったが、「会津は寒くて雪だらけ」というイメージもまた自分の中で書き換えねばなるまい ― 「会津は盆地だから、冬は寒いし、夏も暑い」・・・で、人はあんまりいない、と ― 道行く人にほとんど出会わないのは、早くも訪れたこの猛暑のせいではない・・・そのことは、前回の春の旅(4/19,20)で既にもう体感済みなのだ・・・
会津若松では最も古い歴史を誇るこの「大町通り」は、豊臣秀吉による天下統一が成ったばかりの安土桃山時代から続く商業区画、当時の街並みは幕末の大火と戊辰戦争で失われているから、今なお残る古式ゆかしき店構えは明治維新以降のものである・・・が、それでもなお十分古い ― その古めかしさは、「徳川の北の砦」としての會津松平の由緒、「ラスト・サムライ・タウン」の雰囲気を感じさせるに十分な趣を漂わせている・・・のだが、いかんせん、そうした古い街並みのほとんどが、「江戸~明治の香り」を漂わせつつ、あらかた店仕舞いして、ひっそりと寂しい眠りに就いている。
もっとも、街並み自体が古めかしいので、大方の店は畳まれていても、「テナント募集中」の空きスペースだらけの「神明通り」みたいな「シャッター商店街」の寒々しい印象からは遠いのが唯一の救い・・・だが、見方によってはこれは「救い」ではなく「呪い」とも言える。
現地の人達から聞いた話を総合すると、この「大町通り」には古くからの住人による「持ち家」が多いので、「テナント料」支払いの経済的負担がなく、たとえ儲からない店でも細々と営業は続けられる・・・が、そうした昔ながらのお店のほとんどは先代の老店主が亡くなるともう次の代には商売に見切りを付けて店を畳んでしまう・・・が、商売はやめても居住をやめるわけではないから、商家が民家に姿を変えて、地元の人々の暮らしは続いて行く・・・古い商店が店を畳んでも、そこに新たな店が入ることはない ― テナント(住人)は既にそこにいて、商人ではない住民としての暮らしを続けているのだから、そこに「商店街」としての新陳代謝(=古いテナントが去り、新たなテナントが入るというサイクル)は成立しない・・・そうした構図の中から生じたのが、「会津で最も古く、最も寂れた、もはや商店街として成立していないかつての商業区画」としての今の「大町通り」、それが延々1キロ、徒歩で15分もの長きに渡って、半ば眠ったかのような姿で伸びている・・・「会津若松の寂しい玄関口」として、訪れた旅人をそら寒い思いにさせているわけである。
そんな「会津の顔」の残念な姿に(前回4/19,20の「鶴ヶ城の花見」の際に)触れて、この1キロもの長くてまっすぐな「かつての花形商店街」に活気を取り戻すための方策を考えて、それを紹介するための<会津若松《復興》四案>と銘打ったビラを現地の人に可能な限り多く配って見てもらうこと ― それが今回の「会津若松再訪」の主たる目的である・・・が、相手かまわぬ無差別ビラ配りには何の効果もないことは既にもう「311飯坂温泉郷探訪」で実証済みである・・・そこで今回は、会津若松という街の活性化に主体的に取り組んでいる(と思われる)人々にターゲットを絞って<会津若松《復興》四案>のビラを配り、その復興計画案実施の過程で当方の「英語教材無料提供」という例の宣伝キャンペーンを(も)展開しようという目論見である ― そのために白羽の矢を立てた相手が、「アネッサクラブ」という「大町通り」を中心に結成されたという女性たちの集団であり、その概要については以下の通りである:
この文面から読み解く限り、「大町通り」の街並みが(店仕舞いだらけとはいえ)今なお「昔ながらの城下町の風情」を残しているのは、この「あねさまたち」による「大町通り近代化計画への反対運動」のおかげによるものらしい・・・ということで、当該サイトにある『あねさまたちの散歩道』なる街路図を頼りに1キロあまりの道のり(片道15分)をくまなく往復してビラを渡す相手を探して歩いた・・・のであるが、開いている店はあまりなく、大町通りや会津若松の活性化について話し合えそうな「あねさま」にはついぞ巡り会えずじまい。お店に入って首尾良く話ができた女性たちは三人ばかりいたが、いずれも「店主のあねさま」ではない雇われ要員ということで、肝心のビラは受け取ってもらえなかったり上の方まで届きそうにもないままとりあえず置いてきただけ、という有様・・・
そもそもこの旅に出る前の段階で既にもう以下の団体には(ネット経由で)当方の「会津若松復興案」の案内は送信している・・・というか、送信を試みてはいる・・・が、いずれも残念な結果に終わっている:
●『大町通り活性化協議会』・・・メッセージを送信しようとしても「internal server error(=あちら側の受信機能不全)」でラチがあかない
●『SHARE BASE Aizu』・・・メッセージ入力欄には「改行コード自動削除」という禁断の命令が組み込まれていてマトモに読める文章のやりとりができないので、送信断念
●『神明通り商店街』・・・メッセージは送ったが、音沙汰無し(・・・この点に関しては「アネッサクラブ」代表者へのメール送信も全く同じくナシのツブテ)
・・・ということで、今回もやはりまた「福島復興のお手伝いをしたい東京者の熱意」を福島県人に伝える試みは、100%ムダに終わった ― QRコード付きで「是非ぜひ見てみて!」と訴えた<会津若松《復興》四案>へのWEBアクセスは(「飯坂温泉」に続いて)今回も完全にゼロ・・・今回の会津若松再訪の主目的たる「会津若松の人達にこの眠れる街を活性化するためのアイディアを見てもらう」という当方の目論見も、このまま頓挫ということになりそうである・・・どうやら、この之人冗悟(のと・じゃうご)と福島県の間には、こちらで勝手に思っているほどの「縁」も「運」も、ないのかもしれないな・・・
・・・そもそも、「大町通り」の再活性化のためには「商人をやめた(たぶん、大方は年老いた)古いテナントさんたち」を「会津若松に新たな活気を取り戻す気概に満ちた新たなテナントさんたち」に入れ替える必要があるわけだが、それを行なうには「商人をやめてしまった古い大町通りの住人たち」に「大町通りからの転居」か「新たな住人たちを<間借り人(テナント)>として受け入れた上での建設的同居」のいずれかの道を歩んでもらう必要があるわけである・・・が、会津若松の人々の極めて保守的な精神傾向を思えばいずれも現実的には難しかろうから、「<商店街>としての大町通りの再活性化」は(地元大町通りの<非商人系住人たち>からの抵抗圧力によって)不可能命題(mission impossible)に終わる、というのが論理的必然の構図・・・
・・・このimpasse(出口なき袋小路)の打開には、大町通りの(肉体的にも精神的にも)<古い住人たち>の「(自己犠牲的胆力を発揮した上での)會津を愛する心意気」に訴えかけるよりほかはない ― 「会津若松の街の玄関口の<大町通り>を、現状のごとき<仮死状態>のままにしておいて、本当にいいのか? 自分たちがとりあえず老後をこの街で静かに過ごせさえすれば、会津若松の街全体がこのまま<slow death(静かな死)>へとズルズル沈み込んでしまってもかまわないというのか? 会津の城下町全体の浮沈を賭けて<會津の顔の大町通りを商店街として再生しようとする新たな人たち>との建設的共存へと重い腰を上げるには、もう、自分たちは年老いすぎてそんな元気はないからどうかこのまま放っておいてくれ、と言うつもりなのか? <古い大町通り>を道連れにあの世へ旅立つまで、自分たちの<静かな暮らし>には誰にも手を付けさせないつもりなのか?」 ― 冷淡な言い方だが、結局、大町通りの生き死には、古くからの住人たちの気持ちが「もう疲れたから、<古い大町通りの死>を冥土の土産にあの世へ旅立つ」つもりなのか、それとも「老体に鞭打って実現した<新たな大町通り>の明るい姿を手土産に冥途の御先祖様たちに堂々と逢いに行く」道を選ぶのか、その二者択一の選択次第なのである・・・
・・・地元の住人のその選択に、自分のような部外者があぁだこぅだと口出しすれば、「放っておいてくれ!」と心を閉ざす方向への否定的作用しか生まないのは火を見るより明らかなので、自分にできることはただ一つ ― 「地元住民の心が建設的方向へと向かうに十分魅力的な<新たな大町通り/会津若松/福島県の設計図>」を描いて見せるだけ・・・だが、それもそもそもWEBサイトを開いてその中身を見てもらう段階にすら行き着かないというのでは、何一つ始まらない・・・まぁ、「結局、会津若松とは何のご縁もなかった」ということに終わる公算大のようだが、「当方、ノックだけはしましたから」という既成事実だけは残したということで、この件はもうそれでよいだろう・・・
・・・ということで、明日からの二日間は「会津若松の開かぬ心の扉へのノック」はやめて、「五色沼トレッキング」と「大内宿探訪」という純然たる「福島観光」に費やすことにしよう・・・
今回の会津若松での宿に自分がこの「ゲストハウス なかやすみ」を選んだ理由は以下の通り:
(1)宿泊料金が安かったから
(2)外国人旅行客からの「スタッフが完璧な英語を話す宿」という口コミを見たから
(3)「神明通り」・「野口英世青春通り」・「七日町通り」のいずれに足を伸ばすにも好適な立地だから
(4)自分が思い描いている「超簡易素泊まり宿泊施設(shelter-inn)」の現実的問題点確認のため、見知らぬ旅人(最大四人)が同じ部屋の別々のベッドに寝泊まりするという(軍隊生活や大学生のルームシェアっぽい)宿泊スタイルを実体験したかったから
・・・福島県への貢献のために「英単語習得用WEB自学自習教材」を無料で(一年間)福島県人に使ってもらう、という形での同教材のプロモーションを考えている自分としては、「会津若松で外国人旅行客を相手に英語で自然な応対ができるお宿のスタッフさん(=パン屋のオーナーの女性)」は、自前英語教材を会津若松の人々にアピールする取っ掛かりとしては理想的、と考えたわけである。外国からの旅行客が会津若松にどの程度の「インバウンド景気」をもたらしているか、そうした外国人が会津若松の何に魅力を感じているか、といった情報も聞かせてもらえればなおありがたい・・・ということで、宿の予約と同時に当方のそうした来意を記した自己紹介文を(オーナー女性の七日町のパンのお店をお手伝いしてたりする幼い娘さんたち用に例の英単語暗記用教材の無料アクセス権まで付けて)七日町駅前のパン屋さんのほうのメールアドレス宛てに送っておいた・・・のだが、宿泊前日になってもメールへの返事も英単語教材へのアクセスもない・・・ということは「宿泊は歓迎しますが、そちら様のプロモーション活動への関与は御遠慮します」という意思表示であろう ― 当方としては残念だが、まぁ「2人の児童の保護者&開店ホヤホヤの店&宿のオーナー」としては十分理解できる慎重さであるから、先方の意思を尊重して、今回は「英語」関係でのプッシュは差し控えることとしよう。
前回の訪問で既にもう「勝手知ったる他人の庭先」みたいな感じになっている「神明通り」の横丁にある宿なので、場所はすぐにわかった。そのゲストハウスの一階の「mini basket」のパン売り場を兼ねたフロアに入ると、宿の先客とおぼしき年配男性が一人、フロアの端のテーブルで所在なげに時間つぶしをしている。カウンター前のテーブル上に置かれたパンの品揃えはさほど多くない ― 「ゲストハウス」のお客さんの腹ごしらえ用に「七日町の本店の出店」といった感じで用意されている感じらしいが、自分がチェックインの手続きをしている間にも親子連れのお客さんが来店していたから、お店の少ないこの界隈では重宝されているパン屋さんのようである。
ゲストハウス&パン屋さんのオーナーは小柄で物静かな女性で、(「英語」関係をわざと避けての)当たり障りのない世間話で聞き出した情報によれば、彼女のお母さんはフィリピンから(芸能ビザで)来日した際に(猪苗代出身の)お父さんと知り合って結婚、会津若松に移ってまず出したお店は「Asian Blue」という居酒屋、その後、近所に「中庭」という(ファミリー・グループ向け)ゲストハウスを開き、自分が今回お世話になる「なかやすみ」と「mini basket」は昨年(2024年)冬にオープンしたばかり、お宿のいずれにも「なか」が付くのは、「中町」近くにあるからではなくて、オーナーの名字が「中村」だから、だそうである。当日のお宿(二階)の宿泊客はキャパシティ上限の4人、そのうち1人が外国からのお客さんらしい。
・・・ということで、一階でパンを2種類買ってから二階のゲストルームへ。ドアを開けて中を覗くと、2つある二段ベッド(合計4つ)のうち3つにはもう先客がいる様子。入口近くの二段ベッドの上が空いているので、これから二日間の就眠先はここになるようだ。梯子を登って入り込んだベッドは、上体を起こした状態で座っても頭上には十分なスペースがある。他のお客さんとの仕切りは厚手のカーテンのみなので、隣りのベッドの上段に寝転んで本を読んでいる(メガネ&ヒゲ付きの)外国人男性の立てる物音もカーテン越しに伝わってくる・・・特段の防音措置も施していないこの環境だと、入浴・就眠・外出のためにベッドの上でガサゴソ音を立てて身支度を整えるのもいささかためらわれる感じ・・・ま、ここにはただひたすら「寝る」ためだけに入り、物音はなるべく立てずにおくことにしよう。
・・・てな感じで、いつもなら宿へのチェックイン直後に部屋で行なう「荷ほどき」の儀式もせず、さほど重くない(5キロそこそこの)バックパックをそのまま背負って一階のフロアに降りて、着脱にもけっこう難儀する登山用のトレイルシューズを再び履いて外出準備。靴置き場にはピンク色した女性用シューズも置かれているので、彼女は三階の「貸し切り部屋」にでも宿泊しているのだろう。さっきまで一階の隅っこで時間つぶししていた年配の男性客の姿は見えないから、どうやらもう街へと夕食に繰り出したらしい。自分も、オーナー女性に(彼女のママさんがやっているフィリピン料理のお店)「Asian Blue」への道順を聞いて、夕方(5時台)の街へと繰り出した。
・・・正直言うと、自分は「パン」も「熱帯系料理」もあまり好みではない(というか、ハッキリ言っちゃうと苦手である)が、何の因果かこうして旅先でお世話になる巡り合わせになったお宿関連のお店が三つ、会津若松に待ち構えているのだから、四の五の言わずに足を運ぶのが筋というものであろう ― なんたって、この「神明通り」界隈には開いているお店自体、悲しくなるほど少ないのだから・・・そうして、教えられたルートを辿って日の陰った「神明通り」のアーケードを歩いていると、先ほど「mini basket」でパンを買っていたお母さんと坊やがあっちから歩いて来るのが目に入ったので、ごく自然な感じで「こんにちは」と挨拶を交わす ― お店も人も多くない(がゆえに、とっても大事)というのが会津若松(というか、福島県全般)の特性であり、この希少性ゆえの貴重性は、ゴミゴミとした東京暮らしの自分にとっては新鮮で好もしい限りなのだが、それはまた「商売が成り立たない客足の乏しさ」でもあるわけで、改めてこうして「テナント募集中」だらけの「神明通り」のアーケードを歩くと、(このままじゃぁこの街、本当にゴーストタウンになっちゃうな)という寒々しい感覚になってくる・・・だからこそ、「助けが要るものを、見て見ぬ振りはするな」という私的信条(<誠賢十箇条>その四)に従って<会津若松《復興》四案>をまとめて『神明通り商店街』の事務局のほうに意見具申してみた自分だったのだが・・・どうやら「どこの馬の骨とも知れぬよそものの意見なんて、お呼びじゃない」ということらしい・・・もし自分がこの街に少しでも関わりのある会津っぽなら、どこの誰から舞い込んできた話だろうが、とにもかくにも「御意見拝聴」のオープンな態度は今のこの死にかかった街にとっては<!ABSOLUTE MUST!(絶対必要)>だと感じるだろうに・・・この塩っ辛さもまた「会津っぽの頑固さ」というものなのかなぁ?・・・だとしたら、こりゃ大問題だわなぁ(・・・<誠賢十箇条>その八)故ある意地は張り通せ。故なき意地は張り倒せ・・・)・・・ま、こういうのはすべからく「縁」と「運」なので、「ご縁(運)がなくて残念でした、会津さん」ってことになったとしても、それはそれで淡々と受け止めるしかないんだけど・・・
・・・途中、そこそこ道に迷いながら「Asian Blue」のお店に到着、「なかやすみ」オーナー女性のお母さん(いかにも「フィリピンのママ」って感じの陽気そうな女性)に「脂っこい食べ物・鶏肉・豚肉が苦手」というメンドくさい当方の体質を説明して出してもらった「エビの入った野菜炒め」を肴にビール・カクテル系の飲み物でお腹を満たしつつ、(昔の巨人軍の盗塁王の柴田勲に似た風貌の)パパさんと当たり障りのない世間話をしてから、午後8時頃に店を出る。
・・・この後は、前回(4/19)には訪れなかった新しい居酒屋さんを探して入るつもり・・・で街をグルグル(例によって道に迷いつつ)回る道すがら、駐車場の壁一面に(学校の板書みたいな感じで)書き出されている文言を発見 ― 『青年賦』と題されたその内容をかいつまんで書けば「One is as old as one thinks and feels, not as old as one’s age.:人が老いるのは年齢を重ねたからではない。若々しく柔軟な考え方・感じ方ができなくなった時、人は老人となるのだ」というもの ― 三十路を越えて以降もう齢を数える(&取る)のをずっと忘れたまま今に至っているこの之人冗悟(Jaugo Noto)にとっては、「今さら言われるまでもない自明の理(truism)」ではあるが、およそ「若々しい柔軟性(=先入観抜きに新たな何かと向き合う子供のような心持ち)」に欠ける会津の人々の精神傾向を思い知らされる旅の途中でこういう文言に出くわすと、苦笑混じりに相槌打ちたい気分になる。その『青年賦』の書かれた壁の向こうには喫茶店があって、いかにも古めかしい構えの店頭に出ている看板には「(午後)10:30まで営業」と書いてある・・・ので、とかく長っ尻でお喋りしたがる自分にとってはヨダレが出そうなその文言(『青年賦』じゃなくて10:30のほう)に誘われて、ギィ~ッって感じで開く扉を押し開けて「まだ、やってますか~?」と声をかけながら中に入ってみた。お店の名前は『風街亭(かぜまちてい)』 ― 名前も店内の雰囲気もいかにも古めかしい感じで、平成~令和の若い人たちはこういうレトロな雰囲気に触れると反射的に「昭和だぁ~!」とかの概括的感嘆文を口にするが、同じ昭和にもそれなりの年代差はあって、昭和50年代半ば~終わりの4年間を早稲田通り・高田馬場・池袋界隈で過ごした自分の感想としては「昭和、昭和と言ってもいささか広~ぉござんす・・・この店の雰囲気はさしづめ<昭和40年代っぽい>ってとこでやんすな」って感じ。入店した時に出迎えてくれたのは妙齢のあねさまだったが、「酔い覚ましに、とびきり濃い~ぃホットコーヒーもらえますか?」の注文に応えるべく店の奥から出てきてくれたのは、今は亡き「ムツゴロウ」こと畑正憲(はたまさのり)によく似た感じのメガネをかけた優しそうなマスター ― 後日ネットで調べたところ、この『風街亭』は夜にはジャズやブルースのライブ演奏が開かれることも多いお店らしい・・・のだが、この夜のこのお店にはお客さんは自分だけ・・・というラッキーなシチュエーションを利して、会津若松の街に関するあれやこれやのお話を聞かせてもらいつつ、調子に乗って、ここまで配り所のなかった例の<会津若松《復興》四案>のビラ取り出してはその内容をベラベラと力説したり、先日の猪苗代湖周回サイクリング(頓挫)紀行の話をしちゃったり、とまぁ言いたい放題聞きたい放題 ― こういうヘンテコなお客の相手もニコニコしながら務めにゃぁならんのだから、喫茶店のマスターってのはつくづく大変で立派な人種だと思う(・・・っつうか、その前に我が身の図々しさを反省すべきか?)
その『風街亭』のマスターからあれこれ聞かせてもらった会津若松に関するお話のうち、特に印象に残った話をかいつまんで記しておこう:
●かつて<大町通り>では、地元会津にゆかりのあるミュージシャンを中心とする街角ライブを交えた集客キャンペーンをしたことがあった・・・のだけれど、「あんまりたくさんのお客さんが押し寄せると、お店のほうで注文をさばききれない」という意見が地元から出たりして、結局その数年後にはその音楽イベントでの集客作戦は立ち消えになってしまった。
●<神明通り>でもあれこれいろんなキャンペーンを打って集客努力はしているのだけれど、正直、うまく行っていないというか、そもそもどういう客層を狙ってどういう構想でやっているのか、首をかしげることがある。
●会津若松の中でも<野口英世青春通り>が(<大町通り>や<神明通り>と違って)垢抜けた雰囲気になっているのは、最近会津若松商工会議所の会頭になった渋川さんという人の尽力によるもの。「七日町通り」の方もまたこの渋川さんの肝煎りで街の再開発が進み、メディアへの積極的露出戦略のおかげもあって、今では会津若松で一番栄えた街になっている。
・・・その「七日町通り」は、今日の午後の訪問予定が明日以降にズレ込むことになった場所だが、旅の前にネットで調べたお店の数の多さでも<大町通り>や<神明通り>を圧倒している感じで、「只見線の<七日町>って・・・会津若松の中心からはだいぶ外れてるようなんだけど・・・何か特別な事情や魅力でもあるのかな?」と不思議に思っていたところだっただけに、このマスターの話に出て来る「会津若松商工会議所のヘッドを務める渋川さん」という人には俄然興味が沸いてきた・・・どこをどう突っついても誰にも見てもらえなかった<会津若松《復興》四案>だったが、最後に(あと二つ三つほどある脳内企画案も洗いざらいWEB上にアップロードした上で)その「会津の街興しに実際成功している(唯一の?)人物」である「渋川恵男(しぶかわともお)氏宛て」に御案内差し上げることで「締め」(or諦め?)とすることにしよう・・・
・・・とりあえず、ムツゴロウに似た風貌の『風街亭』のマスター、貴重なお話いろいろ聞かせてくれて(&こっちのしょーもない話にもニコニコ笑顔で付き合ってくれて)ありがとうございました・・・またお邪魔することがあったら、今度は昼間、自慢の料理に舌鼓打たせていただきたいと思います(・・・また会津に来ることがあれば、だけど・・・)
・・・こういう『風街亭』みたいな趣のある喫茶店とか、前回お世話になった(&明日の夜もお邪魔するつもりの)『十六夜(いざよい)』みたいな居心地の良い居酒屋とか、こういうお店がある街に旅するなら、宿泊先は「ただ寝るだけ」で「食事なし」の素泊まり宿がいい ― なまじお宿で「お食事」にありついてしまうと、夜の街に繰り出して地元の名物料理や旨いお酒や楽しいお話にありつける機会が奪われてしまうのだから・・・だが、今の寂れた会津若松では、そういう「素泊まり宿」と「飲食店」のおいしいコラボが成立し難い感じになってしまっているのが実に惜しい。会津若松のメインの国道118/121号線沿いの「神明通り」なんて本来なら素泊まり客が目移りするような「居酒屋密集地帯」になっていて然るべき場所だと思うのだが、そこに店を出している居酒屋は『十六夜』と・・・もう一軒ぐらいあったかな?・・・とにかく寂しい限りである ― ここまで「空きテナント」だらけになってしまったシャッター商店街状態の<神明通り>なら、その空きスペースに「素泊まり簡易宿泊施設」を多数設営することによる街興しという逆転の発想(『Shelter-inn』)もアリだと思うのだが・・・ま、いくら企画案まとめて「どうぞ御覧あれ」と言っても『神明通り商店街事務局』は聞く耳持たないみたいだし、この画期的アイディアは「ある特定の条件を満たす閑古鳥観光地」なら(会津若松でなくとも)どこにだって適用可能な企画なので、「何がなんでも会津っぽに見てもらわねばならぬ」ってわけじゃないから、べつにいいけどね・・・
・・・そんなこんなで長っ尻させてもらった『風街亭』を出たのは夜の9時をかなり回った頃。本当はこの後も(まだ開いてるお店があれば)居酒屋のハシゴをしてもいいのだが、平日の午後10時に近いこの時間から入店してもたちまちラストオーダーの時間になってしまうだろう・・・ということで、先ほどの『風街亭』のマスターの話を聞いてますます気になる存在として浮かび上がってきた「七日町通り」を、この際だから「七日町駅」に至るまでテクテク歩いてみることにした ― 明日の午後には(磐梯山の麓の「五色沼」の散策から帰ってから)訪れるつもりの場所ではあるが、今日のようにジリジリ照り付ける真夏っぽい太陽の下、果たして徒歩で行ける道のりなのかどうか、この心地よい夜の空気の中を歩いて確かめておきたい気分になったのである・・・で、実際歩いてみると、<大町通り>と<野口英世青春通り>の分かれ目の十字路(ホテル「大阪屋」の角)から<七日町駅>までは徒歩で10分少々。他の通りもそうだけど、<七日町通り>もやはりひたすらまっすぐな直線路 ― 曲がったことの大キライな一本気で律儀者の会津っぽの街には、ひたすらまっすぐな一本道がよく似合う、といったところか。道幅は(特に歩道は)<大町通り>・<野口英世青春通り>・<神明通り>よりは狭い感じだが、<七日町通り>の道筋には(営業時間は過ぎているものの)きちんと商売しているお店が並んでいることを確認しつつ、30分ほど夜の空気に当たってすっかり酔い覚まし完了した状態で「神明通り」の「ゲストハウス なかやすみ」に帰着したのは、午後10時を回った頃。
・・・他の宿泊客に耳障りな物音を立てるのも気が引けるので、誰もいない一階フロアでバックパックの中から就眠用の半袖シャツと短パンを取り出し、一階のトイレの(和式なので他のお客さんが利用する可能性が低いであろう)中で着替えと用足しを済ませてから、二階ゲストルーム入口近くの二段ベッドの上へと梯子を静かに登って、眠りに就く。
・・・明朝は(7:35)会津若松発の磐越西線(猪苗代行)に乗る予定なので、本来ならiPhoneのアラームを午前6時30分あたりにセットしたいところだが、けたたましく鳴り響く早朝のアラーム音は他の宿泊客の安眠妨害になるので、遠慮しておく ― アラームなしの状態で、果たして朝の何時に目覚めるか、それ次第で明日一日の旅程は決まるわけだ。何とも不自由でいいかげんな感じだが、ま、こういう旅もたまにはいいだろう・・・
.
.
・・・公式の「案内図」には「片道徒歩1時間20分」とあるアップダウンもさほどない山道を歩き抜けて反対側の「裏磐梯高原駅」まで達するのに自分が要した時間は「1時間4分」 ― 平日だったせいか、山道を行く観光客は(一番最初の「毘沙門沼:びしゃもんぬま」周辺に中華系の賑やかな面々がワンサカいたのを除けば)ごくごく僅かで、向こう側からやってくるパーティと出会った数は11回、そのうち「熊除けの鈴」を鳴らしつつ歩いていたのはわずか3組だったが、まぁ「鈴無し組」はみんな最低二人組だったから、道々あれこれペチャクチャおしゃべりしていさえすれば「クマさん、こっちに来ないでね」のアラームとしては(歩き疲れて無言、という状況にならぬ限りは)十分なのかもしれない。自分は一人旅なので、バックパックから吊り下げた金色の真鍮製熊鈴を絶えず響かせながら歩いたが、「チリリ~ン」と鈴虫のような優しいその音色はいささか頼りなげでクマさんの耳にちゃんと届くかどうか不安だったので、鼻から酸素を吸入して口から二酸化炭素を吐き出す「スースー/ハァハァ・スースー/ハァハァ」のプロセスを思いっきり誇張した荒い息をわざと周囲に響かせながら歩く、というまるで無音の電気自動車がガソリン車を模したエミュレーションサウンドまき散らして走るみたいなマネしての山中散策であった・・・おかげもあってか、クマさん(福島県内に出没するのはツキノワグマ)には出くわすことなく、午前10時ちょい過ぎにはあっさり反対側まで突き抜けてしまった。
・・・この1時間ちょっとのトレッキングで感じたことを書き出すと:
●一番最初に出くわす「毘沙門沼」は、一番大きくて一番キレイな青い色をした湖っぽい沼・・・コース中盤の「青沼」も最後の「柳沼」も同系統のアクアマリン(というかコバルトブルーというか「バスクリン」を入れたお湯の色)だが、それ以外の沼にはあまり心動く色彩はなかった・・・「赤沼」なんかは濁った黄色で、周りの草木が鉄分で「赤」に染まってるだけ・・・大方の観光客が「五色沼入口」で「毘沙門沼」の周りをグルグル回っただけで帰ってしまうのも、まぁ当然かな、といった感じ。
●自然探勝路には大きくもなく小さくもない石が(自然に)散りばめられているため、泥でぬかるんで滑って転びそうな場所はほとんどない。普通の運動靴でも問題なく歩けそうだが、底が薄すぎる靴やハイヒールで挑めるのは一番最初の「毘沙門沼周辺散策」だけだろう。
●ごくごく一部の急な上り下りの隘路を除き、道幅は全般に(マウンテントレイルにしては)かなり広く、「五色沼入口」から自然探勝路に入るパーティと「裏磐梯高原駅」から来るパーティとが逆方向ですれ違っても渋滞が起きることはなさそうだし、遅いパーティに追い越しをかけるのも無理なくできそうな感じである。
●ひとたび探勝路を歩き出してしまえば、山道の途中でコースを外れる危険性は(ほぼ)ないが、一番最初の「毘沙門沼」から自然探勝路に入るあたりでは案内図が極めて不親切なため「毘沙門沼一周コース」と「五色沼(全体)自然探勝路」との見分けがまったく付かない・・・このあたりの対人インタフェースのお粗末さは、「猪苗代湖一周サイクリングコース(=イナイチ)」に関しても言える「観光客相手の商売がヘタクソな福島県」丸出しといった感じである。
●五色沼自然探勝路は自然保護地区のため、途中には売店も休憩所もトイレもゴミ箱も何もない・・・その種のものを置いたら、貴重な自然が損なわれるばかりか、熊が人の食べ残しに味を占めてエラいことになる・・・ので、トイレでの用足しも食堂での腹ごしらえも(もちろん「ゴミ捨て」も)自然探勝路両端の「ビジターセンター」か「物産店」に辿り着くまでは(最低でも1時間以上)おあずけである。
●無料で辿れて、起伏も緩やかで、木々に覆われて涼しくて、行き交う人の数もまばら、という好条件を利して、「トレイルラン」のトレーニングコースとして五色沼自然探勝路を走るランナーもいたりする・・・自分も1人、向こう側から走って来るトレパン・トレシャツ姿の女性に出くわした・・・一瞬「ヤバぃ! あっちでクマが出たか!?」と思ってビビッたが、相手の女性が「こんにちわ!」と軽快な挨拶を残して走り去ったので、「あ・・・トレランしてるのか」とわかって安心した次第・・・みなさんも「クマの出る山道でのトレイルランのトレーニング走行」する際には、行き交う人には「こんにちは!」ときちんと声かけて、「クマ出現のfalse alarm(誤警報)」を発しないよう心がけましょう。
・・・てな感じで午前10時そこそこであっさり終わってしまった「五色沼散策」であった。帰りのバスの時刻を確認すると(11:26)に「裏磐梯高原駅」を出て(12:05)に「猪苗代駅前」に着く便がある ― 待ち時間は約1時間半 ― 山道の途中で写真や動画を撮ったり、行き着いた先の食堂で早めの昼食を取ったりすれば、この待ち時間は残り20分とか30分とかまでいぃ感じで減らせることだろう・・・が、ひたすら早足でズンズン歩き抜けてしまった自分は、そうして生じた1時間半のヒマな時間を、「物産店」で目にした「山塩ジェラート」を頬張りつつ、日なたぼっこするノッポのクマみたいにそこいらじゅうあてどなくぶらついたり、高台の石のベンチに腰下ろして「桧原湖(ひばらこ)」をボーッと見下ろしたりしながら、6月とは思えない強烈な日差しの下、黒い制汗シャツで覆った両腕をジリジリ灼かれて過ごす羽目になった。
・・・桧原湖のほとりにつながれた手漕ぎ/足漕ぎの小型ボートも、大型の遊覧船も、平日の本日はのどかにお休みのようだ・・・「誰もいない湖」というシチュエーションを利して、黒いスピードボートがたった一艘で向こう岸の水面に自由な白波を立てている・・・この桧原湖も五色沼もそうだが、春先に訪れた猪苗代湖もやはりお客さんがほとんどいない閑散状態で、(地元の人はともかく)旅人にとってはこうした「空いてる」感覚の自由度がこれら「閑古鳥観光地」のいいところと言えるわけだが、そのフリーな気分を野放図にエンジョイしすぎると「猪苗代湖ボート事故」(2020年9月)みたいなことも起きるわけであろう。少ないとは言ってもちゃんとそこにいる他人に対する「傍若無人の我が物顔」での放縦は(外来の観光客には)慎んでほしいものである。
・・・行き交う人の数も少ない「希少性ゆえの貴重性」という福島県の特性を(鎌倉や京都や軽井沢みたいな)芋洗い海岸のごとき人出で黒字に塗りつぶしてほしくはないが、それにしても今の福島県には(今よりもかなり多くの)外来訪問者が必要なのは確かである・・・が、そうして人出を呼び込んだ後で、「閑散ゆえの穏やかで手厚い対人関係」に慣らされた福島県人たちが、「暴力的なアリの群れ」のごとき観光客の猛威(=オーバーツーリズム)にうまく対処できるものかどうか、彼らの県民性を思うと、かなり不安なところではある・・・まぁ、それ以前にまず、いまだに拭い去れていない<原発事故に沈んだフクシマ>というマイナスイメージの風評被害を、新たに生まれ変わった<新生フクシマ>の魅力の数々で塗り替えるほうが先決なわけだが・・・
・・・早歩きのツケの1時間半もの無聊の時を過ごした末に、ほぼ定刻の11時半頃にやってきた会津バスに乗って正午ちょい過ぎに「猪苗代駅前」に到着。「会津若松」に戻る磐越西線は(12:52)まで出ないから、50分近い待ち時間のうち10分ほどは、先日(4/20)に「いなチャリ」でお世話になった駅前の「猪苗代観光協会」で係の方たち(2名)との雑談で過ごさせてもらう。今回の会津若松再訪に6/17, 18, 19を選んだのは、6月15日(日)が「会津磐梯山の(例年より3週間遅れの)山開き」だったから ― 猪苗代観光の最大の目玉(であろう)「磐梯山登山」のために猪苗代駅を訪れる観光客がどれぐらいいるのか、猪苗代観光協会の人に尋ねるのも今回の旅のリサーチ課題の一つ・・・だったのだが、どうやら、磐梯山への登山客は「麓の駐車場まで車で乗り付けて日帰り登山する」か「山麓の旅館に前日から宿泊して山登りを楽しんでから帰る」かの二択であって、「磐越西線の猪苗代駅に降り立ち、タクシーで山麓まで乗り付け、山登りして下山してまた磐越西線で帰る」という鉄道旅での登山者はほとんどいないようだ・・・ということは、猪苗代駅も猪苗代市街地も、そしてもちろん会津若松も、「磐梯山登山のベースキャンプ」としての恩恵をロクに受けていない、ということになる・・・このあたり、やはりかなりのテコ入れが必要なようだ ― 赤字ローカル鉄道への乗車そのものを「旅の主目的」に変えるような車窓風景賞美体験『train-tri-view(車窓三景)』と『寝るだけ宿泊施設(shelter-inn』による「素泊まりトラベル」の相乗効果でそこそこの改善は見込めるだろうが、今現在の寂れぶりをどうにかするには(会津若松はともかく)猪苗代は・・・難しいだろうなぁ ― 「磐梯山」も「五色沼」も「土津神社(はにつじんじゃ)」も足でカバーするには無理がある距離だし、途中の街には何にもない感じだもんなぁ・・・
・・・ほんとに民家と田畑以外なぁ~んもない猪苗代駅周辺を歩き回るのにもいたたまれず、早々に駅舎に入り、列車が来るまでの30分近くをベンチに腰掛けてボーッと過ごし、定刻通り(12:52)にやってきた磐越西線に乗ってまた30分ほどの時間をボーッと過ごして、会津若松に戻った(13:20)はまさに一日の日盛り ― 「今って、まだ6月、梅雨明けしてないはずだよね?」とお日さまに問い返したいほどの強烈な日差しの中、本日の午後のメインイベント「七日町通り探訪」の始まりだ。
・・・相変わらず、「大町通り」を歩く人は自分の他にはほとんどいない・・・まぁ、今日のこの暑さじゃぁ、なまじ外など出歩かないのが正解かもしれないな ― ゆうべ見た福島ローカル局のテレビニュースでは、昨日一日で十人の熱中症搬送患者が出たらしいから。
・・・睡眠時間3時間少々で「五色沼」を1時間で踏破するのに電車とバスに2時間揺られてのトータル6時間(そのほぼ半分は電車・バスの時間待ち)の旅を終えて会津若松駅までトンボ返りしてまたこの人気のない「大町通り」を焼け付くような日差しを受けながら歩く自分の身体も、実はけっこうヤバい状態かもしれないのだが、旅先ではあっさりガンバレてしまうのは、何故だろう? 勝手知ったる自分のテリトリーを離れたよその土地ではいつ何が起こるか知れたものではないので、心身共に臨戦態勢を保ち続けるべく体内にアドレナリンが出まくっているということなんだろうな、きっと・・・で、その緊張が緩んだ旅の終わりには疲れがドッと出て、帰りの高速バスで爆睡したり、出し抜けにギックリ腰になったりする、と・・・
・・・ともあれ、今の自分はアドレナリン全開、午前中に「五色沼」を歩き倒したのと同じように、無人の野を行く勢いで炎天下の「大町通り」をズンズン歩いて行く・・・まぁ実際、通りはほぼ無人なわけだが、それでもお店のいくつかはちゃんと開いている:
●『若松通商<会津営業所>』 ― 東京の秋葉原がまだ(今のような「ヲタクの聖地」ではなく)「電気街」だった頃にはランドマークの一つだったお店(今はそのビルも解体されて「ラジオ会館」のテナントとして営業中)が、この会津若松駅からほど近い「大町通り」に店を開いているのを(前回の4/19の旅で)見付けて、何ともノスタルジックな感慨を催したものだった・・・後でネットで調べたところ、「創業者が若松生まれ」だったらしい・・・「電気つながり」ということで言えば、会津若松には『会津大学』という「国内初のコンピュータ専門大学」があるらしい。日本国内のパソコン普及の着火点となった「Windows95」発売の年は1995年、それより2年早い1993年開学だというから、当時としては「コンピュータ工学のみに振り切った教育機関」には斬新性・話題性があったものと推測されるが、30年以上を経た今現在の位置付けはどんなものなのだろう・・・「大学受験指導」から「語学教材開発」へと完全にシフトしてしまった今の自分には、「会津大学」の「入試難易度」だの「受験生の間での評判」だのといった方面にはまったく何の知識も関心もないが、在学生・卒業生のコンピュータプログラミング技能と、教授陣の半数近くが日本国外から集められたIT技術の専門家だというその国際性には、俄然興味を引かれるところ・・・もしこの之人冗悟(Jaugo Noto)/合同会社ズバライエ(ZUBARAIE LLC.)が会津の地にその営業拠点を移すとすれば、「IT技術先端都市」としての会津若松の力を是非とも頼りにしたいところであるし、自社の営業展開を通じて「会津って、実は意外とテクノロジー先進地域だったりする」というアピールで「原発事故で沈んだフクシマ」のマイナスイメージ払拭にも一役買う自信と目算は大いにあるのだが・・・ま、そのあたりは「縁」と「運」ということで・・・
●『みんなの居場所 <まる。>』 ― 茶色い木枠の上の白い丸に「こどもまんなか」と描かれた看板が、「神明通り」の居酒屋『十六夜(いざよい)』とよく似てるけど、ここは「子どもたち(と保護者のみなさん)が気軽に立ち寄って街のみんなのコミュニケーションやアクティビティの拠点になれたらいいな」ということでできた(開設ホヤホヤの)くつろぎスペースだということである。自分は昨日の午後、「練乳アイス(だか、かき氷だか)あります」の看板に誘われて涼みに立ち寄らせてもらって長っ尻しちゃった上に「会津若松《復興》四案」やら何やらの長話で(ほんとは開店間もないお店の準備やら何やらでかな~り忙しかった)スタッフのお姉さんにけっこう迷惑かけちゃったりしたのだが、「江戸~明治」の雰囲気を漂わせつつ半ば眠ってる感じの「大町通り」にあっては、この<こどもまんなかカフェ>(と、その経営母体の<Lotus(ロータス) Group>)は、街に新たな息吹を吹き込もうとする雰囲気を感じさせる数少ない存在・・・「木(wood)」の質感を前面に押し出した感じのそのたたずまいは「水郡線のローカル駅舎」を彷彿とさせて、”木色(woody color)”が大好きな自分には好印象・・・なのだが、その突出した存在感が逆に微妙な違和感を与えてしまうあたりに、今の「眠れる大町通り」の病根の根深さを感じざるを得ないあたりが、なんとも悲しいところ・・・やっぱ、この街にはもっともっと新たな刺激と芽吹きが必要だよなぁ・・・
●『會津町方伝承館』 ― 「赤べこ」や「会津塗」といった「昔ながらの會津名産品」の展示販売のほか、会津若松市内の案内もしてくれる(市が運営する)施設。昨日ここに立ち寄った時には(山形県からの)修学旅行で来たという小学生の男の子三人組が「起き上がり小法師(こぼし)」に色塗りする作業にチャレンジしていたが、今日もまた旅の小学生とおぼしきちびっこ数人が施設の前の通りをチョコマカしてたから、修学旅行の小学生たちにとっては「会津の街の定番訪問スポット」として(事前学習段階で)マークされている場所なのだろう・・・昨日の午後に立ち寄った「七日町通り」入り口にある『昭和なつかし館』でも(おそらく同じ山形県からの修学旅行の)子供たちが「わぁ~、昭和だぁ~」とかわかったようなわかんないような黄色い声上げながら「くじ」引いたり「ビー玉」買ったりして楽しげにキャッキャしていたから、あそこもまた「立ち寄りポイント」として事前マークされていたのに違いない。
・・・今の会津若松の観光業にとっては、こうした「修学旅行の子供達」がか細い頼みの綱なのかもしれない ― 「七日町通り」界隈のホテルに関するネット上の口コミにも「修学旅行生が宿泊しているらしく、声がうるさくて迷惑だった」といった(自分も子供だった頃があることを完全に忘れているらしいかわいそうな大人の)否定的書き込みがちょこちょこ目立ったりするし。
・・・子供は未来の希望の種だが、近隣県の学校が修学旅行先としてこの会津を選ぶ理由が「他にあまり旅行客がいないため、生徒たちがトラブルに巻き込まれる危険性が少ない」とかの事情によるものだとしたら、それは会津の未来の希望の種からはほど遠い話になってくる。会津には「修学旅行の小学生たちが安心して歩ける街」であり続けてほしいけれども、「1キロも続く大町通りを歩いても歩いても出くわすのは修学旅行の小学生ばかりの街」であり続けてもらっては、やっぱり困る・・・子供も大人も安心して楽しめる会津 ― そうなる潜在可能性は会津若松の街には山ほど眠っているし、それを呼び起こす方策だって山ほどある(当方がとりあえず思い付いた企画案だけでも6つもある)・・・が、いかんせん、今の会津には「こういう新しいこと、やってみてはいかが?」という余所者からの声に耳を貸そうという空気がほとんど感じられないし、そもそも「会津若松を新たに生まれ変わらせるための気概と機略」が致命的に欠落しているらしいことは、廃業や空き地やテナント募集だらけの「大町通り」や「神明通り」の姿を見れば誰の目にもわかる ― 誰が見てもそう思うだけに、「何をやってもムダだべ」みたいな諦めの境地(defeatist attitude=負け犬根性)が板に着いてしまっている、という寂れた日本の地方都市にありがちな負のスパイラルに完全にはまり込んでいるように見える・・・まぁ、この「敗者のメンタリティ」はなにも会津若松市のみに限ったことではなく、1990年代以降の大方の日本人にすっかり染み付いてしまった「国民病」である(ように、ありとあらゆる観点から「日本人離れ」しているこの之人冗悟の怜悧な観察眼には)見えるのだけれども、それでもこの会津若松の街には「眠れる街を目覚めさせるための方策」がいくつも立案できるだけの「素地」が山ほど眠っているのだから、思わず余計な口出しをしたくなるというか、「助けが要るものを、見て見ぬ振りはするな」という私的信条(<誠賢十箇条>その四)に照らしてもただ溜息つくだけの傍観者ではいられない気分のこの之人冗悟(冗語の人=余計な口数のやたら多いヤツ)なのである・・・が、潜在可能性は豊富にあるのに、そういう可能性もよそ者からの入れ知恵も最初からまるで見ようともしない「会津の民のnegativism(否定的体質)」だけが、返す返すも残念でならない ― その「後ろ向きなメンタリティ」さえ脱却できれば、可能性豊かなこの会津若松の再生なんて、さほどの難事業でもないはずなのに・・・
・・・栄える「活力」、蘇る「生命力」のある街ならば、自分たちの「眠れる街」を目覚めさせる(かもしれない)方策を何かの拍子に住人の誰かが聞き付けたなら、たとえ「自分にそんな話されても、ちょっとねぇ」という場合であっても、それを知り合いの(そういう方面に知識や関心のありそうな)誰かに伝えて「可能性の芽吹き」のお手伝いぐらいは必ずするもの(せずにはいられぬもの)なのである・・・が、会津若松の人々からも飯坂温泉の人々からも、そういう積極性は微塵も感じられなかった ― 彼らは何も「自分たちの郷土である会津若松や飯坂温泉を愛していない」わけではなく、「今の会津や飯坂を何とかしないといけない」という問題意識がないわけでもない。ただ「自分のようなちっぽけな存在に、郷土を救うなんて大それた芸当ができるわけがない」という<謙遜>のスタンスに凝り固まっているだけなのである。「謙虚は美徳、出しゃばりは悪徳」という(何もしない自分を正当化するのに都合のよい)お粗末な道徳観ゆえに、「郷土を救うなどという大それた事業はお上の仕事であって、自分のような下々の民の領分ではない」という逃げ腰根性、「<自分たちの郷土を救う主体>であるはずなのに何にもしてくれない<お上>の怠慢」にただただ文句を並べるばかりの受身根性・受益者意識・被害者感覚に漫然と身を委ねるばかりの淀んだ無気力・無行動が、彼らのネガティブ体質の正体なのである・・・が、そんな態度の行き着く果てに待つものは「廃業」と「空き地」と「テナント募集」だらけの寂しい地元であり、そんなだらしない郷土に見切りを付けて余所へと転出する若者達のexodus(出 フクシマ記)なのだから、これはもうはっきりと「百害あって一利なしの<謙遜>という名の<当事者意識の欠落>が招く<負け犬根性>」以外の何物でもない。
・・・父方も母方も親類縁者は全員福島県人である自分ははっきりと断言するが、この「新機軸開拓(に結び付くような前向きの精神傾向)の欠落」は、福島県人全般の実に残念な体質なのである ― 何でもかんでもまず”否定(いや、しかし)”から入り、相手を否定しただけで自分が何か一仕事終えた気分になったり相手よりも自分の方が一段エラい立場に身を置いているような気分で悦に入ってみたり、前例によって成功が保証されている(ように見える)道以外は最初から歩もうとも見ようともしなかったり、そういうひたすら気が滅入るばかりのネガティブ体質の面々を「反面教師」とすることで、「誰も思い付かないしやらないようなトンデモないあれこれ」を幾つも形にし続けてきたこの之人冗悟(のと・じゃうご)なのだ・・・第四回(2017年)日経星新一賞グランプリ『OV元年』みたいな「近未来SF」を思い付いたりするのも「会津若松《復興》四案(・・・その後2つ追加してトータル六案)」をまとめて会津の民に見てもらおうとするのも、いずれも「やる前から”どうせダメだから、やってもムダ”とかホザいて一歩も動こうとしない後ろ向き体質の負け犬人間どもを尻目に、ひたすら前向きの思考と行動に徹する」という自分の「anti-negative(反・否定)体質」から生じたものなのだ。
・・・福島県人達が、そうしたマイナス指向の淀んだ空気を自らの体質改善努力で改めない限り ― 会津若松や飯坂温泉のためによそ者が立案した《復興案》を「最初から開いて見ることすらしない」というような(部外者に対しても自分たちの未来に対しても)閉ざされた心をなんとかしない限り ― この自分が活動拠点(&終の棲家)を「フクシマ」に移すことは、ないだろう・・・まぁ、このあたりは「縁」と「運」の話なので、この地に見切りを付けてどこかよその土地で「ズバ抜けてどエライ偉業」を達成しちゃった之人冗悟(Jaugo Noto)/合同会社ズバライエ(ZUBARAIE LLC.)を見ても、恨みに思ったりすることなく、自らの体質改善の必要性を猛省するだけに留めておいてね、フクシマのみなさん・・・ぁ、これは「自分たちだけが相変わらず住み続けている”古里”に後ろ足で泥引っかけるようにして出て行っちゃった若者たち」に対しても、同じだよ。
・・・と、こういうこと言われて「こんな傲慢なヤツの口から出て来る話なんて、何がなんでも聞いてやるものか!」と感情的に心の殻を閉ざし、「どうせこんな生意気なヤツが口にする話なんて、ロクなもんじゃないに決まってる!」と最初から決め込んで、「相手の話に素直に心を開き耳を貸そうともしなかった自分自身の度量の狭さ」を反省する代わりに、相手側を一方的に否定する、相手の能力や実績が否定し得ない素晴らしいものだった場合には「だけど、あんなに性格が悪いんじゃぁ、話を聞きたい気分にもならないのは当然だろ? 悪いのはあっちの態度であって、それを嫌気したこっちには何の落ち度もないんだ」といった形で相手の「人格否定」へと逃げ込んでまであくまでも「自己正当化」に終始する(で、「自己改善努力」は何もしない)・・・古い日本を重苦しく包んでいたそういう淀んだ空気には、もういいかげん、決然と終止符を打たねばならない時代が来ていることを、この之人冗悟、たとえ全ての日本人から忌み嫌われようとも、ここで断固として力説しておく。考えてもみるがいい ― 今のような無為無策を続ければ、今後の日本には「少子高齢化による自然消滅」を避けるために「海外から流入する新日本人」の血脈が是が非でも必要となるわけだが、そうした「在来型の日本人とは異質の出自と思考・感覚・行動様態を持った人々」に対して、古くて淀んだ狭量なネガティブ体質の日本人が頭ごなしにこれを否定・無視するばかりのケッタクソ悪い自己正当化の態度で臨んだら、相手側の「新日本人たち」は決してそんな態度を許さないのだから、そこからは「摩擦・軋轢」しか生じない。そうしてそこに「対立構図」が生まれた時、最終的に勝利するのは「わざわざ外国から<滅び行くニッポン>へと渡来して自分たちの新天地開拓にトライするイキのいい連中」に決まっているのである(・・・インカ帝国やアメリカインディアンの末路を見るがいい)・・・先祖代々受け継いできた「土地」だの「立場」だのでのうのうと生きて行けた古い時代ならともかく、新たな地平を築く構想力と実行力がない限り敗残者として落ちぶれて行くしかない新時代に於いては、狭い了見に凝り固まって必ず負けるに決まっている新参者との愚かな対立構図へと自らを追い込むよりも、余所者ならではの客観的状況認識や旧習に囚われない新たな考え方に基づく新機軸を積極的に受け入れ共に実行する建設的共存共栄の作法を身に付けるほうが、ずっと良いに決まっている(というより、そうせぬ限りはブザマな自滅の道を辿るしかない)ではないか・・・
・・・これ、福島県人のみに限らない、これからの日本人すべてに当てはまる「意識改革の勧め&生き方を改めて進め!」の訓戒なんだけど・・・ちゃんと聞く耳持ってる人、今の会津に、日本に、いったい何人いるのかしらん?・・・
・・・ということで(これぞまさしく「昭和」って感じの)お店の暖簾をくぐって入ってみると、意外なことに(と言うと失礼かもしれないが)地元の人とおぼしき先客さんが四人もいた・・・「会津若松駅」から「大町通り」をここまで歩いて出会った大人の総数より多い・・・その横をすり抜けて、奥の厨房に一人ぽつねんと居るおばあちゃんに「ソースカツ丼、やってますか?」と尋ねると、「料理ができるまでかなりお待たせしてしまうんですが・・・」との答え ― どうやらこのおばあちゃんが一人で切り盛りしているお店らしいので、先客四人の注文をさばくだけでも手一杯なのだろう・・・こういう場合、相手側のキャパシティを考えずに自分側の都合(=この食堂が発祥の地だという「ソースカツ丼」を食べてみたい、という希望)を優先させるのは旅人としての嗜みに反する無粋な振る舞いだから、ここは素直に「あ、それじゃぁかえって御迷惑かけそうなので、今日は御遠慮しときます」と言い置いて、お店を出る。
・・・四人のお客さんに料理を出すだけでも手一杯そうなおばあちゃんがやっている『若松食堂』という現実に触れて、ゆうべ喫茶店『風街亭』のマスターに聞かせてもらった「大町通りのミュージックフェス」のお話を思い出した ― 「あまり大勢のお客さんに来られても、お店のほうでは注文をさばききれずにお待たせしてしまって、かえってお客さんに迷惑をかける」 ― ちょっと聞くと「せっかくあれこれ知恵を絞ってイベント開いて大勢お客さん呼んであげたのに、そんなこと言われたんじゃ、もうやってられない」というイベント主催者側のぼやきを招くような「恩知らずな反応」に思えるかもしれないが、これは決して「大町通り側」の「恩知らず」とか「有り難迷惑」とかの否定的反応ではなく、「開いているお店もまばらで、そのお店にも通常あまり多くのお客さんは来ない」という地方都市の閑散とした商店街の実情を考慮せずに「ただ大勢の客を呼べばいい」という機械的発想で動いただけのイベント主催者側のチョンボだと見るのが正しい見立てであろう ― 要するに「思慮が足りない」というか「本源的な努力をしていない」というか、「単なる付け焼き刃」のムダな出し物で地元に過剰な負荷をかけただけ、という図式である。
・・・「客足が乏しい」から「商売が成り立たない」ので「お店の多くは廃業」してしまい「やってるお店もまばらな閑古鳥商店街」に、お祭りだのイベントだので一時的に取って付けたような客足を呼び込んだとて、地元の抱える構造的問題の解決にはまったくつながらない・・・が、大方のイベント主催者は「ただ客を呼ぶだけ」で「地元への貢献」になると信じ込んでいるのだから、地元の「閑散商店街」との間の思惑のミスマッチ(&お互いに対する不信や不満)が生じるのは必然の構図なのである。イベントが終われば引き潮のように消えて戻ってこない「一時的な客足」なんて、一瞬キレイに輝いてたちまち消える「打ち上げ花火」みたいなもの、そんなものブチ上げてどれほどの客を呼んだとて、それは所詮イベント主催者側の自己満足に過ぎない。そんなハタ迷惑な他人の自己満足のために地元の人々が高い金払った挙げ句、お客から「遅い!いったいいつまで待たせるんだ!?」とか怒鳴られてイヤな思いするなんて、まったくバカげている。
・・・そのあたりの論理的・倫理的構図がまるで見えていない身勝手な自己満足中毒者どもが「客足回復」だの「街興し」だのの名目で地方都市にタカる困った図式 ― もしかして、会津若松の閑散商店街は過去にそういうハタ迷惑な押し売り連中の「被害」に何度も泣かされているせいで、「地元の実情も知らずに、こうすればいい、ああすべきだ、と独り相撲取った挙げ句に高い金ふんだくって行くばかりのインチキ野郎ども」への反射的否定行動が習い性となっていて、それでこの之人冗悟(Jaugo Noto)の「会津若松《復興》四案(いまはもう六案)」に対しても最初から貝のように堅く耳と心を閉ざして一切取り合わない、ということになってしまったのかもしれないな・・・
・・・自分の提案はいずれも一過性の「客寄せイベント」ではなく「街そのものを<人々が訪れたくなる>&<商店が出店したくなる>ような魅力的な姿に作り替えることで<客寄せ>とは本源的に異質の<閑古鳥商店街からの脱却>」を果たすための恒常的な「会津若松改造計画」であるということ、開いて見てくれれば確実にわかるはずなのだが、そもそも開いてももらえないというのでは何一つ始まらない・・・やれやれ・・・「縁」と「運」、どうやら、自分と会津若松との間には、うまくつながりそうにもないな・・・
・・・とりあえず、お昼ご飯のご縁もなかった『若松食堂』は諦めて、昨日の午後に立ち寄った『昭和なつかし館』の姉妹店だという『蔵』という名の喫茶店目指して歩くことにしよう ― 小学生なら大喜びしそうな「50円引き券」ももらってることだし、これも何かのご縁ということで・・・
・・・かなり遠い距離から(なんたって間を遮る通行人の一人もいないもんだから)この不思議な老人と少年の「炎天下しゃがみこみ劇場」の成り行きを見つめながら歩いてきた自分だったが、数分後、問題の信号のある十字路に自分が差し掛かろうという直前あたりで、男子学生は自転車にまたがって前方へと走り去って行った。後に残ったのは、歩道の脇に停められた自転車と、路上のアスファルトに両手両足とお尻を付けたまま、目をつぶってじっとしているおじいちゃん一人・・・通りを行く者は、この自分一人・・・これはもう、黙って通り過ぎるわけにはいかない状況である・・・
「どうした~? 自転車でコケちまったかぁ?」 ― 自分の口をついて自然と出てきたのは(言葉のおしりを持ち上げるだけで微妙に和むアクセントの)「疑似福島弁」・・・横っちょにスタンド立てて停められている自転車のサドルが15度ほど右へヒン曲がっていることからして、転倒事故であることは明白である・・・相手は案の定、「いやぁ、まいったなぁ・・・自転車でこんなコケたの、生まれて初めてだぁ~」と言葉を返してくる。どうやら口がきけないほど大きな衝撃は受けてはいないようだが、この炎天下でいつまでもアスファルトの上にへたりこんでいられては確実に熱中症になる・・・
「そらぁまたえらい目にあったなぁ・・・サドルも、ほら、こんなひん曲がって~」 ― 「いや、ひん曲がってはいねぇ、だいじょうぶだぁ」 ― 福島県人の発話は”否定”(いや、しかし)が基調、しかも相手は相当年配の老人であるから、こっちが「**するかぁ?」と尋ねれば「いや、だいじょうぶだぁ」と反射的に「NO」のこだまが返ってくる・・・とりあえず、自転車の荷台にまたがって両手でサドルを正しい方向へと直してやる・・・触れた両手がヤケドするほどサドルが熱いので、転倒してからもうすでにかなり時間が経っているのだろう・・・ともなれば、焼け付くような太陽の下、フライパンみたいなアスファルトの上に、このままこのじいちゃんをへたりこませっぱなしにしておくわけにもいかない・・・
「それにしても、今日はまた暑いなぁ・・・焼け焦げそうだ~・・・ここはアツくてかなわんから、ほら、あっちの日陰のほうにとりあえず移ろうか」・・・しかし、返ってきた答えはやっぱり「いや、だいじょうぶだぁ・・・しばらくここでジッとしてれば治っから」 ― これ以上ここでジッとしていたら熱中症でヤラれちまうのは確実だが、そういうところまで頭が回る状態ではないというか、「だいじょうぶ。だいじょうぶ」を繰り返しているうちに自分はきっと大丈夫になる、と信じ込んでいるというか・・・とにかく、他人の手を借りて助けてもらうよりも、自分で何とかこの状況を抜け出したい(けど、とりあえず今は何がなんだかわからん状態なので、このまま静かに放っておいてもらいたい)という心理状況にあることはハッキリとわかった。
・・・それと、どうやらさっき自転車で走り去った男子は、この老人と衝突したわけではなく、歩道の真ん中に自転車もろとも倒れているこのおじいちゃんを見つけて、助けてあげようといっしょうけんめいがんばったけど、「だいじょうぶだぁ。だいじょうぶだぁ。しばらくここでジッとしてればだいじょうぶだぁ」の「”ほっといて”一点張り攻撃」に跳ね返されて、やむにやまれず後ろ髪引かれる思いで退散した、ということらしい・・・もしかしたら、後方から歩いてくる大人(=この自分)の姿を見て、「あとは、よろしくたのみます」ということでこっちにバトンを渡した格好なのかもしれない・・・ともなれば、ここはひとつ、大人らしくしっかりこの場を収めてみせずばなるまい・・・
「まぁ、しばらくジッとしてれば大丈夫になるだろうけどよ、どうせなら涼しい日陰で休んでるほうがラクだっぺよ。ほら、道を渡ったあっち側のビルの前に、いい塩梅に腰掛けられる花壇があっから、次の青信号で一緒にあっちさ渡ってみっぺ」 ― 相変わらず「いや、でも自転車があっから、置いてけねぇ」とか、抱え起こせば「いや、帽子が落ちたから拾わにゃならん」とか、とにかく何であれ「NO!と言うための理由探し」にしか頭が回らない状態のじぃちゃんの両腕の下に自分の両肘を突っ込んで、青信号を待って、ゆっくりじっくり後ろ向きの姿勢で引っ張りながら(例によって「テナント募集中」の)ビルの前にある(花の植わっていない)花壇のレンガの上にじいちゃんを腰掛けさせるのに成功・・・ちょうどいい具合に日差しをビルが遮って日陰を作ってくれている上に、花壇もまたじいちゃんの腰掛けには絶妙の高さ・・・移動の最中にまたしても落っこちたキャップとあっち側に残してきた自転車のことをやたら気にするじっちゃんに、両方ともしっかりこっち側に持ってきて落ち着かせたところで、ふと前を見ると、心配して通りに出てきたすぐ前のお店のおねえさんが、「救急車呼ぶ~?」と声をかけてくる・・・が、反射的に飛び出したじっちゃんの「だいじょうぶだぁ」の声に跳ね返されて、「じゃあ、とりあえず水分取らせようか?」と自分に語りかけてくる ― このおねえさん、「ペットお預かり」の『オリーヴ』というお店から出てきただけに、炎天下でグターッとなってる動物への対処には慣れてるようだ・・・ということで、『オリーヴ』のお店の横にある清涼飲料水の自販機から(クセのある味のポカリスエットは避けて)(さわやかな大谷翔平君が宣伝してる)「お~いお茶」の小さなペットボトルを買って開封してから、「いや、いいって、いいって」と(例によって)辞退するじいちゃんの手に握らせて、「転んだ拍子にレンズが割れて取れちまった・・・」とじいちゃんが盛んに嘆くメガネを手に取って、「どぉれ、じゃ、とりあえずフレームにはまるかどうか、やってみっかな」とか何とか言いながら、じいちゃんの横の花壇に腰掛けて、世間話モードに持ち込むうちに、あちらもだいぶ落ち着いてきたらしく、お茶をチョビチョビ飲んだりしながら、どうしてこういうことになったかを(同じ話を何度も何度も繰り返す「老人話法」で)語り出した・・・
・・・じいちゃんの話の要点をまとめると、「先日紛失した携帯電話の件で警察署に出向いたその帰りに、道端で出し抜けに自転車ごと転倒して、衝撃でメガネのレンズの端は割れてフレームから外れてしまった。今日はこの後で知り合いのところに行くつもり(だった)。壊れたメガネはまた新しいのに買い換えるからもういい。生活保護で暮らしてるからキツいけどな。88年も生きてるけど、こんな風に自転車でコケたのは初めてだ。まったくまいったまいった」ということになる。
・・・話の端々で、「あんた、親切だなぁ」の台詞が針飛びレコードのリフレインのようにちょくちょく入るようになってきたから、「だいじょうぶだ、ほっといてくれ」一辺倒の厄介な状況は脱却できたようだ・・・ということで、先ほど心配して出てきてくれた『オリーヴ』のお店に入って、おねえさんともう一人のお店の人に後を託して、自分はそろそろ退散しよう ― 「どうやらだいぶ落ち着いてきたようで、この後は、友人のとこに自転車で行く、みたいなこと言ってます・・・が、あんまり長いことあそこの花壇の上でへたり込んでるようだと心配なので、時々、お店の中からチェックしてみてくれますか?」
・・・そうしておねえさんたちにあっさり”引き継ぎ”をお願いできるのも、会津若松ならではのこと ― 東京ならこういう場合、119番(あるいは110番)に電話をかけて、事後の処置は救急車かパトカーに丸投げして終わり、というのが関の山だが、会津の民は「助けが要る人を見て見ぬフリ」なんてできないようで、自分がこうして『オリーヴ』のお店の中でおねえさんたちに後を託している間にも、通りの向こうの花壇の上にうつむいて座ってる御老人の姿に吸い寄せられるようにして、二台の自転車が次々と停車して、心配げにおじいちゃんに様子を尋ねている ― うん、これなら、もう後は絶対だいじょうぶ、「本日の熱中症搬送患者」の列の中にあのじっちゃんが加わる心配は、なさそうだ・・・というわけで、『オリーヴ』の二人のおねえさんと、お預かり中の茶色いプードルわんこ(お名前は「ココちゃん」)とに別れを告げて、通りを渡ってじっちゃんの横に戻る。
「しばらくここで休んでから、大丈夫になったら、友達んとこさ行くといい。安全のこと考えたら、自転車には乗らずに押して歩いたほうがいいかもな。それと、目の前のあのペットショップのおねえさんたちにも声かけといたから、具合が悪いようなら遠慮せずに手ぇ振るといい、必ず助けに来てくれっからな・・・じゃ、俺はここらでもう行くから」 ― 「うん、ありがとぉな・・・あんたほんと親切だ・・・みんな、ほんとに親切だ」 ― 「あったりまえだべ、ここは会津だもん」・・・言いながら、我ながらなんかジーンとしてきちゃったので、照れ隠しにおっきく手を振りながら、「野口英世青春通り」の方へとズンズン大股で歩き去る・・・
・・・途中、気になって後ろを振り返ると、またまた別の誰かさんが立ち止まって、おじいちゃんの肩に手をかけるようにして気遣っている ― 最初の若い男子を含めて、これで4組めだ。自分と『オリーヴ』のおねえさん二人を加えればぜんぶで7人もの「見知らぬ他人」が、道端でへたりこんでいる御老人一人を巡って一つの「助け合いの輪」を形成している ― 人通りもほとんどない大町通りの『若松食堂』に四人もの先客がいたのにも驚いたが、こっちの「お助け七人衆」の驚きはまたひとしおである ― 東京からの旅人の自分がその輪の一人に加われた喜びもまたひとしお・・・こういう「人から人へのあるべき振る舞い」が自然に成立する会津/福島の姿を見せられると、「他人を<人>ではなく<物>としてしか扱わない/扱えない東京の非人間性」につくづく嫌気が差している「60年来の(東京の変遷をつぶさに眺めてきた)江戸っ子」の自分としては、「主たる営業所(=法人税納付先)を東京から福島へ移す」という思いをなかなか断ち切れないわけである・・・
・・・この自転車転倒事故にはさらに後日談がある・・・
転んで地べたに叩き付けられてレンズの端っこがギザギザになってしまったメガネをそのまま使うわけにもいかず、以前(2017年)に作った(ものの、3度も調整し直してなお度数が全然合わないままだったのでこりゃダメだと諦めてタンスの奥にしまっておいた)いわくつきのメガネに掛け替えたのであるが、とにかくマトモに物が見えないので数ヶ月でギブアップして、フレームもひん曲がりレンズの端はギザギザの「転倒事故メガネ」に逆戻り ― 新しいメガネを作ろうにもまたまた度数が合わないやつにムダ金使わされてもつまらんので、しばらくそういう「目に悪い生活」を続けていたのであるが、2024年(11月)には運転免許証の書き換えがあるので、このブッコワレメガネじゃぁ「両目で最低0.7(片目で最低0.3)以上」の度数が稼げないのは明白だから、夏が来る前にマトモなメガネを新調することに決めた。
メガネを作るお店としては、こないだの(何度調整しても全然マトモに見えるようにならなかった)大手メガネチェーンは敬遠して、地元王子にある別の大手メガネチェーンのお店を選んだのだが、そこでもやはり、視力測定段階で、極度に近視と乱視が進んだ自分の眼ではマトモに度数が合うレンズを作るのが困難である、という事実を知らされることになった・・・のであるが、このお店の担当者は実に良心的な人で、「うちでメガネを作る前に、一度、眼科医で検診してもらったほうがいいかもしれません。このままお作りしても、マトモに見えるメガネにはならないかもしれないので」というアドバイスをくれた上に、視力測定の結果を(眼科医提出用に)プリントアウトしてくれて、なおかつ「本日の検眼の費用は結構です」と言って送り出してくれた。
そうして近所の眼科医で検診を受けたところ、「白内障の初期症状が見られるので、この際、手術してしまったらどうか」ということになった ― 「白内障手術で、メガネも不要な程度まで視力が回復する人がけっこういる」とまで言われ、まさかそうそう事はうまく運ぶまい、と思ったものの、とりあえずその助言通りに(別のこれまた近所の)眼科医で白内障手術を受けてみると・・・これがビックリ! 翌日にはもう裸眼で日常生活が難なく送れる状態になったではないか! 極端な近距離には焦点が合わないので「老眼鏡」が必要なものの、運転免許証取得に必要な「片目0.3/両目0.7」程度の視力は裸眼で十分得られる状態となったのである。
こうして(ほぼ半世紀ぶりに)「メガネ不要」の快適生活を手にした自分ではあったが、そもそもそのきっかけを作ってくれたのは「眼科医での検診」を勧めてくれた大手メガネチェーンの良心的な店員さん(Kさん)である ― こういう親切に対しては、当方としてもそれなりの礼を尽くさねば人としての仁義を欠くというものであるから、「白内障手術を受けることになったが、手術の成否にかかわらず、術後にはメガネを新調しに行く」こと、「新型コロナウィルスに感染して手術が一ヶ月程度遅れる」こと、「手術は無事成功したものの、眼科医の先生から<三ヶ月程度経過して視力が落ち着くまで、メガネの新調は控えたほうがいい>と言われた」ことを、いずれも当方の署名入りの手紙の形にして、「Kさま」宛てに、お店のほうに三度出向いて(当人および別の店員さんに)手渡しする「御礼行脚」をしておいた。
そうして白内障手術から三ヶ月後、本来であればもう不要なメガネを、「店員のKさんへの恩義を果たす」ためだけに新調するべく王子のお店に出向いた自分であった・・・が、来店時にはあいにく「Kさん」は昼食に出ていて留守との由、これはタイミングが悪いとみて退散しようと思った自分を引き留めた別の女性店員は、自分に「番号札」を渡して「1時間後」に来店してほしい、と言う ― そんな無駄な待ち時間を強いられるのは通常なら拒否して別の日にまた出直すところであるが、「お世話になったKさんへの恩義」を果たすために来店した自分としては、今日一日の時間はすべてその「Kさん」のために使い切ってもかまわないという気分だったので、近くのファミリーレストランで持参のパソコン広げて軽く仕事をこなしつつ1時間の時間をつぶした後で、「Kさん」への恩義を果たすべくお店に戻った・・・のであるが、どうも雰囲気がおかしい ― お店の中には「Kさん」がいるが、別のお客さん相手に接客中の様子 ― 1時間待たされて再び来店した自分の接客担当は当然「Kさん」になるものと信じていたのに、なんとしたことか、先ほど図々しくも「1時間待ち」を自分に強いた(自分としては何の恩義もない)例の女性店員に「私がゲットした客」として取り込まれてしまったこの自分は、まったくもって何の意味もない時間・労力・忍耐力+金銭の浪費を強いられる羽目になったのである。
考えてもみてほしい ― この自分が「店員のKさんへの恩義」を感じて来店していることは、この小さな王子のメガネ店の従業員の全員にとって周知の事実なのである ― 三度に渡って「Kさんへの手紙」を律儀に渡しに来る珍しい客を、二度目・三度目にはもうお店の誰もがはっきりと認識しているのを自分は(店員側の反応から)明確に感じ取っている ― にもかかわらず、その「Kさんへの恩義」を果たすために来店したことが店員の誰もに明白に認識されている客を、「自分のお客」として「横取り」するような「外道の振る舞い」を、この女店員はいけしゃぁしゃあと演じているのである ― 我が私的行動規範「誠賢十箇条その六)心の富を貶めてまで、懐の富を増そうとするな」に真っ向からションベンひっかけるような振る舞いである ― (まったく、いったいこの店はどうなってやがるんだ?!)と自分は思った・・・と同時に、(こういう人間のクズみたいなヤツに捕まっちまうたぁ、自分もつくづく、疫病神に魅入られてるってこったろうなぁ)と、逆にもう「めんどくせぇ、もうどうとでもなりゃぁがれってんだベラボーめ!」という気分になってしまった・・・で、終わってみれば結局「遠近両用メガネ」を作るつもりが「この上なく精密な度数測定」とやらを経たにもかかわらず「近距離に度数を合わせればそれ以外の距離を見ると何も見えずに頭痛がする/遠距離に度数を合わせれば手元はボヤけて裸眼よりタチが悪い」ということで、結局「遠くを見るためのメガネ/手元を見るためのメガネ」を2つ作るしかない、というバカげた状況・・・手元を見るためなら既にもう「百円ショップ」で買った老眼鏡が何個もあるのだからこの店でわざわざ買い足す必要はないし、遠くを見るためのメガネなんて(運転免許証更新に必要な裸眼視力0.7も白内障手術の結果得られているので)必要ない ― そんな不要なメガネでも、「恩義のある店員のKさんの営業成績アップ」のためになら「免許更新時の万一の備え」として喜んで購入するが、何の恩義もないこの「横取り女店員」のためにそんなもの買ってやるべき筋合いはまったくない・・・が、成り行き上もう仕方ないので、「じゃあもう手元は百均ショップの老眼鏡で間に合わせるので、遠くを見るだけのレンズにして」と指定した当方なのであるが、そもそも一番最初に乗せられた「一番<高級>な精密視力測定」の段階から始まって「<高級>で<高額>なレンズ」へとシームレスに誘導されて高い金払う流れへと顧客を巻き込むというメガネチェーン店側が編み出した新手のボッタクリ手法に則った形で「<高級>な視力測定にふさわしい<超ハイグレード>な<遠近両用レンズ>のラインナップ」をあくまでも売り付けようとする相手側の<外道店員>の鉄面皮なセールスの勢いはなお止まらない ― 「遠く」にも「近く」にもマトモに焦点が合わないことが「超精密視力測定」の結果として明白に出ているにもかかわらず、いったい何のために「超高額遠近両用レンズ」を入れるというのだ?! 外道店員のテメェの営業成績のために、なんでこの自分がそんなバカげた出費を強いられねばならんのだ!?・・・まったく、バカの鉄面皮もここまでくると、もう怒る気にも笑う気にもなれやしねぇ・・・・近頃の東京は、こっちが喧嘩腰で「ナメんじゃねぇぞオラ!」と凄んで力ずくで跳ね返さねぇかぎり、ニコニコ笑顔でこういうボッタクリ商売平然と仕掛けてきくさりゃぁがるクソ商人だらけ・・・もうホント、終わってるな、この現代のソドムは・・・
・・・結局、「超高額遠近両用レンズ」だけは拒否したものの、なんのかんので「作る必要もない役立たずの遠メガネ」に「!8万円!」ものバカげた大金を支払わされるテイタラクと相成った・・・ちなみに、「白内障手術での視力回復」に要した費用は10万円弱、そのうち4万円ほどは「高額医療費」ということで後日返ってきたので、実質費用は6万円 ― 「外道店員のボッタクリ」で奪われた8万円がどれほどバカげた出費だったことか、思い出すだに腹が立つ・・・本来なら「遠近両用のマトモなメガネが作れなかった以上、もう意味ないんで、やめます」と振り切ってしまってもよかったのだが、それをせずに敢えて「まったくバカげた8万円をドブに捨てる」という挙に出たのは、「Kさんへの恩義」を果たすことにとことん執着することもせずに「外道の女店員の横取り営業」を(内心、はらわたが煮えくりかえる思いを抱えつつ)そのまま許してしまった我が身の不甲斐なさに対する「自己処罰」として、のことである。
・・・さて、上記のケッタクソ悪い顛末を見て、アナタならどう思うであろうか? ― 「べつに、その女性店員は<外道の振る舞い>をしているわけではないのでは?」と感じるだろうか?・・・たぶん、そう思うのだろうね、アナタが東京・大阪・横浜・etc,etc.といった「むしり合い経済圏」に身を置く「都会人」であれば、ね・・・その感覚がいったい何を意味するものか、自分がいったいどういう生存状況で暮らしているのか、自覚もできずにいる人間だらけだからこそ、自分はもう「クソッタレな東京」には見切りを付けて「人から人へのあるべき振る舞い」がきちんと成立する地方都市へと「合同会社ズバライエ(ZUBARAIE LLC.)」の拠点を移し、ゆくゆくは自分自身もまた「現代のソドムに成り下がったケッタクソ悪い東京」を引き払って地方都市に移り住むことを(真剣に)考えているのである・・・が、このあたりの感覚は、わからんヤツらには何をどう説明したって絶対にわかるまい ― 「世の中みんな他人からぶんどれる限り多くのあれこれを分捕る生き方をしている・・・のだから、自分だって奪われた以上に多くの物事を他人から奪って生きてやる」というのが「現代日本の都会人の感覚」なのであって、それを大方の都会人は「おかしい」とは思わないし、たとえ「おかしい」と感じてはいても「だからって自分がそれに逆らったって、他人から一方的に食い物にされるだけだから、もうその流れに従って、なるべく損しないような生き方に徹するしかない」という言い訳で自分自身を納得させて生きているのである ― だからもう、自分としては、そんな「どうしようもない人間以下の振る舞いに対して無感覚に成り下がって平然とそれをやらかす連中だらけの東京」には背を向ける以外の選択肢が、ないわけである・・・
(・・・上記の女店員の「外道の振る舞い」を「べつに問題ないじゃん!」と感じる向きに対しては、もう少し露骨に犯罪的な「人としてあるまじき振る舞い」の腐れ商人の所業を告発した当サイト内の別記事をも紹介しておこう・・・今の東京では、何か/誰かと関わるたびに、こういうケッタクソ悪い事態に ― 日常茶飯事的に ― 見舞われるのである・・・だから東京では「なるべく誰にも何にも関わらずに済ます」という処世術へと誰もが雪崩を打って転げ落ちて行くわけである・・・)
「外道」とは「道(=ルール)を踏み外した違反者」ではなく、「自分自身の内的規範(=個人的主義信条)を持たぬヤツ」であり、「外的規範(=組織・集団の禁則事項)に抵触しない限りそれは悪事ではない、と信じ込んで平然と悪事を犯す人間のクズ」のことである ― 「法治主義」は大事だが、「内的規範の不在を外的規範で代替」することはできない ― この点の根源的思い違いを放置したままだからこそ、東京あたりのダメ都会では「狂ったルール」が増殖するばかりで「(内的規範に照らして)人から人へのあるべき振る舞い」がどんどん成立し難くなるわけである・・・「生き方の根本線を踏み外した<外道ども>の掃き溜め」となり、神の怒りを買って焼き尽くされたという「(旧約聖書の)ソドム・ゴモラ」への転落の道を真っ逆さまに加速度付けて転げ落ちているわけである。
「内的規範=個人的主義信条」と言われても何のことやら見当も付かない、という「根っからの外道ども」のために、我が個人的主義信条のうち「特に會津っぽいやつ」だけを取り出してまとめた<誠賢十箇条>を下に掲げておく:
■一)礼には礼を返せ。非礼に非礼を返すな。
■二)守れぬ約束はするな。守れぬ法を放置するな。
■三)法や立場を笠に着るな。むしり合わずに支え合え。
■四)助けが要るものを、見て見ぬ振りはするな。
■五)強いものすがりは、弱い者いじめの裏返し、と知れ。
■六)心の富を貶めてまで、懐の富を増そうとするな。
■七)人への根源的信を失うな。他人様の信を裏切るな。
■八)故ある意地は張り通せ。故なき意地は張り倒せ。
■九)旧きを誇らず貶さず、新しきを驕らず拒まず、ただ相応しきを尊べ。
■十)今あるものも常ならず。無常の刹那の有り難みを知れ。
■ONE) Pay courtesy for courtesy. Never pay discourtesy for discourtesy.
■TWO) Make no promise you can’t keep. Leave no rule unamended that can’t logically be followed.
■THREE) Play no tug of war on the strength of law or position. Resort to mutual support, not to mutual plunder.
■FOUR) Never turn a blind eye to someone or something in need of help.
■FIVE) Remember: depending on the strong is the reverse side of stamping on the weak.
■SIX) Never try to thicken your purse by thinning down your wealth of the heart.
■SEVEN) Never lose basic trust in others. Never betray the trust others put in you.
■EIGHT) Stay dogged when you reasonably should. Slap the dogged who reasonably shouldn’t.
■NINE) Be not proud or contemptuous of oldness, do not boast nor loathe novelty, just soberly appreciate adequacy.
■TEN) What is here is not here to stay. Thank all the more for what happens to be here in this fleeting world.
・・・いかがかな? これを見て「なぁ~にをエラそうに!」とか心の中で叫んだアナタ ― その反発が「!自分は外道!」の動かぬ証拠品なのだという恐るべき現実を弁えて悔い改めぬ限り、アナタに「人間的幸せ」なんてあり得ませんよ・・・ま、「外道だらけの大都会でのムシリ合いライフ」でせいぜい「懐の富」を増やしまくっては、時折「金食いリゾートでのおもてなし散財」だの「恵まれない人々へのささやかな寄付」だの「ネット上でのイイ人ゴッコ」だので今にもコワれそうな精神のバランスを取るだけのヤジロベエ人生、続けるこったね ― 「心の富、ゼロ」の我が身への「正体不明の不安感・不信感」に死ぬまで苛まれ続けながらね・・・
・・・今の東京(に限らぬいわゆる「日本の大都会」)で「人から人へのあるべき振る舞い」なんてものが構造的に成立しない理由としては、「内的規範(=個人的主義信条)」を「外的規範(=集団・社会の禁則)」で代替しようとする「外道を量産するばかりの道徳的アウトソーシング」以外にも、実に即物的なもう一つの事情がある ― 「人・物・金」があまりにも多くなりすぎると、それはもはや「人」・「物」・「金」としての本来の価値を失って「単なる数」へと消え入ってしまうということである。何千万円もの札束を日常的に扱う銀行員にとって、「万札」なんてただの「紙切れ」である。「何億円・何兆円」といった「身の幅一杯の経済感覚では扱いきれない大金」を帳面の上で右から左へ動かすだけで金儲けする「FINTECH(財テク)」にうつつを抜かしている人間たちの金銭感覚の麻痺はもっとヒドいもので、連中はその「マトモな金銭感覚(&人間的感覚)喪失」の罰を様々な形で(自業自得で)受けることになる。「フォロワー数何十万人」を抱えて御満悦の「ネットインフルエンサー」が、その膨大な数のフォロワーと「人と人として」向き合っていますなんぞとホザいたら「こいつ、本物のバカだな」と嘲笑されるだろう(ま、おおっぴらに嘲笑したら「ネット炎上」のつまらぬ火種になるだけだから誰も口にはしないだろうが・・・) ― 増えすぎた「人・物・金」が「単なる数」へと転落してしまう限界点を、今の東京あたりのダメ都市はもうとっくに踏み越えてしまっているのである。相手が「人」として存在しない「ネット空間」、あらゆるものが単なる「電子端末上で見る情報」、「具体」を持たぬ「抽象体」として認識されるだけの「ヴァーチュアルスペース」なんぞは、踏み越えるも踏み外すもなく、最初から「外道」の世界である ― だからこそ、福島県のような「閑散」を基調とする地方都市に於ける「生身の人間」の「希少性ゆえの貴重性」は、自分のような「都会への幻想を抱かぬ冷めた都会人」にとって、得も言われぬ魅力を持っているわけである。
・・・上に紹介した女店員が言語道断の「外道の振る舞い」を平然と演じられるのは、件の「大手メガネチェーン」という組織自体が「大都会化」しているせいである。そこはまるで大都会の盛り場か映画館のようなもの、「人は(従業員も客も)来てはまた去る一瞬の泡のごとし」というのがこの種の「巨大チェーン店」の構造的特性であるから、「あぶく」でしかない相手に対しては何の敬意もなく、そこは「職場」というよりは「狩り場」であり「遠征先」でしかなく、そんな場所での振る舞いは「旅の恥はかき捨て」の感覚で「仁義なき外道のむしり合い」へと堕して行き、そんな状況に対して誰も文句を言わない ― 自宅の便所をクソ・ションベンまみれのまま放置して平然としていられる人間はいないが、公衆便所であればいくら汚しても平気、というのと同じことで、「どうせすぐまた転勤なり転職なりでおさらばする<仮の狩り場・稼ぎ場>」でしかない「大都会のごとき職場」では、例の女店員がやらかした横取り営業みたいな「外道の振る舞い」もやりたい放題 ― 「それをすれば以後その職場には肩身が狭くていられなくなる」という形で自らの問題行動を戒めるブレーキとして作用するような「ホーム感覚」は存在せず、「何でもかんでもやりたい放題のアウェー意識」が従業員のモラルを低下させる ― 会社側では様々な「縛り」を課して、そうした「乱れ」を抑制しようとするが、そこに「働く職場は我が家も同じ・・・だから、穢れた振る舞いはしてはならぬ」という自制的倫理観が欠落している以上、何をどうしようが結局「旅の恥をかき捨てまくる従業員」のまき散らす悪弊は止めようがない。
・・・会津若松のような地方都市には、大都会では構造的に成立しない「おらが里」のホーム意識が自然に根付いているので、「うちの庭先で倒れてる老人」がいれば黙って見過ごしたり110番/119番任せにしたりはできないわけである。このあたりの「当事者意識」を自然に発揮できる街とそうでない街の違いは、結局、そこを流れる「人・物・金」の総量の差なのである ― あまりに多すぎれば、それらはすべて「単なる数」への転落を免れない ― 地方都市側としては「都会の豊かさ」に憧れるかもしれないが、「質が消え、数へと成り下がる」限界線を踏み越えてしまった地方都市の辿る道は、実に惨めなものである ― 「人から人へのあるべき振る舞い」がとうの昔に失われている東京あたりとは違って、最近にわかに「インバウンド旅行客の人気スポット」やら「キテる観光地」やらへと成り上がったばかりの地方都市では、つい最近まで成立していた「人と人のマトモな関わり合い」のブザマな喪失を、誰もが肌身で感じるはずだから・・・
・・・会津には、そういう惨めなモラルの転落劇など決して演じてほしくない ― 今日のような「助けが要るものを見て見ぬ振りはしない/できない」会津っぽの心根をまざまざと見せられた後では、なおさら強くそう思う・・・けれども、観光都市である会津若松が今のように外来観光客の少ないままでいていいはずもない・・・「人・物・金」が「単なる数」への質的転落を演じない範囲内で、今の会津の人気のなさをどうにかせねばなるまいな・・・
・・・とかなんとか「会津の民」でもないこの之人冗悟(のと・じゃうご)が真剣にそういうことを考えたくなるのは、会津若松という土地そのものに「やればできる素地」が豊富に眠っているから、ということもあるが、何よりもまず今日のようなこの地の人情が心に沁みる体験あればこそ・・・そんな自分の思いも、どうやら「片思い」に終わりそうな気配濃厚なんだけど・・・
・・・会津の人情にほのぼのと温もる心を抱えつつ、ギラギラ太陽にしばしおさらばして喉と胃袋を満たすべく、「野口英世青春通り」から「神明通り」へと抜ける「北小路通り」に沿ったところにある喫茶『蔵』の二階に身を落ち着ける・・・隣の席に後からやってきた自動車旅行の年配夫婦と、さっき経験した「困ってる御老人を見過ごせない会津の人々」の話やら何やらの雑談に花が咲く ― 会津若松には(今のところ)街そのものに見るべきものがあまりないので、この街の旅行者にとっての最大の魅力はやはり「人から人へのあるべき振る舞い」という(都会生活ではなかなか味わえないというか忘れ去られている)「無形の心の温もり」ということになるだろう ― この御夫婦との何ということもない会話もその一つ ― ここは「イベント」だの「ショッピング」だのではなく、「人との触れ合い」を売り物にすべき街なのだ・・・と、自分はそう思う・・・
・・・のだが、そんな会津若松にあって(現状)唯一「街そのものの魅力」で旅行者を引き寄せることができる場所がある ― この後で向かう予定の「七日町通り」である。
平日(水曜日)午後4時近くのこの通りには、観光客とおぼしき人影はまばらだが、人通りそのものはそこそこあって、街並みを隙間なく埋め尽くしたお店の数々も(ほぼ全店)開いているので、「寂れた地方都市」のマイナスな印象は微塵もない・・・通りに並ぶお店の商いも「昔ながらの由緒」を感じさせるものばかりで、「きちんとした存在理由」のあるその店構えには、日本の各所に見られる「金太郎飴観光地」の(どこもかしこも判で押したように似たような店だらけの)溜息を誘うばかりの没個性ぶりとは、別格の風格がある。
かつてはこの「七日町通り」も(三軒に一軒が空きテナントという)シャッター商店街だったという・・・その復活のために1994年に「七日町通りまちなみ協議会」を立ち上げ、30軒もの空き店舗に新たなテナントを入れて今のような街並みを復活させたという話だから、新たに導入すべきお店のコンセプトに至るまで、それはもうじっくり考え抜かれて練り上げられた「大正浪漫の香る街」なわけである。
会津若松駅前から七日町通りへと客足を運ぶ「まちなか周遊バス」も走っていて、その名前は「ハイカラさん」 ― 1987年の南野陽子主演映画(というか阿部寛の俳優デビュー作)の『はいからさんが通る』を思い浮かべずにはいられないネーミングである ― 2001年デビューのこのレトロなボンネットバスの「あねさま」には、2007年からは逆方向へと走る「あかべぇ」(モチーフはもちろん会津のシンボル「赤べこ」)という「弟分」も加わって、「徒歩で回るには広すぎる会津の街」を走り回っているようだ。会津の街を「歩き倒す」ためにやってきた自分はまだこのバスには乗ったことがないので、実際どれくらいの乗客数があるのかはわからないが、この「七日町通り」の歩道が賑わいを見せるのは、「会津若松駅前」から走ってきた「ハイカラさん」が「七日町駅前」で観光客をわんさか降ろしたその直後であろうことだけは見当が付く ― 今の時間帯はその「バス下車乗客繰り出しタイム」からは外れているのかもしれない・・・少なくとも、自分のように「会津若松駅」から「大町通り」を十五分間かけて歩いた末に『ホテル大阪屋』と『昭和なつかし館』と『白木屋(しろきや)漆器店』の角を曲がって「七日町通り」を十分間かけてその街並みを十分鑑賞しながら歩く、なんてゴクロウサマな観光客はほとんどいないようである・・・まぁ、今日のこの真夏のような六月の太陽の下では、そういうヘンテコな旅歩きをしてみようなどというヘンなヤツは(自分以外)一人もいないのが当然(&安全)だろう・・・「ハイカラさん」に乗って七日町を訪れた観光客も、あまりの暑さに音を上げて街道筋のあちこちの茶店へとみんな逃げ込んじゃってるのかもしれない・・・
・・・何にせよ、気軽にヒョイヒョイ入れるお店が通りに並んでいるのは、良いことだ ― 「大町通り」や「神明通り」じゃぁ、開いてる店を探すのも一苦労なのだから ― お店もまばらな商店街にはお客も立ち寄ってはくれない、お客が立ち寄らない商店街からはお店も逃げてゆく ― 「客を呼ぶための試み」と「店を増やす&定着させるための企み」とは車の両輪、後者に手を付けずに前者だけに終始する「イベント屋」なんて、今の会津若松には百害あって一利なし ― 必要なのは「恒常的に客足を呼び込める魅力的なエリア」へと会津若松の街全体(「七日町通り」だけでなく、「会津若松駅」から「大町通り」⇒「野口英世青春通り」⇒「神明通り」⇒「城前国道118/121号線」を経て「鶴ヶ城」に至るまでの街道筋のすべて)を作り替えること ― 「単発のイベント」ではなく「常設のハードウェア」の魅力で「客足」を呼び込み、その客足によって「お店」を商店街に再び呼び込み定着させること、なのである・・・
・・・そのための「会津若松《復興》四案⇒六案」なのだが・・・こっちに必要な「中身を開いて見てくれる会津っぽ」が(これまでのところ)「ゼロ」というのでは、この之人冗悟(Jaugo Noto)/合同会社ズバライエ(ZUBARAIE LLC.)と会津との間には何の「縁」もなし、我が「福島行脚」もこれにて「運」の尽き・・・ということに、どうやら、なりそうである・・・
・・・さて、我が「七日町通り」行脚の終点は、「ゲストハウスなかやすみ」の女性オーナーが七日町駅前に開いているフィリピンのパンのお店の「Bakery&Cafe basket(ベーカリーカフェ バスケット)」。根っからの「米人間」の自分は、「パン」にはあまり魅かれるものがないのだが、二泊三日のお宿を(格安料金で)お借りしたご縁の延長線上で、「七日町通り」徒歩行脚の終着点にあるこの駅前のお店に立ち寄らないわけにはいかないだろう・・・店内のスペースをパンの入った透明なショーケースで3:1ぐらいに仕切ったシンプルな作りの小綺麗なお店に入ると、お客さん用のスペースには女性客が二人してテーブルを囲んで談笑している。お店のカウンターの向こうでは、例の小柄で物静かな女性オーナーともう一人の女性スタッフが笑顔で迎えてくれる ― オーナーの女性がこちら七日町のパン屋さんのカウンターに立っている時は神明通りの「ミニ・バスケット」のほうはお休みというパターンのようだ。スタッフ用スペースの隅っこのほうでは、ちっちゃな(たぶん、幼稚園児の)女の子がこっちに背を向けて立ったままスマホかタブレットか何かを一心にいじっている。「あれが、このお店の”副店長”さん?」と尋ねると、「いいえ、あの子は”皿洗い店長”です」との答え。幼稚園児でもう皿洗いのお手伝いができるなら立派なものだが、今はたぶん目を皿のようにしてスマホかタブレットのスクリーンに見入ってる最中みたいだから、お邪魔をしちゃ悪いので、「こんにちは」とごあいさつしたい気分をググッと飲み込んで、とりあえず何か冷たい飲み物でも注文してお店の端のテーブルにつく・・・たしか、甘いケーキと南国風ドリンクを注文したと思う(後からまた別のフィリピン風の飲み物も追加したと思う)のだが、今振り返っても何を頼んだかよく思い出せない ― それぐらい、このお店に辿り着いた時点でもう、頭も身体も相当ヘタっていたのである ― そりゃそうだ、ゆうべは(他のゲストのいびきやらせきばらいやらで)ろくすっぽ寝てない上に、午前中に「会津若松⇒猪苗代⇒五色沼」のトレッキングツアーを6時間、トンボ返りしたその後は「自転車転倒おじいちゃん救出会津っぽリレー」をメインイベントとする街歩きを(この炎天下)もう2時間以上も続けてきたのだから・・・もし辿り着いた先が「七日町駅前バスケット」ではなく「神明通りゲストハウスなかやすみ」だったなら、二階の二段ベッドにそのまま倒れ込んで長い午睡(あるいは、翌朝までの就眠)へとなだれ込んでいたことだろう・・・が、ちょくちょくお客さんも入ってくるこの小綺麗なパン屋さんのフロアの片隅で、むくつけき大男がテーブルに突っ伏して居眠りこいてたんじゃぁ営業妨害もいいところなので、ノートPC取り出して「会津若松《復興》四案」関連へのレスポンスが相変わらずゼロのままなのを再確認したり、明日向かう予定の「大内宿」関連の情報をチェックしたり、とにかく何やら創造的な仕事に集中している体を装いつつ、時折目を閉じては睡魔と程良く折り合いをつける仕儀と相成った。カップのドリンクのフルーツ系の内容物をストローで吸い上げる作業に意識を集中することで眠りの世界とこっちの世界をかろうじて行き来しているウツラウツラ状態では、お客さんの切れ間にオーナー女性から「会津若松のインバウンド旅行客事情」を聞き出そうという事前の目論見も何もぜ~んぶ夢とうつつの向こう側・・・そんな感じで、けだるく心地よい午睡未満のボンヤリ休憩で午後5時までお店の椅子を暖めた末に、オーナー女性に(明日早朝にはチェックアウトする旨伝えて)お別れの御挨拶をしてから、再び「神明通り」方面へと歩き出す。
今回の会津若松の旅の締めくくりは、前回(4/19)にもお世話になった居酒屋『十六夜(いざよい)』・・・その直前に腹ごしらえのために「野口英世青春通り」のとあるお店(敢えて名前は伏せておく)で注文した例の会津名物「ソースカツ丼」があまりにも脂っこくって大味な代物だったせいで、胃袋はもう「食べ物お断わり」状態だったので、『十六夜』ではほぼアルコールオンリー、胃が重いので日本酒も遠慮して爽やかな梅酒・サワー系のみで通す・・・それにしてもこのお店は、「神明通り」の数少ない居酒屋だけあって、いつ来ても(といってもこれで二度目だけど)お客さんで賑わっている。今回も大将の昔からの馴染みのみなさんが「十六夜開店十周年イベント企画会議」みたいな感じで実に楽しげに盛り上がっていた。その団体さんが引き上げたその後は(例によって申し訳なくも有り難いことに)大将を独り占めする形でまたあれこれと(当然、当方の「会津若松《復興》四案」も交えつつ)お話をしたり聞かせてもらったりの夜となった。
大将が語ってくれた中でも特に印象に残ったのは、「会津若松には街ごとに細かい集団がやたらたくさんあって、その足並みがまるで揃わず、てんでんばらばらに動いているので、会津若松全体としての復興という形に結び付かない」というお話・・・「頑固で保守的で人の言うことを聞こうとしない」という”會津っぽ”のイメージは、”個人”のみならず”街”にもそのまま当てはまるらしい・・・
・・・そんな会津若松にあって、かつてはシャッター商店街状態だった「七日町通り」の徒歩10分にも及ぶ長い街道筋を「大正ロマンの香り漂うレトロな街へと生まれ変わらせる」というコンセプトで地元の人々の総意を取り付けて見事復興に漕ぎ着けた例の(会津若松商工会議所会頭の)渋川恵男(しぶかわともお)氏の手腕と苦労は、やはり並々なものではないと言えるだろう・・・その渋川さんの実家は「七日町」にあって、元は会津随一の海産物問屋、今は『渋川問屋』の名前の郷土料理屋となっている・・・それだけに、地元「七日町通り」の見事な復活ぶりには、他の商店街からは「会津若松の商工会議所会頭なんだから、地元の七日町ばかりひいきせずに、会津若松全体を何とかしてくれ」みたいなやっかみの声が上がったりするらしい・・・それが事実だとしたら、実に嘆かわしいというか、救いようのない話である ― 「主体性に欠ける受身体質」の人間というものは、「自助努力による自己改善」を何もしないくせに、というより自分で自分をどうにかする見込みがまったくないだけに、「<お上>が<下々>のためにあれこれやってくれる」という「受益者意識」ばかりがいびつに肥大してしまい、「自助努力によって獲得したより良い暮らし」を他者が享受しているのを見ると「なんでアイツだけがいい思いをしてるんだ? 不公平じゃないか!」という「ひがみ根性」に走るもの ― 「会津若松全体の復興」のためには「街ごとに細分化された集団どうしがてんでんばらばらに動く」のではダメで、「有機的連合体として一つになる」のが必須なわけで、彼らが「頑固で保守的で人の言うことを聞こうとしない」という會津っぽの悪い体質を自己改善努力で乗り切って「会津若松ワンチーム」として動かない限り、何も始まらない・・・そういう主体的な「自己救済」へと動く努力もせずに、「七日町通りを生き返らせたみたいに、うちらの商店街も何とかしてくれてもいいだろうに、あんた、会津若松商工会議所の会頭だろ?」みたいな恨み言を口にしてるようじゃ話にならない ― 「何とかしてくれ!」と悲鳴を上げるんじゃなくて「何とかしなきゃ! 何とかしよう! 何をしたらいいか、誰でもいいから是非教えて!」と、そうなるのが筋だろうに・・・全然そうなる気配を感じない、というのが、「大町通り」や「神明通り」を何度も何度も歩いた(&「会津若松《復興案》」という形であちこちちょくちょくノックもしてみた)この之人冗悟(Jaugo Noto)の実感である ― この会津若松全体には「主体的自己再生努力」と「有機的連動性」が(現状では)欠けている、要するに「有機体=生き物」としての生命力が、感じられないのである ― 「生き物」なら(たとえ死にかかっていても)生き返らせることができるが、「手・足・胴体・頭・・・それに、気持ち」がバラバラ状態で転がっていたのでは、再生のしようがない・・・
・・・渋川恵男氏が会津若松商工会議所の会頭職に就いたのは「七日町再生」の功によるものだろうが、2016年から今に至るまでのその在職期間には「東日本大震災および東電原発事故風評被害」と「コロナ禍」という2つの未曾有の大災厄からの復興という最大級の難題に直面しているわけで、そちらの課題克服の難しさは「七日町再生」の比ではないだろう ― 特に、「てんでんばらばら商店街」に「有機的連動による自助努力」の気配が見えない現状では・・・そのあまりにも困難な立場への同情の意味も込めて、我が「会津若松<全体>を有機的に連動させて生まれ変わらせるための企画案(六つ)」、渋川さん(個人)宛てにお送りすることで、この之人冗悟の「福島行脚」の締めくくりとさせてもらうことにしよう・・・「飯坂温泉」とも「会津若松」とも、「縁」と「運」、どうにもうまくつながりそうにない感じなので、これ以上この之人冗悟が個人的に福島のあちこちを動き回ってノックしまくっても何も始まらないだろうが、その「復興案」が渋川さんのような「お上」の立場にある人の目に留まってそこから何かが始まるなら、それもまぁ悪くはないだろう・・・あまり「福島県人の自助努力による復興」といった感じではないのが、個人的には、気に入らないけどね・・・
とにもかくにも、「会津若松の復興案」について語るのはこれで最後なので、大事な点だけ念押ししておこう:
●「七日町通り」を「大正浪漫の香り漂うレトロな商店街」というコンセプトで復活させたのと同じやり方では、他の商店街は生き返らない ― 会津若松全体の復興を真剣に考えるのなら、「二番煎じ」は厳禁である。
●「大町通り」は、「江戸~明治」の雰囲気のある街並みが辛うじて残るものの、その時代の「商い」をそのまま蘇らせるという(「七日町通り」を模倣した)復活策は通用しない ― 「お得意さん」が戻らない街に「昔ながらのお店」だけ戻したところで「商い」が成り立つ道理がない ― 復活させるなら「レトロな旅籠街」の形にするべきである ― 「外観は江戸~明治の旅籠ふうだが、中身は現代的な快適性を備えた宿泊施設」をズラリと並べるのである ― 「会津若松駅前」にあって「會津の顔」となる街なのだから、「宿屋」が並ぶのは当然であろう?・・・それがまるでない現状は、「この街にはどうせ宿泊客なんて来ない」と最初から諦めている「会津のやる気のなさ」の証拠品である。
●「神明通り」は、現代的なアーケードを最大の特徴とする商店街であり、そこへの集客は「今は亡き4つの大型百貨店」からのスピンオフ(=おこぼれ)に依存していた・・・その集客力の源泉が(21世紀に入ってから)すべて失われた以上、今のこの商店街が求めるべきは「大型百貨店やショッピングモールの復活」ではない(客足が死に絶えた今のこの商店街に、そんなものを出店する企業があるはずがない) ― 必要なのは「神明通りそのものへと(大型百貨店のおこぼれではない形で)お客を呼び寄せる何か」である ― その「何か」は、七日町通りや大町通りのような「レトロな街並み」という外観上の特色ではなく、「宿泊を伴う形でお客さんを呼び寄せる<企画>」、それも「一過性のイベント」ではない「恒常的にお客を呼び込み続ける何か」でなければならない ― さしあたり実現可能な企画としては、当方が提案する「会津若松《復興》六案」のうちの『Patent Road Assistant:パテント道標』ならびに『寝るだけ宿泊所(shelter-inn)』があるだろう ― これらの企画が「神明通りにぴったり合う理由」が即座に思い浮かばぬようなニブい御仁には、この瀕死の商店街の再生は到底無理だろうが・・・
●<神明通り南>の十字路から会津若松最大の客寄せスポットである「鶴ヶ城」へと至る「国道118/121号線」に、「大町通り」・「野口英世青春通り」・「神明通り」のような固有名称が付いていないのは実にバカげている ― 「鶴ヶ城西出丸沿いの国道118/121号線」などというまどろっこしい呼び名しかない現状は、「この街道筋は商店街ではないから、べつに呼び名は不要」と言っているようなもの・・・だが、本当にそんなことでよいのだろうか? ― 「城前通り」とか「武家屋敷通り」とか、この通りに相応しい固有名称を付けてもらわないことには、「鶴ヶ城の城下町としての会津若松全体の有機的連動性」もヘッタクレもありゃしない!
.
.
江戸時代、参勤交代で會津と江戸の間を行き来する松平の殿様一行が立ち寄った山中の宿場町の趣が現代に至るまでそのまま残っているという「レトロが売り」の観光地だという話で、その特性上、「the air of good old Japan:旧き良き日本の雰囲気」を求めてインバウンド旅行客がわんさか押し寄せている、という話を聞いていたので、「語学屋」の自分としては訪れないわけにはいかないスポットである。
「ゲストハウスなかやすみ」では、同部屋の日本人2名がチェックアウトしていたおかげで、前夜(6/18)には「いびき・せきばらい攻撃」から解放されて熟睡できた自分は、朝の6時前にスッキリ起床、シャワールームでサッパリして旅の出で立ちを整え、二泊三日お世話になった二段ベッドに「Thanks for the nice stay & bread:素敵な滞在&パンに感謝」とメモ書きを残して、午前7時ちょうどに会津若松駅に向けて出立した。
事前にネットで調べた情報では、「会津若松駅前(07:46)~大内宿(08:36)」の直通バスがあるらしいので、駅前の会津バスのターミナルでバス乗り場を尋ねたのだが、「そういうバスはないです」との予想外の答え ― 後日改めて同じ情報を調べ直してみたら、「会津バス」で「会津若松駅前」から「大内宿入口」に行けるわけではなく、「会津バスの<会津若松駅前>から徒歩2分で<会津若松>まで行き、そこから会津鉄道に乗って<湯野上温泉:ゆのかみおんせん>まで行き、そこから歩いて6分のところに会津バスの<大内宿入口>という乗り場がある」という手の込んだガセ情報であった・・・しかも、<湯野上温泉>から<大内宿>まで「徒歩6分」などというのはまったくのデタラメ、けっこうな高低差のある5.3キロもの山道は、地図上の単純計算でも徒歩1時間半、実際車で往復した実感からすれば、とてもじゃないが歩いて上り下りできる道ではない・・・「バスで会津若松から大内宿へ行くルート」を求めている人間に対して、こういうロクでもないインチキ情報を平然と投げ付けてくるあたりが、現状の「インターネットの乗り換え案内」のブザマな現実なわけで、これを「旅人が安心して従える正しく親身な情報」へと改善するだけでもそこにはそこそこ大きなビジネスチャンスが生まれるはず・・・会津若松が「日本初のコンピュータ専門大学」たる「会津大学」との協調活動によるベンチャービジネスで不振の街を立て直すつもりなら、こうした「手つかずの猟場」を放っておく手はないだろう ― 「人のことを親身に思う街」としての会津のイメージ向上にもつながるし、現状てんでんバラバラで有機的連動性に欠ける「福島県内の観光スポットの数々」の連携的活性化にとっても、「どこそこの観光地にいついつまでに行くには何々に何時何分に乗ればいいか、料金はどれくらいか」が正しく瞬時にわかる観光客思いのインタフェースの開発は、手っ取り早い起爆剤になると思うのだが・・・まぁ、現状では「会津の民」にこそ「やる気を起こさせる起爆剤」が必要な状況みたいなんでねぇ・・・
・・・というわけで、大慌てで会津若松駅に駆け込んで、券売機横の改札の駅員さんに「大内宿まで行きたいんですが、どうしたらいいでしょう?」と尋ねると、「最寄り駅は<湯野上温泉>です」との答え。「料金はいくらでしょうか?」と尋ねると、「とりあえず190円の切符だけ買って、後は車内精算してください」とのこと ― これは先日「常磐線で日暮里から水戸までの切符が買えない」という事態で経験済みの展開である・・・が、あの時とは違って、今回はその同じ駅員さんが、190円の切符を自販機で買おうとしている自分を呼び止めて、「大内宿まで行かれるんですよね? だったら、鉄道とバスのおトクなセット料金というのもあるんで、よろしかったら<みどりの窓口>で御案内しますけど」と声をかけてくれたこと・・・
・・・というわけで(東京あたりではもう人件費節約とテナント有効活用のために次々廃止されて)滅多にお目にかかれない<みどりの窓口>に入り、受付のおねえさんと駅員さんとを交えての三者協議が始まった ― とりあえず、乗るべき列車は「会津若松(07:51)発、湯野上温泉(08:30)着」の会津鉄道で、発車時刻まではまだだいぶ余裕があることが判明・・・したのだが、<みどりの窓口>のおねえさんいわく、「湯野上温泉から大内宿まで行くバスは、接続の時間があまり良くないので、<会津鉄道+バス>のセット乗車券は・・・どうなんでしょう?」とのこと・・・駅員さんともども首をひねった末に結局出た結論は、「とりあえず、190円の切符を買って列車に乗っておいて、巡回してくる係員に車内精算してもらう時に、バスの乗車券のほうはどうするか、改めて決めたらいいと思います」というものだった・・・まぁ、ローカル鉄道の乗り継ぎに関しては、旅人よりも現地の人のほうが絶対的に詳しいわけだから、ここは言われた通りにしておこう ― 「相手のいいなりにしていたら不当に高い料金をボッタクラレる」みたいな心配は(東京でのサバイバルには必須だが)ここ会津では不要だろうから・・・
・・・てなわけで、190円の切符で会津鉄道に乗り込んで進行方向最前方の窓際の席へ・・・乗客がまばらなのは平日の早朝だからか、ローカル鉄道の日常的苦境を示すものか・・・乗務員さんは発車前にやってきてくれて早速車内精算の手続きに入る ― 「大内宿に行きたいんですが、列車とバスの共通割引乗車券があるとかいう話ですよね?」 ― 「はい。湯ノ上温泉駅前から大内宿まで行くバスとのセット販売切符があります。ただ、この列車が到着するのが(08:30)、バスの発車が(09:45)なので、かなり間が開きます」 ― 「1時間15分かぁ~・・・かなり待たされますね」 ― 「駅前からタクシーで大内宿まで行かれるお客さんも結構おられます」 ― 「徒歩で行ける距離ではないですか?」 ― 「う~ん・・・まぁ、行けないこともないでしょうが・・・あまり歩かれるお客さんはいませんね」 ― 「タクシーはラクに拾えますか?」 ― 「列車が着いた時には駅前にはたいてい客待ちのタクシーが停まってます」・・・どうやら、「バスのチケット」をここで購入してしまうのはあまり得策じゃなさそうなので、とりあえず会津鉄道で湯野上温泉まで行く分だけの料金精算に留めておいた。駅前でゆ~ったりとバスを待つか、タクシーに乗ってさっさと大内宿まで行くかは、駅に着いてから考えよう。
それにしても、会津の駅員さんも乗務員さんも、実に親切である。「鉄道+バスの共通割引きっぷ」というのは御当地が観光客向けに考案した「お勧めメニュー」のはずだから、たいていの土地でなら何も考えずにひたすらその売り込みに走るところだろうに、この会津若松では、鉄道からバスへの乗り継ぎで生じる待ち時間まで勘案した上で、「駅からタクシー、という手もありますから、ここでバスに決めてしまうのは考え物かもしれません」と誠実なアドバイスをしてくれる ― 旅人にとって、こういう誠意こそが目に見えない最高のサービスなのである・・・その無形の志の有り難みをしっかり感謝して心に刻むような本筋の旅人にとって、會津/福島は、凡百の「大人気観光地」とは別格の地なのである・・・そういう「心で感じる旅」の良さなんて、ただひたすらに「写真・ビデオに残す旅」をするだけの観光客にはわかるまいし、また、そういうわかってない連中が大挙して押し寄せたのでは折角の「心の里の會津/福島」の良さである「ほどほどの閑散感」も台無しになるから、ま、わからない連中にはわからないまま無視され続けながら、「人としてのあるべき姿を再確認しにくる旅人」だけの心の古里として永遠に存在し続けてほしいのが、会津/福島・・・というのは少々贅沢な望みかな~?・・・平日の早朝とはいえ、列車がこの空き具合じゃぁ商売としてはやっぱ苦しいはずだから、存在し続けてほしいなら「お客を呼ぶためのお手伝い」もしてあげないとなぁ・・・でも、「会津若松《復興案》」、誰ぁ~れも開いて見てくれないからなぁ~・・・
・・・深い緑の木々の間やトンネルを抜けて走る「会津鉄道」は、山を避け川をまたいで平地をひた走る「水郡線」とはだいぶ趣が違う。約40分の乗車時間は「磐越西線」で「会津若松」から「猪苗代」に至る所要時間(33分)に近いが、あちらは遠くに山々を見晴るかす平野を走るのどかな田舎の列車、こちらは山深く分け入る峡谷鉄道といった感じである。第三セクターが運営するローカル鉄道である点も、「会津鉄道」は「水郡線/磐越西線」とは異なる。路線図の上では「会津若松」から「西若松」までは「JR只見線」、「西若松」から「会津高原尾瀬口」までが「会津鉄道」となっている。東京の「浅草」から「会津若松」まで(「会津田島」で1回乗り換えるだけで)5時間以内で来るルートもあるようだ ― 終点「会津若松」の1つ前が「七日町」だから、あの街を土日祝日に賑わしている観光客たちの多くはこれで来ているのかもしれない。
・・・そんな乗客密度のかなり低い平日朝の会津鉄道にゆったり揺られて到着した「湯野上温泉」は、絵に描いたようにノスタルジックな「昔の日本の駅」といった感じ・・・屋根はなんと茅葺き、木組みの改札口を出た右側には囲炉裏を囲むようにして畳敷きの休憩所があり、左側にあるおみやげ売り場には木戸を「ガラガラ」って感じで開けて入る ― この駅で下車するお客さんの目当ては「大内宿」だろうから、それを意識しての古式な造りなのだろう。改札脇の小部屋は切符売り場と案内所を兼ねていて、中では女性三人がお茶を飲みながらゆったりくつろいでいる・・・いかにも第三セクター鉄道、といった感じののどかな雰囲気である。
・・・この駅に(08:30)に降り立った乗客は自分を含めて5組だけ ― そこそこの年配の夫婦連れ以外は全員一人旅、目指す先はたぶんみんな「大内宿」であろう。駅舎を出ると、すぐ右手にタクシーが一台、客待ちをしている。その右側にはかなり広い駐車場があり、駅舎に隣接して無料の足湯スペースがある。駅を出て左側にはトイレがあり、その先の坂を下ったところに「猿游号(さるゆうごう)」という「大内宿」行きのバス乗り場があるのだが、発車時刻の(09:45)まではあと1時間15分、駅舎の周りをざっと歩いた感じでは、山また山に囲まれたこの駅周辺をブラついても、見るべきものは何もなさそう・・・無料の足湯に浸かり続けて過ごすにも長すぎる時間だし、第一、この「大内宿」の後は「郡山駅周辺」の復興状況&商況を確認しに行く予定の自分としては、この駅前で1時間以上も無為の時を浪費している余裕はない・・・
・・・ということで、自分は一計を案じた ― 今この駅前でブラブラしている人達の共通の目的地は「大内宿」のはずだから、数人でまとまってあの駅前に停車しているタクシーに乗り込めば、割り勘で安上がりに大内宿まで着けるではないか。バス料金よりは高くなるかもしれないが、1時間以上もの時間をここで過ごすよりはずっといい・・・ということで、駅舎の周りを思い思いの方向へブラついている人達に一人一人声掛けして回ろう・・・と思ったのも束の間、駅前に停まっていた一台きりのタクシーは、一人の年輩男性を乗せてサッサと走り去ってしまった・・・ぁはは・・・何から何まで「企画倒れ」に終わるのがこの会津/福島での自分の運命のようだ・・・さりとて、このままダラダラ1時間以上もの時をこの駅前でツブすつもりもない自分は、駅舎の改札脇でお茶を飲んで談笑している会津鉄道の女性たちに頼んでタクシーを呼び寄せてもらうことにした。割高にはなるが、仕方がない。ついでに、大内宿からの帰路のバスの時刻を書いた紙片ももらった ― 「大内宿」を(10:50)に出る「猿游号(さるゆうごう)」のバスに乗れば、「湯野上温泉」には(11:10)には到着するので、(11:19)発の会津鉄道に乗って(11:57)には「会津若松」に到着、(12:20)に発車する磐越西線で「郡山」には(13:36)に到着できる。
・・・かくて、どれだけの料金を取られることになるか不明のタクシーの到着を待つ間、駅舎の周りをぶらついていたもう一人の男性にも「割り勘いかが?」の声掛けをしたのだが、すでに「猿游号(さるゆうごう)」のチケット購入済みということであっさりフラれてしまった。さっきまでいた年配夫婦の二人連れはどこかへ消えて、もう一人いたはずの一人旅の男性もどこかへブラブラひまつぶし散策に出ちゃったようなので、いずれもきっと「猿游号チケット購入済み」なのだろう・・・
・・・あれこれやたらと間が悪い我が身に苦笑しつつ、タクシーが来るまでの時間を駅舎の真ん前のベンチに腰掛けてぼーっと過ごしていると、駅前の坂道の向こうから、「バスは9時だってさ」と大声上げながら男性の二人組がやってきた。ベンチに座っている自分のすぐ前まで来たところで、「9時のバス、どこだ?」みたいな感じでバス停を探している ― こりゃぁ渡りに船かもしれないぞ ― 「大内宿に行くなら、バスの時間は9時45分だよ」とこちらが相槌打つと、「え? 午前9時だって聞いたけど」と声が返ってきたので、「バス停はあっちの坂の下だけど、あと1時間もしないと出ないって・・・そんなに待ってられないから、こっちはタクシー呼んじゃったんだけど、よかったら三人で相乗りしませんか? 三人の割り勘なら、タクシー料金もさほど高くはつかないだろうし、何よりさっさと大内宿まで行けるんだから・・・もしそっちさえよければ、の話だけど」・・・相手方の二人組は、自分の横のベンチに座って、少しばかり相談してから「じゃぁ、そういうことで、お願いします」との答え ― この春以来、福島に(三度も)来訪してあれこれ提案してはことごとく拒絶か無反応だった自分にとって、これが初めてもらった「OK」である。
相手の二人組は、片方はそこそこ大柄、もう一人は少し小柄な凸凹コンビ、千葉県のほうから来た会社の同僚だという。駅前の坂の下の方から歩いてきたのは、そっちの方にある(歩いても結構な距離がある)宿屋に昨日から泊まっていたからで、そこのおばあちゃんに「大内宿さ行くなら湯野上温泉駅前からのバスが9時に出るから」と教わったので、遅れてはならじと足早に歩いて来たらしい。ばぁちゃんの頭の中の時刻表はだいぶズレてたみたいだが、おかげでタクシー待ちのこっちとタイミングがドンピシャ、ベンチに座ってそこそこ雑談するうちにやってきたタクシーに三人して乗り込んで、午前9時ちょい過ぎにはもう大内宿の麓まで乗り付けることができた ― 帰りのバスの発車時刻(10:50)まで、2時間近く過ごせる計算である ― タクシー料金は(配車費用まで含めて)2500円、一人頭800円ほどなので、無駄な待ち時間を削れたことを思えば悪い出費ではない。例の「猿游号(さるゆうごう)」のチケットは「往復1100円」なので金額的にはそちらのほうがかなり割安だが、「料金節約」を取るか「時間節約」を取るかで考えた場合、タクシーは悪い選択ではない。
・・・というか、今回はそもそもの出発時刻の選択を間違えたようだ ― 「会津若松」を(07:51)ではなく(09:02)に出発しておけば「湯野上温泉」に(09:41)に到着して(09:45)発の「猿游号(さるゆうごう)」に待ち時間なしで乗り込めたはずだったのである ― (08:30)に湯野上温泉駅に到着する早起きのお客さんなんて、バス会社(正確には「合資会社広田タクシー」)としては”想定外”なのだろう・・・まぁ、福島県の旅にはこうした乗り換えの待ち時間は付き物だし、駅舎の脇の屋根付きの足湯に浸かりながらじ~っくりバスを待つこともできるわけだから、早く着きすぎてヒマを持て余した旅行者に対しても、「湯野上温泉は、優しい駅」と言えるだろう。
・・・ちなみに、「大内宿」の探訪を終えて「湯野上温泉駅前」へと帰るバスは(10:05)・(10:50)・(11:50)・(12:35)・(13:55)・(15:12)と、ほぼ1時間間隔で出ている。バスのチケットは「往復1100円」が基本なのだが、自分は帰路には片道だけで(10:50)発の便に乗せてもらった。料金はやっぱり1100円で、片道だからといって550円にはならなかったが、帰りもまたタクシーを使うとなれば2000円は取られるのだから、タイムパフォーマンスとコストパフォーマンスのバランスからして、これが一番合理的な選択だったと思う ― それもこれも、うまいことあの凸凹男性二人組との相乗りで往路を安く上げられたからこその展開であって、自分はこういう「人との巡り合わせ」の運にはかなり恵まれているようだ・・・「提案受容運」のほうは(今回のタクシー相乗り案を除き)総崩れのグダグダ状態だけど・・・
・・・さて、そうして「旅は道連れ」で乗り込んだタクシーの窓の外に展開する景色は、これまでの「福島行脚」のどの場面よりも魅力的な「秘境探訪」の趣・・・目指す「大内宿」の入り口で下車して見上げる山々は、木々の緑の色が絶妙に異なる心躍るような晩春のグラデーション・・・見下ろす山裾にも可憐な季節の花々が自然な彩りの絨毯を成していて、山々には「ホーホケキョ!」の声がこだまし、水辺ではかじかの鳴き声が心安らぐBGMを奏でている・・・絵に描いたような「美しき日本の山里」の光景と音色が、ちっともわざとらしくない自然な姿で、そこに広がっている ― こりゃあ、ガイジンさんに人気が出るわけだ。日本人だって、この光景を前にして郷愁に胸躍らせずにいられる者は一人もいないだろう ― まだ宿場町に足を踏み入れてもいないけれど、入り口から見るこの素晴らしい自然の情景だけでもうすでに100点満点以上の満足感 ― !来てみて本当によかった! ― 来訪者が(平日の早朝だからか)まばらなのも、実によい感じである。
・・・宿場町へと向かう一本道は、なだらかな上り坂になっている。平日の午前9時台では開いてるお店もなかったりするのではと思ったが、多くのお店がちゃんと開いている。アスファルトも石畳もない「昔の学校の校庭」みたいなジャリジャリした質感の土の道を、ザッザッと音を立てながら前のめりで歩くうち、自然と早足になってきた自分は、タクシー相乗りのご縁のあった凸凹男性二人組に別れを告げて、左右に並ぶ茅葺き屋根の家々(というか、店々)に交互に視線を走らせながら、上り坂の行き着く先まで一気に辿り着いてしまった ― 麓の駐車場からここまで歩くのに、ものの10分とかかっていない。頂上からは左右に道が折れるT字路になっていて、両方ともそこそこまで歩いてみたが、観光客向けの施設があるわけでもない。上り坂の終わりには小高い場所からこの宿場町の全容を眺められるスポットもあって写真撮影には打って付けだと聞いていたが、自分は「旅の情景は心のスケッチブックに残すだけ」と決めているので、これ以上高い場所には登ることなく、T字路の真ん中からなだらかに下る大内宿の家並みを見下ろすだけ。
・・・観光客の数はさほど多くはないが、それでもこれまでに自分が訪れた飯坂温泉・会津若松市内・猪苗代湖・五色沼といった福島県の有名どころのどこよりも客足が多い。平日の午前9時台でこの数なのだから、土日祝祭日にはさぞや賑わうことだろう・・・左右に居並ぶお店の数々は、それぞれが別々の物品を商っているわけでもなさそうなので、観光客としては、何となく気を引かれたお店に立ち寄って、土産物を買うなり、名物の「ねぎそば」を味わうなり、といった形で行き当たりばったりの巡り合わせを楽しむ旅になる感じである。
・・・帰りのバスの時間までは約100分、持て余すことも足りないこともない、絶妙な持ち時間・・・湯野上温泉駅前で(09:45)まで待って「猿游号(さるゆうごう)」で来た場合の「大内宿」到着時刻は(10:05)だというから、その場合の大内宿滞在可能時間はわずか45分、麓の駐車場から宿場の端まで歩くのに往復15分~20分はかかるので、落ち着いて過ごせる時間は30分足らずという計算になる ― やはり「タクシーでGO!」は正解だったようだ・・・まぁ、大内宿から湯野上温泉へと戻る「猿游号」は(11:50)にも(12:35)にも出ているのだから、その気になれば宿場滞在時間はいくらでも伸ばせるわけだが、自分の場合はこの後「郡山駅前行脚」へのハシゴ旅が控えているので、今日のこのタイムテーブルはベストの選択だったと言えるだろう。
・・・この大内宿へは、自分の母も(まだ幼稚園児だった姪っ子と一緒に)バス旅で来訪している。「イチゴ狩り」だか「サクランボ狩り」だかのバスツアーだったらしいが、旅先では必ずキーホルダーを買って帰るのが常だった姪っ子は、居並ぶ店々(ぜんぶ開店なら50軒近く)のすべてにキーホルダーが置いてあることに大興奮して、「ばぁば、あっちのお店にもこっちのお店にも、ぜぇ~んぶキーホルダー売ってるよ!」と叫びながら、あっちこっちチョコマカと目移りしながら坂道を駆け上がったり駆け下りたりしていたらしい。大内宿の周りにはイチゴやサクランボを栽培している場所はないみたいなので、どこか近隣の農園でそういうツアーをこなしつつ、行きがけの駄賃にこちらの大内宿までバスがお客さんを運んで来たといったところなのだろう ― 近くまで車まで来たのなら、立ち寄らずに帰るにはあまりにも惜しい場所だからね、ここは。
・・・てな感じで、坂道の上の端まで登り詰めて宿場の全容をざ~っと確認した自分は、店先に並ぶ品々ではなく、お店の中や周りで動いている宿場の人に注目しながら、坂道を下ることにした。
・・・三角の茅葺屋根に向かって長い剪定鋏を伸ばしてはチョッキンチョッキンしているおじいさんを見つけ、作業の合間で一休みしているタイミングを見計らって「ごくろ~ぅさまですぅ」と声を掛けてみる ― 「屋根の上に生えてる草とか花とか、そうやって取るんだねぇ~」 ― 「鳥が種運んできて、あれこれ生えちまうんで」 ― 「やっぱり茅葺屋根の手入れって、大変なんだ~」 ― 「茅そのものも、ちょくちょく入れ替えるし」 ― 「どれぐらいちょくちょく?」 ― 「この屋根の茅は、4年ぐらい前に葺き替えた」 ― 「そんなに新しいんだ?」 ― 「いろいろ手ぇ掛かる」 ― 「ごくろうさまです~・・・お話、どうもありがとうございました~」 ― 近代建築の屋根なら、作ったらあとは取り壊すまでそのままだが、昔ながらの日本の茅葺屋根は、一度作ってそれっきりというわけにはいかない。その定期的な作り替えは大変な重労働なので、一家総出でも手が足りないから、村ぐるみの共同作業になる。そうして誰もが誰かの手を借り誰かに手を貸すサイクルを繰り返す中で、村全体の有機的統合体としての連帯感が生まれる ― 逆に言えば、地域全体が一つの有機体(=生き物)としての連動性を失った時、「茅葺屋根の里」の存続もまた不可能となる ― 人々が「群生」してはいても「連帯」していない現代社会にあって、てんでんバラバラの孤立的生存様態の中でめいめい好き勝手にむしり合って生きている都会人が、この「大内宿」や「白川郷(しらかわごう)」の姿に心惹かれるのは、その「レトロな外観」のせいばかりではない ― 自分たちの周りではとうの昔に失われてしまった「人と人との真の連帯」が、これらの古い里ではいまだにちゃんと受け継がれているのを(本能的に)感じ取るからこそなのである。
・・・宿場の両脇の家々と道の間には掘があり、流れる水を長い柄杓で掬っては路上に撒いている人がいる。目と目が合ったので「こ~んちゎ!」と挨拶すると、あちらも(多少ぎこちない感じで)「こんにちは」と返してくる。お客が大勢詰めかける観光地にしては、あまりこなれていないその感じは、「會津っぽ」というよりは「大内宿」の特色なのかもしれない ― 「内輪での一体感」が強くなければ存立不可能な「茅葺屋根の地域共同体」では、その輪の外からの「こんにちは」の声に対する「こだま」にも、離合集散の激しい一般的な商店街みたいな反射的で機械的な愛想の良さは籠もらない、といったところなのだろう ― この感じは、自分にとっては実に好もしい「朴訥さ」だが、「地域の絆の強さの逆説的証明としての、対外的な愛想のなさ」の魅力を心底愛でるだけの知性・感性のあるお客は(特に、表面的な体裁を取り繕う技芸ばかりイビツに発達しまくった都会人の間には)あまり多くはないだろう。お店の前にあるお花に水をあげているのかと思ったが、実際は、砂利道に砂埃が立つのを抑えるための水撒きなんだそうだ・・・そういえば昔、自分の高校のグラウンドでもスプリンクラーで撒水してたっけ・・・でも、そうして校庭が機械で自動的に水撒かれてる間は生徒たちはみんな校舎の中に避難してた ― 人の手で、通行人を上手に避けながら水撒きして砂の舞い上がるのを避けるの図は、昭和の昔から生きてる自分にとっても、実は初めて間近に見る情景だったりするわけだ。
・・・そうしてただ見て歩くだけでも物珍しいこといっぱいの大内宿だが、そろそろ自分も観光客らしい消費行動でこの宿にささやかな貢献をすることにしよう・・・土産物を買い込んで荷物を重くするつもりはない自分としては、この大内宿での目当てはもっぱら「ねぎそば」、ただ飲み食いするだけではつまらないので、お店の人との雑談を通じて大内宿のあれこれについても感じ取れればありがたい・・・ということで、奥まで素通しの座敷にお客が一人もいないお店を見つけ、端っこに座って団扇をゆらゆらさせている店番の女性に向かって「ねぎそば、やってます~?」と尋ねると、「はい、よかったら中の座敷へどうぞ」ということなので、座敷の一番外側、お店の商品が並んでいるすぐ内側で、店番のおねえさんのすぐそばの食卓に腰を下ろし、道行く観光客の姿を眺めながら、噂の「太くて長い一本のネギが乗っかった、日本そば」を食べてみる。箸の代わりにネギ一本で蕎麦を食べるなんて、宴会の一発芸みたいなもんで実際にはすぐさま挫折してお箸のお世話になるだろう、と想像していたのだが、実際やってみると意外と簡単に食べ切れてしまってビックリした。まぁ、「そばもつゆもちゃ~んと音を立ててズルズルすする」という由緒正しき日本の作法を「!不作法!」と感じるような無粋な日本人や外国人には逆立ちしたって出来ない芸当だろうが、「音も立てずにお上品に麺類食うヤツなんざ、自分の仲間たぁ認めねぇ」ってクチの江戸っ子にゃぁ至極自然にすすり切れちまうこの「ねぎそば」は、食い方の作法もオツなもんだったが、何よりもそのつゆの味が絶妙で、濃すぎず薄すぎず、この日のような暑い夏の昼飯にはまさにもってこいの水分&塩分補給、最後に残った細かなそばの糸ごと、ゴックンゴックンと喉を鳴らして一滴残らず一本残らず飲み干してしまった ― それぐらい美味なつゆだったのであるが、飲み干した後で大事なことを思い出した ― そばを掬い上げる箸代わりに使った太くて長いねぎ、食後にこいつをかっ食らうにゃぁ、つゆに浸してふやかして味付けしねぇことにゃぁ堅くていけねぇってこと・・・結局、ねぎの先端のほうは終始つゆの中に突っ込んでたせいでいぃ塩梅に塩っ気が染みてムシャムシャいけたが、そこから先は湿りっ気も塩っ気も何もないただの苦いネギのまんま残っちまったんで、ジャキジャキ音立ててかじってるうちに、虫歯を抱えた出来損ないパンダにでもなったような気分になってきて、ネギ全体の4分の3以上も残して無駄な抵抗はやめにした。
・・・言い忘れてたが、お店の名前は『大和屋』さん ― 坂道のてっぺんから数えて五軒めぐらいにある左側のお店である。お店の商品の陳列棚のすぐ内側に座って、そこそこ盛大な音を立てながら長いネギ使ってそばをかっこむ自分の姿は、客寄せになったのか営業妨害になったのか、店先に並ぶ土産物を見に来るお客はそこそこいたが、自分がそうして通りに面した座敷にあぐらかいてくつろいでる間じゅう、このお店の中に入って来る他のお客さんは一人もいなかった・・・それをいいことに、店番のおねえさんとも、ねぎそば持ってきてくれたおにいさんとも、そこそこ雑談が楽しめた ― なんか、福島県じゃぁこのパターンばっかだな。べつにこっちはお客が来なさそうな店を殊更選んで入ってるわけじゃぁないんだが、自分が入ったお店では、なんのかんので最後には必ずこうした「閑散時の雑談タイム」にありつける・・・お店の人とあれこれ話し込んでるお客の自分が、別のお客がお店に入るのを邪魔する「疫病神」に成り下がってなければいいんだが・・・とにかく、自分が『大和屋』さんの座敷を出るまでの間、他のお客は一人も入って来なかった・・・まぁ、自分がお店を出たのは午前10時30分、昼飯時にはまだまだ早い時間帯だったので、あと1時間もすればお腹を空かせたお客がわんさか「ねぎそば」食いにやってくることだろう。
・・・それにしても、今年の夏は来るのが早すぎる ― まだ六月下旬、梅雨明けもしていないのにこの暑さはないだろう・・・ここ大内宿は冬には大雪に閉ざされる里だというし、ここに来るまでには山道をかなり登ってきたのだから標高が高い分涼しくてもよかろうに、実際には「山々に囲まれた盆地」という特性から「冬には寒く、夏は暑い」ということになるようだ・・・にしても、今は六月、山々の色合いも「晩春」なのに、照り付ける太陽だけが「!夏!」を叫んでる ― 季節がかつての日本の四季を思いっきり無視するようになってきた今の世で、大内宿が「旧き良き日本の風情」を守り通すのは、さぞや大変なことだろう。
・・・この『大和屋』の座敷には囲炉裏もあり、冬場にはおそらくストーブも出てくるのだろうが、この吹き抜けの座敷に本格的な夏がやってきたら、どうやって涼を取るのだろう? 「エアコンの室外機なんかがお客さんの目に付く所にあったらダメなんで、夏は大変です」とお店の人が話していたが、ということは、目立たぬ形で冷房機は稼働させるのだろうか? それにしても座敷は吹き抜け、密閉されていない部屋では冷房のしようもないはずだから、そうなると(昭和の夏よろしく)扇風機の出番ということになるのか? 江戸時代の会津藩御一行様を夏場にお迎えした時は、盆地の暑さをどうやってしのいでいたのだろう? 氷室で秘蔵した巨大な氷を座敷に置いて団扇で扇いだ冷風で殿様を涼ませた、とか?・・・とか言いつつも、この日の午前中は、時折座敷を吹き抜ける自然の風が実に心地よくて、帰りのバスが出るまでの間ず~っとここで長居をさせてもらったのだが、「こういういい風がずっと吹いてくれれば楽なんだけどねぇ・・・」と言いつつ田舎っぽい和服で大きな団扇をゆったりくゆらせるおねえさんたちの身に、「近頃の日本の夏」はかなり厳しいようだ。
・・・道行く観光客の数は午前10時を回った頃から増え始めた。語学屋の自分としては「英語圏(=欧米)からの観光客」の数が気になるのだが、この日の午前中はほとんど目にしなかった。服装や立ち居振る舞いの賑やかさから中華系とおぼしきインバウンド客はそこそこ混じっているようだが、「大内宿の人達がカタコト英語でガイジンさんをおもてなし」の図は見られなかった。日本人の親子連れが思いの外に多いのは、「この国の原風景」を我が子に見せたいという親心なんだろう。
・・・福島県のあらゆる観光地の御多分に漏れず、ここ大内宿でもやはり来訪者のほとんどは自動車で麓の駐車場まで乗り付けているようで、「湯野上温泉駅前」まで行く(10:50)発のバス「猿游号(さるゆうごう)」に乗り込む鉄道旅行者は、5~6人しかいなかった・・・その数少ないバス乗客の中には、朝のタクシーに相乗りした例の凸凹男性コンビのうちの大柄な方も含まれていた ― 小柄な方の男性は、行きの山道で見た木々の緑や山々の趣にすっかり魅せられて、「帰りはこの道を歩いて下る!」と決めちゃったらしい。大内宿の下り坂の途中で再び出会った時からずっと、「山道は大変だよ。バスで帰ろうよ」 ― 「いや、下り坂だから大丈夫」 ― 「疲れるし時間かかるよ、バスで降りようよ」 ― 「いや、タクシーで登って来た感じでは大丈夫」 ― 「バスで楽して湯野上温泉まで行って、足湯に入ろうよ」 ― 「いや、あの山道の素晴らしい景色を味わいながら歩きたい」といった問答を繰り返していた二人組だったが、一足先に麓の駐車場まで下りてお手洗いで用足しとかしてから県道329号の坂道をちょっと登ったところにある「猿游号(さるゆうごう)」のバス停に着いた自分がそこに発見したのは、大柄な方の男性のみ ― 小柄な相棒は結局やっぱり歩いて山道を下ることになったという。
・・・バスで山道を下ってみると、対向車線を登ってくる車の数が、朝方タクシーで来た時よりもだいぶ増えている ― 大内宿の客足は、これから午後にかけて上り調子ということだろう。山を下る車の数がどの程度なのかはよくわからない ― 追い越しはまず不可能な狭い山道なので、このバスの後方にはけっこうな数の車が連なっているのかもしれないが、バスの前方の下り車線は空いていて、スイスイ下って「湯野上温泉駅前」に到着したのは、予定の(11:10)よりだいぶ早い午前11時そこそこ。今回はそうしてスムーズだったが、お客さんが大挙して訪れる繁忙期には、たぶんこの山道も車が数珠つなぎ状態になるのだろう・・・そうなると、帰りの列車の発車時刻に間に合わなくなる事態も考えられるから、やっぱり大内宿の旅には「最初から予定をキッチリ詰めすぎない心構え」が必要そうだ ― 予定していた列車に乗り遅れたとしても、駅舎横の屋根付き足湯で「予定外の1時間のプチ温泉体験」が無料で楽しめた、という風に心の切り替えができる旅人でない限り、「会津鉄道で行く大内宿の旅」を満喫するのは(今日のように比較的空いている平日の午前中以外では)難しいかもしれない・・・
・・・さて、そうしてスイスイ麓まで帰り着いてしまった凸凹コンビの大柄な方の男性は、この先、かな~り長い時間この湯野上温泉の足湯に浸かりながら、歩いて下りてくる小柄な相棒を待ち続けることになるようだ。車で飛ばせば10分少々の下り坂とはいえ、5キロを越える道のりを歩いて下りれば2時間近くはかかるだろう。道幅が狭い上にカーブが続く山道では歩行者と自動車の接触事故も心配なだけに、待つ身としては「足湯でくつろいでのんびり気分」というわけにもいかなそうである・・・聞けば、その小柄な男性はこの春先に脳卒中で倒れて六月に職場復帰したばかりだというから、この山深い会津の旅は一種のリハビリ道中のようである。言葉も動きもそういう病み上がりには見えなかったが、年齢は既にもう還暦を越えているという彼としては、「倒れても、立ち上がって、自分はまだまだやれる!」ということを証明するためにも、眼前に広がる「木陰が続く下り坂の美しい山道を歩いて下るというチャレンジ」は是が非でも達成したい気分だったのだろう・・・そのあたりの心情は、自分にもよくわかる ― 春先の「飯坂温泉春行脚」で15キロものリュック背負って歩き回り過ぎたせいでギックリ腰を再発した直後から、夜寝る前のエアロビバイク漕ぎを今までにも増してガンバっちゃうようになったのと、同じパターンだから・・・ただ、そうして当人はアツく燃えていても、麓で待たされる相棒の大柄男性のほうは気が気じゃあないだろう・・・ということで、とかく周りを置いてけぼりにして一人で突っ走りがちな”同類”の小柄男性の無事を祈りつつ、自分は、(11:19)発の会津鉄道に乗って会津若松へと戻る車中の人となった。
・・・それにしても、福島県内を走る列車は(新幹線を除き)どれもみな空いている ― 「便利な自家用車」への依存度の高まりから「不便な鉄道移動」に地元民が背を向けた結果、公共交通機関が衰退し、移動の足の乏しさを嫌気して外来観光客が寄り付かなくなる、という地方都市衰退の典型的図式。この会津鉄道もやはり早朝も昼時もガラガラ。休日にまでこの空きようだと経営的にはかなり困るだろうが、逆に土日祝日にだけ混雑して平日の不入りを取り戻すみたいな営業形態だとすれば、それはそれで困ったことになる ― 土日祝祭日にしか動けない大方の日本人観光客が、自分らの土地を賑わわせ儲けさせるためにわざわざ混雑した交通機関を使って休日特別料金のバカ高いお金を地元に落としに来てくれるのをヨダレ垂らして待ち構えるみたいな「蟻地獄営業」をしていたのでは、結局自分で自分の首を絞めるようなもの・・・「ヨソの観光地もみんなそうして<土日祝祭日のかき入れ時>にガッポリ稼いでる」という「右へならえ意識」で漫然と「ホリデー頼み営業」続けてる凡百の観光地を尻目に、「ウチらだけは<土日祝祭日ボッタクリ営業>に背を向けた独自路線でお客に喜んでもらう」という意識で臨んで新たな販路を切り拓く、ぐらいのことをしないと、お世辞にも盛ってるとは言えない福島県の観光地はもうほんとにダメなんじゃないか・・・と、旅人の自分としてはそう思うのだけれど、当の福島県の観光地側には、どうもそういう「独自路線で活路を開く」という意識はあまりないらしい・・・少なくとも、自分には、そういう意識で動いている「福島県の独自の姿勢」は、ここまでの三度の旅ではついぞ感じられなかった。
・・・あまりこういう文脈で持ち出すのは可哀想なのだけれど、「会津鉄道」と「JR只見線」との境界線上にある「西若松」で見た街の情景が、今でも自分の目に浮かぶ ― “悪夢”の光景としてである ― このあたりの土地には新たに転入してくる住民がよほど多いのか、新築一戸建ての家々が出来たてのホヤホヤの雰囲気を漂わせて立ち並ぶニュータウン状態になっている。そのこと自体は地元の活況を示すものなので喜ばしいのだが、そうして何十軒となく軒を連ねた幾多の新規住民の夢のマイホームたちが、どれもこれも同じ姿をしているのである。本当に誇張抜きで全く同じで何一つ外形上の違いがない家々だから、この地に住まう知り合いを訪ねて来た外来者は、何度訪れてもきっと毎回迷子になることだろう。これは「マンモス団地」の中でなら昔からよくある事態だが、一戸建ての新築住宅の建ち並ぶニュータウンでのそうした「デジャビュ(これと同じやつ前に見たよ現象)」には、心底ゾッとするものがある ― 「オリジナリティの欠如」だけでも溜息ものだが、それよりも何よりも、”マイホーム”という人生で一番高い買い物をした「家主に対する敬意の欠落」があまりにも露骨に現れているその姿を見ると、「こういうこと平然とやらかすような地方都市に、観光客に対する新鮮で感動的なサービスの提供なんて、期待すべくもないな」という気分にさせられる・・・それぐらい、「西若松のカーボンコピー住宅のデジャビュ現象」は、ひどいものだった。当該地域の新規住民のみなさんには、折角の「夢のマイホーム」を貶すようなことを言って悪いのだが、その「夢の実現」に携わるデベロッパー側の意識のあまりの低さには、どうしても一言文句を付けずにはいられない ― そうした意識の低さは、当該地域の「観光地としてのレベルの低さ」を(かなり直接的に)示す指標となるものなのだから。
・・・マトモな個性・アイデンティティを持った外国人旅行者の目から見れば、あの情景は「ニッポンそのもの」 ― 1980年代に猛威を振るった「<個性なきアリかハチの群れ>のごとき全体主義的行動様態で全世界を席巻するジャパニーズ・コレクティブ(日本集合体)」 ― もっと具体的なイメージで言えば、「個体としての存在の重みを持たずただひたすら集合体の構成要素としてのみ機能する<Borg drones:ボーグ・ドローン>」という(明らかに当時の日本の経済侵略への恐怖から生み出された)「Star Trek: The Next Generation(新スタートレック)」(1987-1994)の”陰キャラ”の姿の具現化である・・・こういう「ボーグ・ドローンの街」を「ギャグ」として作ってみました、というのならそれは見上げたエンターティナーぶりだが、実際はもちろん「商売の手順」としてただ粛々と家を建てて売るという営みを行なったらああいうことになっちゃったわけだから、その病根は極めて深い ― それを「ビョーキ」と感じない人々の意識の分だけ、重~い話になってくるのである・・・
・・・これ、なにも「西若松の没個性住宅群」だけの話にとどまらない、今の日本&日本人すべてに関して言える「金太郎飴デジャビュ現象」の一象徴事例の話なんだけど、「いったいこいつは何言ってんだ?」って日本人がほとんどだろうということまで想像できてしまうあたりが、心底、ホラー話なのである・・・この之人冗悟(Jaugo Noto)がいったい何を言っているか、何に寒気を覚えているか、あなたには、わかりますか?
・・・まずは帰りの足の「高速バス」のチケットを入手するべく、西口のバスターミナルへ ― 今回もやはり「(15:50)発新宿バスタ行き」は余裕で買えた(値段は4300円、座席は例によって最後尾の左側) ― これであと2時間は駅周辺をうろつき回って震災・コロナ禍からの復興状況を肌身で感じ取る、という(=前々回の旅ではギックリ腰に阻まれてできなかった)行脚ができる。
・・・3/12の春行脚ではそれはそれはもう美しい光景を見せてもらった郡山駅前広場だが、今回は歩く人々の数はまばら、学生たちの姿もほとんど見えない ― あまりの暑さでみんなさっさと昼過ぎには下校しちゃったのか、はたまた本日(6/19)は何かの祝日で学校そのものが休みなのか? ― 行き交う学生の姿がないこの駅前広場は、いささかそら寒い寂しさ・・・それでもまぁ、同じ時刻の会津若松駅前のような寂寥感を催すほどの閑散ぶりではないのだが、前回(3/12)にこの広場に3時間ほども座って眺めて感じた「さすがは福島県の商都、郡山!」という「程々の人出」には程遠い閑散感である。
・・・その物足りなさは、駅前広場を後にして信号を渡って「うすい百貨店」へと続く(と、北口の外れの宝くじ売り場のおねえさんに教わった)細い通りを歩くにつれて、ますます強まって行った ― 目抜き通りを外れた横丁・裏通りのこの雰囲気は、慣れ親しんだ「池袋」・「新宿」といった東京の繁華街の裏道とまったく同じ・・・だが、その空気感に「懐かしさ」は感じない・・・こうしたうらぶれた酒場街を「なつかしい!」と感じるのは、馴染みのお店の店員・常連さんたちとの心情的つながりあってこそ ― 一度も入ったことのない郡山の「池袋/新宿場末風横丁」に対して自分が「懐かしさ」を感じる理由は、一つもないのである。
・・・「なつかしい」とは「なつく=馴れ付く」気持ちを呼び起こす雰囲気を表わす語であり、「なずむ(泥む=一箇所に拘泥してなかなか離れない)」に由来する形容詞である ― 「この場所に心惹かれる、ここから離れたくない」と感じさせる空気は、この郡山の裏通りにはない・・・が、会津若松の街並みにはそうした「なつかしさ」がある ― 人通りのほとんどない「大町通り」の『若松食堂』の”昭和のままの店構え”にも、「七日町通り」の”大正浪漫溢れる店並み”にも、思わず引き込まれる「なつかしさ」がある。前に立ち寄ったことがあるからではない ― お初にお目に掛かった瞬間に「あ、なんかなつかしい⇒何となく心引かれる⇒このまま立ち去るにはちょっと惜しい」と感じさせる何かが、会津若松の街にはあるのだ。
・・・一方、「池袋・新宿もどき」の郡山裏通りの酒場街には、そうしたなつかしさが、ない ― その細い路地を抜けた所で景色がパッと開けて、左手を見ると、出し抜けに立派な「うすい百貨店」のビルがあるのだが、この百貨店前の通りの雰囲気もまた「渋谷の裏通り」のデジャビュ(=既視感)を催させるばかりで、「なつかしさ」がない ― よく知ってるけれども、ちっともなつかしくない、心引かれないし、いつまでもそこにいたいとも思わない ― 「東京の繁華街のチンケなカーボンコピー」、「それはもう前に見たから、もぅいいよ」の食傷を誘うばかりの「うんざりデジャビュ」のゲップが出るような情景でしかないのだ。
・・・「郡山」と「会津若松」のこの「なつかしさ」の有無の違いは、いったいどこから来るのか? 自分にはほんの一言で表現できる ― 「都会と田舎の違い」である。ここでの”田舎”は100%肯定的な意味なのであるが、この語の響きを嫌うのであれば”古里”と言い換えてもよい ― 「”新しいこと”を目指して作られた街と、”古いもの”をいつまでも保ち続けている里との違い」ということである ― もっと具体的なイメージの対比で言えば、「”マンモス団地群”と”大内宿”との違い」を思い浮かべればよい ― 「郡山」と「会津若松」とでは、街の目指すところ、里の歩んできた道が、まるっきり違うのである。
・・・「福島県の商工業の都」としての郡山の歴史は極めて新しい。明治時代の初めまで「水利に乏しい不毛の原野」だった郡山は、遠く離れた猪苗代湖から水を引くという大事業によって、「農業用水」と「工業用水」と「水力発電」の恩恵を得て、一気に福島県の農業・工業・商業の中心地となり、他の地域の誰もが羨む”都会”となった ― 「安積疏水(あさかそすい)」と呼ばれるこの事業の運用が始まった1882年が、現在我々が知るような「福島随一の”都会”としての郡山」の始まりである。
・・・対する会津若松の歴史は遙かに古く、豊臣秀吉の天下統一が成った直後の1590年、この地に蒲生氏郷(がもううじさと)が移封された時に始まる。江戸時代に入り、会津藩は徳川三代将軍家光の異母弟の保科正之(ほしなまさゆき)を藩祖とする松平家の領国となり、幕末には最後の最後まで徳川に忠義を貫いた結果、戊辰戦争に於ける”賊軍”として、明治新政府の”官軍”に徹底的に叩きのめされることになる ― 1868年のことである ― 幕末の京都で会津藩に痛い目にあわされた長州藩出身者が権力の中枢にいる明治新政府にとって、この「会津戦争」は一種の意趣返しであり、その新政府肝煎りの「安積疏水」による開拓事業で一気に近代化されて福島県随一の”大都市”へと成り上がった郡山の姿を見るにつけ、古い会津の里の民は、自分たちが明治の新たな世から「置いてけぼり」を食らわされている、という感覚を強く抱いたであろうことは想像に難くない。
・・・安積疏水の大事業は、廃藩置県で俸禄を失った旧武家階層の不満の刷毛口を求めて行なわれた一連の国家事業の一つであり、必ずしも「憎い會津への長州からの面当て」ではなかったが、それまで不毛の原野でしかなかった郡山の開拓のためにこの地(今で言う「中通り」)に集められた旧士族は「會津藩に関わりのない余所の藩の出身者たち」だったため、結果的には「昔ながらの會津の里」と「新たに出来た都会の郡山」とでは、住民の質も違えば、土地の目指す方向性も違う、という対照的な構図が生じることとなった。福島県内で工業化の先端を走り続けたのは常に郡山であり、それゆえに太平洋戦争の際には「工業都市の郡山」はアメリカ軍の度重なる大規模爆撃で破壊されたが、「旧態依然の会津若松」は米軍の空襲を受けることもなかった。戦後は、焼け野原となった郡山は国から”戦災復興都市”の指定を受けて福島県の商工業の中心地としての復興・発展を遂げたが、戦災を免れた会津にはそうした国からの後押しもなかった・・・こと「近代化・工業化・都市化」に関しては、明治時代以降ず~っと郡山の一人勝ち状態 ― 県内で最も栄えた”都会”としての郡山は、福島県民にとって”glamour city:魅惑的な雰囲気のある都市”だったわけであろう・・・19世紀末から20世紀いっぱいにかけては。
・・・いま現在の郡山駅前に、かつてのグラマー(=思わず息を呑むような魅力)がなくなっていることは、外来旅行者である自分の目にも明らかである ― 駅周辺の大型店舗は「うすい百貨店」のみ、かつては集客を競った「ダイエー」・「丸井」・「西武」といったデパート群は2000年までに軒並み撤退してしまい、古来”郡山の顔”であり続けた「うすいデパート」はその老舗の意地にかけて一人ふんばってはいるが、客足の乏しさから有力テナントの流出が相次ぎ、自分が訪れた木曜の昼下がりには、人通りもまばらなデパート前の道路でタクシーが10台近く空しい客待ちの数珠つなぎ駐車場状態 ― これは「猪苗代駅前」や「会津若松駅前」とまったく同じ「停滞する地方都市」の典型的図式である。
・・・「うすい百貨店」の周辺の”疑似渋谷裏通り”にはおシャレな店舗がそこそこ並んでいるが、郡山駅前からまっすぐ伸びる「駅前大通り」の看板のある広い通りに面した商店街は空き店舗だらけで、一番目立つお店は「不動産屋」(5~6軒もある)というまるで悪い冗談のような有様、そんな寂しい駅前の目抜き通りの角地ではやたら立派なホテルの数々が「どうです、郡山って”都会的”でしょ?」と言わんばかりの空しい自己主張を繰り広げている ― ハッキリ言って、街全体がチグハグで、いったい何が売り物なのか、何をもって外来観光客を引き付けるつもりなのかが、さっぱり見えない状態である。
・・・郡山は確かに福島県の(ひいては東北地方の)交通の要衝であり、列車も道路も必ずやこの地を経由するような構造になってはいるが、今のこの有様では、郡山駅前は”経由”はしても”滞在”したい気分にさせるような場所ではない。同様の「単なる経由地でしかないな、この街は」という感覚は、3月に訪れた福島駅前に関しても抱かされたものだったが、「福島市」のアイデンティティは「官公庁の集中する都市」である(ようである)ので、その「呆れるまでの商売っ気のなさ」には目をつぶることもできるが、「郡山市」は福島県の”商都”のはずなのだから、さすがにこれではマズいだろう。
・・・明治時代の「安積疏水」開拓事業以来、「福島県内の”最先端都市”」としてのglamour(その存在自体の中からにじみ出るような魅力)をもって(地元の)人々を引き付けてきたその神通力は今では失われ、県外からの来訪者にとっては「なつかしい”田舎”の魅力」のかけらもない「東京もどき」の郡山には、新幹線や東北自動車道でこの地に集められた人々の足を引き留める力はない・・・それでも、「農業・工業」が郡山の経済的屋台骨を支えてくれるというのであれば、「商業的(≒観光的)魅力に欠ける街」という欠落は補えるかもしれないが、現代日本の産業構造では、「農地・工場の多さは福島県随一」というその立ち位置もさしたる強みとは言えないだろう。
・・・自分がこの郡山駅前広場で3時間ものバス待ちをした3/12の翌々日(3/14)には、1年前に閉店した「イトーヨーカドー」の跡地に「ヨークパーク」という名の大型商業施設がリニューアル・オープンしたという ― かたや、福島駅前で2024/5/6に閉店した「イトーヨーカドー」の跡地は、1年経ってもいまだに利用方法未定のままだだっ広い空き地として駅前一等地で惰眠をむさぼっている・・・このあたりには「商都の郡山市」と「官公庁でもつ福島市」のバイタリティの違いを感じるが、外来観光客の立場から言わせてもらえば、このような「大型ショッピングモール」は所詮「地域住民のための施設」であって、「観光客向けのアトラクション」にはなり得ない ― 東京みたいな大都会で暮らす人間が旅先に求めるものは、「都会にはない田舎の魅力」なのであって、「毎度おなじみの都会的利便性」ではないのである・・・長年慣れ親しんできた「地域の象徴の大型商業施設」の相次ぐ撤退で否応もなく「落ち目」を自覚させられ続けている地元民にとっては、その種の施設の「復活」は元気の出る話ではあろうが、その種の「地元民のための施設」をいくら復活させたところで「観光客への訴求力」が高まるわけではない・・・「うちは”観光の街”ではなく”農業・工業・商業の街”だから、これでいいのだ」というのならそれでいいだろうが、果たして郡山は今でもなお「観光要らず」の「福島随一の農業・工業・商業の都」という立ち位置を目指しているのか、それで食っていけるのか、そのあたりには ― 今の郡山駅周辺の惨状と今後の日本経済の構造変化からして ― かなり大きな疑問符が付くところである。
・・・そんな郡山とは対照的に、良い意味で「田舎っぽさ」が残る会津若松には、「観光都市」としてのかなり大きな潜在的復活可能性がある ― その潜在力を活かして復活しよう、という進取の気概がまるっきり感じられない点は問題だが、その気になって動き出しさえすれば、現状の停滞からの脱却はさほど難しくはないだろう ― 「都会」を目指して行き詰まってしまった郡山には構造的に欠けている「なつかしさ」が、會津の里には色濃く残っているのだから。
.
.
.
.
・・・ということで、14年目の3月11日の「東日本大震災追悼復興祈念式」への献花に始まるこの之人冗悟(Jaugo Noto)の「福島県の復興を肌身で感じるための旅行脚」も、このあたりで終幕としよう ― 現地を歩いて回って肌身で感じたところでは、「震災復興」や「コロナ禍からの復活」という以前にまず、これらの地には「もはや立ち行かなくなった旧態依然たる地域構造からの脱却と新規再生」が必要なのであり、そのお手伝いをしようにも「東京の余所者からの入れ知恵」に耳を貸してくれそうな空気がまったく感じられない今の福島県ではどうしようもない、というのが三度に渡る福島行脚の結論である・・・もちろん、当方の提案する「会津若松《復興》六案」に、会津の民が乗り気になってくれればそれは幸いではあるが、あいにくこの之人冗悟(Jaugo Noto)/合同会社ズバライエ(ZUBARAIE LLC.)には『この春(2025年3月)にようやく完成した<英単語完璧習得用WEB自学自習教材:QFEV=速修英単語>および<英熟語完璧習得用WEB自学自習教材:MNECOLID=銘憶英熟語>を(お客さんからきちんとお金を取る形で)売り込む』という商業的命題があるので、同じ教材を「会津若松《復興》案に動員するためのボランティア要員への<返礼品>として無料提供することで、その驚異的な効用を世間に広く周知させる」というプロモーション活動に対して「会津の民が乗り気になるのを待つ」という百年河清を待つがごとき暢気な受動的姿勢を取り続けるつもりはない・・・ので、もし「会津とはご縁がなかった」ということになれば、「会津以外で、ボランティア要員を必要とする地域で、進取の気性を持って<我が里>を新たに作り替えるべく迅速に動くだけの生存適性を持った、日本の地方都市」がこの「会津若松以外にも流用可能な《復興》案」に興味を示したなら、そちらの地との新たなご縁を結ぶ心の準備だけは(当面)整えておくことにしようと思う・・・てなわけで、旅行脚はこれにて打ち止め ― ここまで文章/音声で長らくお付き合いいただいたみなさんも、お疲れさまでした。
